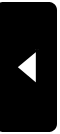スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2015年05月21日
残雪の焼岳20150520
上高地や乗鞍の山開きが行われ、北アルプスにも人々が訪れはじめました。
全国的に晴天の中、北アルプスの中でもある意味活気のある焼岳を登ってきました。

新中のノ湯ルート登山口です。登山口には軽自動車1台とバイクが1台いました。
登山口は雪で塞がれていますが右側のパイロンから進んで行きます。

登山道はまだ雪がたっぷり。マーキングを頼りに進んで行きます。
樹林帯が続く中、ようやくりんどう平手前にて山頂部が見えて来ました。

いよいよ下堀沢。無雪期の登山道は沢の右にありますが、今日は雪渓を登っていきます。
所々に落石が見えます。石と雪崩とクレパスに注意を払いながら登って行きます。

晴天の為、ゆるむ雪をキックステップとストックで進みます。

あとこれはオススメ!スマートフォン用の「山と高原地図」見慣れたマップに現在地を示してくれます。

出発から約3時間で2300mの岩まで到着。火口まではあと少し!

お鉢に到着。もちろん噴煙は相変わらずの勢いです。
ちなみに焼岳の大噴火で大正池ができて今年で100年です。

出発から約3:40で北峰山頂へ。雪渓残る北アルプスを一望してきました。
山頂にて1:20程休憩後下山を開始。雪渓をグリセードで一気に下降。
1:20程で無事登山口に戻ってきました。
8:30中の湯登山口→10:10りんどう平→11:50焼岳火口→12:10焼岳北峰(昼食)
→13:30焼岳火口→14:00りんどう平→15:20中の湯登山口
※現在、焼岳は噴火警戒レベル2になっています。登山の際は細心の注意をお願いします。
全国的に晴天の中、北アルプスの中でもある意味活気のある焼岳を登ってきました。

新中のノ湯ルート登山口です。登山口には軽自動車1台とバイクが1台いました。
登山口は雪で塞がれていますが右側のパイロンから進んで行きます。

登山道はまだ雪がたっぷり。マーキングを頼りに進んで行きます。
樹林帯が続く中、ようやくりんどう平手前にて山頂部が見えて来ました。

いよいよ下堀沢。無雪期の登山道は沢の右にありますが、今日は雪渓を登っていきます。
所々に落石が見えます。石と雪崩とクレパスに注意を払いながら登って行きます。

晴天の為、ゆるむ雪をキックステップとストックで進みます。

あとこれはオススメ!スマートフォン用の「山と高原地図」見慣れたマップに現在地を示してくれます。

出発から約3時間で2300mの岩まで到着。火口まではあと少し!

お鉢に到着。もちろん噴煙は相変わらずの勢いです。
ちなみに焼岳の大噴火で大正池ができて今年で100年です。

出発から約3:40で北峰山頂へ。雪渓残る北アルプスを一望してきました。
山頂にて1:20程休憩後下山を開始。雪渓をグリセードで一気に下降。
1:20程で無事登山口に戻ってきました。
8:30中の湯登山口→10:10りんどう平→11:50焼岳火口→12:10焼岳北峰(昼食)
→13:30焼岳火口→14:00りんどう平→15:20中の湯登山口
※現在、焼岳は噴火警戒レベル2になっています。登山の際は細心の注意をお願いします。
2015年05月10日
池ケ原湿原ハイキング20150510
今日は去年からグリーンツアーに新コースとして設定された、池ケ原湿原ハイキングに行って来ました。連休の終わった日曜日で天気良し、今年は雪が多かったので水芭蕉も例年より多く霜の影響もないベストコンディションでした。

ご参加の方は全部で12名、ガイドスタッフ3名の15名です。駐車場で早速恒例のストレッチ。
水芭蕉もリュウキンカもたくさん咲いています。

大きなイワナもお待ちかね(笑)

大野ガイドの説明を受けながら木道を進みます。

先日は未だ咲いていなかったエンレイソウ。今日のお客様には尾瀬のガイドさんや植物に詳しい方もいらっしゃって、こちらも勉強になりました。

これまたグリーンツアー恒例のおにぎり弁当。今日も美味しく頂きます。

池ケ原の後は、棚田と板倉の里「種蔵」へ回りました。

トチノキや桐の花が咲き始めてのどかな風景が楽しめます。

最後に添乗員さんからおやつが配られました。初夏の飛騨の銘菓「あねかえし」です。
ことしから地元バス会社さんもGW期間を含めて池ケ原湿原ツアーを初められましたが、我がグリーンツアーはなかなか違いのわかる内容になったようです。地元参加のお客様もしっかり違いを実感されました(笑)
夏のツアーの予定が発表されました。
・天生湿原 6月28日(日) 大人6,500円
・乗鞍岳ご来光トレッキング 7月26日(日) 大人8,000円 (早朝発)
・乗鞍岳お花畑 7月27日(月) 大人7,500円
是非皆様のご参加をお待ちいたしております。

ご参加の方は全部で12名、ガイドスタッフ3名の15名です。駐車場で早速恒例のストレッチ。
水芭蕉もリュウキンカもたくさん咲いています。

大きなイワナもお待ちかね(笑)

大野ガイドの説明を受けながら木道を進みます。

先日は未だ咲いていなかったエンレイソウ。今日のお客様には尾瀬のガイドさんや植物に詳しい方もいらっしゃって、こちらも勉強になりました。

これまたグリーンツアー恒例のおにぎり弁当。今日も美味しく頂きます。

池ケ原の後は、棚田と板倉の里「種蔵」へ回りました。

トチノキや桐の花が咲き始めてのどかな風景が楽しめます。

最後に添乗員さんからおやつが配られました。初夏の飛騨の銘菓「あねかえし」です。
ことしから地元バス会社さんもGW期間を含めて池ケ原湿原ツアーを初められましたが、我がグリーンツアーはなかなか違いのわかる内容になったようです。地元参加のお客様もしっかり違いを実感されました(笑)
夏のツアーの予定が発表されました。
・天生湿原 6月28日(日) 大人6,500円
・乗鞍岳ご来光トレッキング 7月26日(日) 大人8,000円 (早朝発)
・乗鞍岳お花畑 7月27日(月) 大人7,500円
是非皆様のご参加をお待ちいたしております。
2015年04月04日
高山グリーンツアー「池ヶ原湿原ハイキング」募集のお知らせ
今年もいろいろな飛騨の自然をご紹介していきたいと思います。
そして今年度、第1回目のツアーは昨年大変ご好評をいただきました
飛騨の尾瀬「池ヶ原湿原ハイキング」を開催いたします。
飛騨の山奥に突然と現れる大湿原の中をのんびりと散策します。
湿原一面に咲く水芭蕉は一見の価値あり。

興味のある方は是非ご参加ください。
◎催行日
○2015年5月10日(日)
池ヶ原ハイキングの詳細は以下のリンクからどうぞ。
http://www.takayama-gh.com/ankinitour/shizen/ikegahara_hiking/index.html
昨年のレポートはこちら。
http://tgtour.hida-ch.com/d2014-05.html
そして今年度、第1回目のツアーは昨年大変ご好評をいただきました
飛騨の尾瀬「池ヶ原湿原ハイキング」を開催いたします。
飛騨の山奥に突然と現れる大湿原の中をのんびりと散策します。
湿原一面に咲く水芭蕉は一見の価値あり。

興味のある方は是非ご参加ください。
◎催行日
○2015年5月10日(日)
池ヶ原ハイキングの詳細は以下のリンクからどうぞ。
http://www.takayama-gh.com/ankinitour/shizen/ikegahara_hiking/index.html
昨年のレポートはこちら。
http://tgtour.hida-ch.com/d2014-05.html
2015年03月02日
西穂高・丸山 雪山行
久しぶりの青空。せっかくなので西穂高の丸山へ行ってきました。

ロープウェイの西穂高口駅から眺める笠ケ岳。登山届け出していざ!

さっそくロープウェイの名物「雪の回廊」。背丈より高く、まるで迷路を歩くようです。

無雪期の登山口は雪でほぼ見えません。

登山道の急登エリアになるとまさに白い白山が見えてきました。

約1時間弱で西穂山荘へ到着。90ℓのバケツをかぶった巨大雪だるまがお出迎え。

本日の第一目標の西穂山荘ラーメン。山での温かい食事はホッとします。

少し高度をあげて振り向くと焼岳と乗鞍岳が。

また、見下ろした先は先週スノーシューツアーをした上高地。

山荘から20分ほどで目的地の丸山へ。白い山々はどこを見ても感動です。

稜線はほぼ風が無かったので、多くの方が独標や西穂高を目指していました。
岐阜県では冬期の北アルプス登山は登山届けが義務化されています。
しっかりとした装備で無理をしないようお願いします。

ロープウェイの西穂高口駅から眺める笠ケ岳。登山届け出していざ!

さっそくロープウェイの名物「雪の回廊」。背丈より高く、まるで迷路を歩くようです。

無雪期の登山口は雪でほぼ見えません。

登山道の急登エリアになるとまさに白い白山が見えてきました。

約1時間弱で西穂山荘へ到着。90ℓのバケツをかぶった巨大雪だるまがお出迎え。

本日の第一目標の西穂山荘ラーメン。山での温かい食事はホッとします。

少し高度をあげて振り向くと焼岳と乗鞍岳が。

また、見下ろした先は先週スノーシューツアーをした上高地。

山荘から20分ほどで目的地の丸山へ。白い山々はどこを見ても感動です。

稜線はほぼ風が無かったので、多くの方が独標や西穂高を目指していました。
岐阜県では冬期の北アルプス登山は登山届けが義務化されています。
しっかりとした装備で無理をしないようお願いします。
2015年02月22日
上高地スノートレッキング 20150222
さて、今日は今年二度目の上高地です。参加者はご宿泊のお客様6名に地元のご参加8名スタッフ5名の計19名と久々の大所帯。10代から70代手前までの老若男女混合部隊です。今回は地元にお勤めの山のない国、オランダから男性もご参加。レンタルのスノーシューズがサイズ的に不安で、今回参加しないスタッフのものを借りてきました。出発前から楽しそうな予感です。

午前6時30分定刻通りにホテルを出発。一路釜トンネルを目指します。気になるのは天気。昨日は晴天でしたが、今日は曇のち雨の下り坂。

出発時の気温です。今日は先回に比べると格段に暖かく。トンネルを登るだけで十分汗ばんでしまいました。結局、気温は終始プラス。

日曜日で工事車両もなく快調に進んで大正池まで来ましたが、残念ながら山は見えず。それでも寒くないのは助かります。その分まだ誰も歩いていない雪の中をスノーシュで歩きまわって頂きました。

田代池にて、スノーシューがないとどうなるかと大野ガイドが解説中(笑)

いつものように河童橋で記念撮影。

こちらも恒例のバスターミナルでの昼食時のスタッフコーヒーサービス。今日は幸い風もなく19個のコップに手際よく準備していきます。

バスターミナルを出発し帰路につくと小雨が降って来ましたが、大正池を過ぎると太陽が顔を出してきました。ウーン山が見えないのが残念。

気温が高く山側の斜面からはコロコロと雪が落ちてきます。
管理人10回目の冬の上高地でした。残念ながら眺望には恵まれませんでしたが、一日中気温がプラスという陽気も初めての経験。今日は冬山の厳しさには触れること無くスノーシューを楽しんで頂けました。オランダ人のFさんにもご堪能頂けたようです。グリーンツアーのこれまでの晴天率は4割近いので、ぜひまたご参加下さい。
今日のコースタイム: 釜トンネル(07:45)-トンネル出口(08:20)-大正池(09:00-0915)-田代池(10:00-10:15)-田代橋(10:40-10:50)-河童橋(11:20-11:35)-バスターミナル昼食(11:45-12:20)-大正池(13:20-13:30)-釜トンネル(14:15)
参考(スノーシューを履いてい歩いた区間:大正池-田代池、田代橋-河童橋)

午前6時30分定刻通りにホテルを出発。一路釜トンネルを目指します。気になるのは天気。昨日は晴天でしたが、今日は曇のち雨の下り坂。

出発時の気温です。今日は先回に比べると格段に暖かく。トンネルを登るだけで十分汗ばんでしまいました。結局、気温は終始プラス。

日曜日で工事車両もなく快調に進んで大正池まで来ましたが、残念ながら山は見えず。それでも寒くないのは助かります。その分まだ誰も歩いていない雪の中をスノーシュで歩きまわって頂きました。

田代池にて、スノーシューがないとどうなるかと大野ガイドが解説中(笑)

いつものように河童橋で記念撮影。

こちらも恒例のバスターミナルでの昼食時のスタッフコーヒーサービス。今日は幸い風もなく19個のコップに手際よく準備していきます。

バスターミナルを出発し帰路につくと小雨が降って来ましたが、大正池を過ぎると太陽が顔を出してきました。ウーン山が見えないのが残念。

気温が高く山側の斜面からはコロコロと雪が落ちてきます。
管理人10回目の冬の上高地でした。残念ながら眺望には恵まれませんでしたが、一日中気温がプラスという陽気も初めての経験。今日は冬山の厳しさには触れること無くスノーシューを楽しんで頂けました。オランダ人のFさんにもご堪能頂けたようです。グリーンツアーのこれまでの晴天率は4割近いので、ぜひまたご参加下さい。
今日のコースタイム: 釜トンネル(07:45)-トンネル出口(08:20)-大正池(09:00-0915)-田代池(10:00-10:15)-田代橋(10:40-10:50)-河童橋(11:20-11:35)-バスターミナル昼食(11:45-12:20)-大正池(13:20-13:30)-釜トンネル(14:15)
参考(スノーシューを履いてい歩いた区間:大正池-田代池、田代橋-河童橋)
2015年02月09日
上高地スノートレッキング20150209
今日は今年1回目の上高地スノートレッキングです。参加者はガイド・スタッフを含む然14名。嬉しい事に内4名様がリピーターです。最低気温-6.5度でチョットはっきりしない天気の高山を予定通りに出発し一路釜トンネルまでバスを走らせます。

トンネル入口でトイレ休憩を兼ねて出発準備。釜トンネルの上高地側に新しいトンネル(上高地トンネル)の工事も行われており、月曜で車の通行も多いためトンネル内は歩道を歩きました。トンネル内の照明も落とされているので、ヘッドランプは必携です。

いつものように山岳ガイドの大野さんが要所々々で説明を加えながら上高地の奥へと進んでいきます。今日は大正池の入り口でスノーシューを履きました。信州側の天気予報では晴れマークもでていましたが、残念ながら穂高連峰は雲の中。

田代池です。時折強い風が吹き抜けて雪煙が舞っています。

田代橋からは新雪のフィールドに侵入。初めてのスノーシュに戸惑う方もありましたが、懸命に自分のトレースを作って進む方も。

河童橋で記念撮影の後、バスターミナルで昼食としました。風に悩まされながらもスタッフは恒例のコーヒーサービスを実施して喜んで頂けました。

帰り道は雪が舞って風もありまさしく冬の上高地。山が見えなかったのが残念でしたが、冬山らしい良い体験が出来たというお声も頂きました。ぜひぜひ皆様またのご参加をお待ちいたします。
今年2回目の上高地は22日です。
今日のコースタイム: 釜トンネル(07:40)-大正池(09:05-09:20)-田代池(09:55-10:05)-田代橋(10:35-10:45)-河童橋(11:20-11:30)-バスターミナル(11:40-12:15)-大正池(13:15-13:30)-釜トンネル(14:30)

トンネル入口でトイレ休憩を兼ねて出発準備。釜トンネルの上高地側に新しいトンネル(上高地トンネル)の工事も行われており、月曜で車の通行も多いためトンネル内は歩道を歩きました。トンネル内の照明も落とされているので、ヘッドランプは必携です。

いつものように山岳ガイドの大野さんが要所々々で説明を加えながら上高地の奥へと進んでいきます。今日は大正池の入り口でスノーシューを履きました。信州側の天気予報では晴れマークもでていましたが、残念ながら穂高連峰は雲の中。

田代池です。時折強い風が吹き抜けて雪煙が舞っています。

田代橋からは新雪のフィールドに侵入。初めてのスノーシュに戸惑う方もありましたが、懸命に自分のトレースを作って進む方も。

河童橋で記念撮影の後、バスターミナルで昼食としました。風に悩まされながらもスタッフは恒例のコーヒーサービスを実施して喜んで頂けました。

帰り道は雪が舞って風もありまさしく冬の上高地。山が見えなかったのが残念でしたが、冬山らしい良い体験が出来たというお声も頂きました。ぜひぜひ皆様またのご参加をお待ちいたします。
今年2回目の上高地は22日です。
今日のコースタイム: 釜トンネル(07:40)-大正池(09:05-09:20)-田代池(09:55-10:05)-田代橋(10:35-10:45)-河童橋(11:20-11:30)-バスターミナル(11:40-12:15)-大正池(13:15-13:30)-釜トンネル(14:30)
2015年02月05日
いよいよ上高地スノトレ
今シーズンの上高地スノートレッキングは2月9日(月)と22日(日)。そろそろ第一回目が近づいて来ましたので、準備を始めました。

スノーシューとストック。レンタル用はもう少しシンプルなものをご用意いたします。ほぼ1年間使っていなかったので、ストラップやパーツに緩みがないかチェックします。

大雑把にザックに詰めてみました。釜トンネルの中を歩くので小さなライトがあると便利です。直ぐ取り出せるところにパッキング。
さて、ご参加のお客様で準備中に不安になることがありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

スノーシューとストック。レンタル用はもう少しシンプルなものをご用意いたします。ほぼ1年間使っていなかったので、ストラップやパーツに緩みがないかチェックします。

大雑把にザックに詰めてみました。釜トンネルの中を歩くので小さなライトがあると便利です。直ぐ取り出せるところにパッキング。
さて、ご参加のお客様で準備中に不安になることがありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
2015年01月01日
2015年もどうぞよろしくお願いします。

いつも「高山グリーンツアー・やまやま通信」をご覧いただきありがとうございます。
本年も皆様のご期待に応えられるようさまざまな情報発信を努めてまいりますので、
相変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。
また、白川郷ライトアップや、恒例の上高地スノートレッキングを好評発売中です。
「ベテランガイドと行く上高地スノートレッキング」
◎催行日
○2014年2月9日(月)
○2014年2月22日(日)
ご予約は
http://www.takayama-gh.com/ankinitour/shizen/snowshoe/index.html
2014年11月22日
「雪の上高地スノーシュートレッキングツアー」募集開始しました。
今季も「ベテランガイドと行こう!雪の上高地スノーシュートレッキングツアー」を開催します。
毎回大好評の上高地スノートレッキングツアー。
雪と静寂につつまれた上高地。冬しか見れない景色があります。
興味のある方は是非ご参加ください。

◎催行日
○2015年2月9日(月)
○2015年2月22日(日)
上高地の詳細は以下のリンクからどうぞ。
http://www.takayama-gh.com/ankinitour/shizen/snowshoe/index.html
過去のレポートはこちら。
2014
http://tgtour.hida-ch.com/e605184.html
2013
http://tgtour.hida-ch.com/e516591.html
2012
http://tgtour.hida-ch.com/d2012-02.html
2011
http://tgtour.hida-ch.com/d2011-02.html
毎回大好評の上高地スノートレッキングツアー。
雪と静寂につつまれた上高地。冬しか見れない景色があります。
興味のある方は是非ご参加ください。

◎催行日
○2015年2月9日(月)
○2015年2月22日(日)
上高地の詳細は以下のリンクからどうぞ。
http://www.takayama-gh.com/ankinitour/shizen/snowshoe/index.html
過去のレポートはこちら。
2014
http://tgtour.hida-ch.com/e605184.html
2013
http://tgtour.hida-ch.com/e516591.html
2012
http://tgtour.hida-ch.com/d2012-02.html
2011
http://tgtour.hida-ch.com/d2011-02.html
2014年11月18日
白草山
高山付近ではめぼしい山は紅葉がおわっているらしいので下呂の「白草山」まで行ってきました。
高山を7:30に出発。
登山道へつながる黒谷林道から9:30に歩行開始。わたしたちの他には2組のグループいました。

約40分ほどで登山口へ。登山口の橋には雪が積もっています。

今年は、熊の目撃情報が多く被害も出ていますので鈴は必須です。
熊鈴の替わりに神社で購入した鈴を持って行きました。

登山口から90分で三ツ岩へ。登山道は比較的整備されていて登りやすい道です。

三ツ岩から約5分。箱岩山との分岐があります。分岐点を抜けると広大な稜線が広がっていました。
しかも、雪が降ったあとなのでまさに白草山の名にふさわしい景色となりました。
コースタイム
黒谷林道ゲート(09:30)-白草山登山道口(10:10)-三ツ岩(11:30)-山頂分岐点(11:35)-白草山山頂(11:50)-昼食- 白草山登山口(14:10)-黒谷林道ゲート(14:40)休憩を含む概略
高山を7:30に出発。
登山道へつながる黒谷林道から9:30に歩行開始。わたしたちの他には2組のグループいました。

約40分ほどで登山口へ。登山口の橋には雪が積もっています。

今年は、熊の目撃情報が多く被害も出ていますので鈴は必須です。
熊鈴の替わりに神社で購入した鈴を持って行きました。

登山口から90分で三ツ岩へ。登山道は比較的整備されていて登りやすい道です。

三ツ岩から約5分。箱岩山との分岐があります。分岐点を抜けると広大な稜線が広がっていました。
しかも、雪が降ったあとなのでまさに白草山の名にふさわしい景色となりました。
コースタイム
黒谷林道ゲート(09:30)-白草山登山道口(10:10)-三ツ岩(11:30)-山頂分岐点(11:35)-白草山山頂(11:50)-昼食- 白草山登山口(14:10)-黒谷林道ゲート(14:40)休憩を含む概略