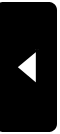スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2011年12月29日
今年も一年ありがとうございました
今年も一年このブログをご覧頂いてありがとうございました。
更新が不定期でご迷惑をお掛けしています。来年はもう少し回数を増やして投稿したいと思います。

写真は夕日に染まる焼岳です。天気のよい冬場は、こんな風景をホテルからもお楽しみ頂けます。
2月の「上高地スノートレッキング」を好評募集中です。ぜひご参加下さい。
ツアーの詳細はホテルHPおよび以下のリンクからご覧下さい。
http://www.takayama-gh.com/pdf/kamikochi12wn.pdf
それでは皆様、良いお年をお迎え下さい。
更新が不定期でご迷惑をお掛けしています。来年はもう少し回数を増やして投稿したいと思います。

写真は夕日に染まる焼岳です。天気のよい冬場は、こんな風景をホテルからもお楽しみ頂けます。
2月の「上高地スノートレッキング」を好評募集中です。ぜひご参加下さい。
ツアーの詳細はホテルHPおよび以下のリンクからご覧下さい。
http://www.takayama-gh.com/pdf/kamikochi12wn.pdf
それでは皆様、良いお年をお迎え下さい。
2011年12月04日
スノートレッキング講座 vol.3
3回目の今日はザックのお話。釜トンネル内など雪のない道やよく踏まれたトレースを歩く時はスノーシューをザックに収納します。スノーシューを留められるストラップやメッシュの収納ポケットのあるザックが便利です。

自宅でそれらしい写真を撮って見ました。ちょっとだらしなくなってしまいました(^^ゞ 前回のアルバムから、参加者が歩いている様子の写真を探してみました。

日帰りですから極端に大きなザックは必要ありませんが、防寒のための衣類や温かい飲み物を入れたサーモス(携帯用保温瓶)など荷物が多くなります。ザックは夏よりも少し大きめがお勧めです。
今年はぜひあなたもこんな風景を見に出かけませんか。

ツアーの詳細はホテルHPおよび以下のリンクからご覧下さい。
http://www.takayama-gh.com/pdf/kamikochi12wn.pdf

自宅でそれらしい写真を撮って見ました。ちょっとだらしなくなってしまいました(^^ゞ 前回のアルバムから、参加者が歩いている様子の写真を探してみました。

日帰りですから極端に大きなザックは必要ありませんが、防寒のための衣類や温かい飲み物を入れたサーモス(携帯用保温瓶)など荷物が多くなります。ザックは夏よりも少し大きめがお勧めです。
今年はぜひあなたもこんな風景を見に出かけませんか。

ツアーの詳細はホテルHPおよび以下のリンクからご覧下さい。
http://www.takayama-gh.com/pdf/kamikochi12wn.pdf
2011年12月03日
スノートレッキング講座 vol.2
シーズン中の上高地ではバスターミナルが出発点になりますが、冬のトレッキングのスタートは釜トンネルの入口です。全体で12.5キロ程の行程の中で、トンネル部分は片道1310メートル、しかもここに160メートル程の高低差があります。

トンネルの入口で出発の準備をして、暗く急なトンネルを汗をかかないようにゆっくりと歩き始めます。ここでの必需品はこれ!

このツアーにご参加の方は、忘れずにヘッドランプか小さな懐中電灯をお持ち下さい。トンネル内にはほとんど灯りもなく、工事用の車両が落とした大きな雪(氷)の塊が落ちていることもあります。ついよそ見をして前を歩く人にぶつかったり、はたまた違うグループに付いて行ってしまったり・・・。 そんなこともこれがあると安心です。カップルでご参加の場合はふたりにひとつでも大丈夫です。おっと電池の残量は必ず確認してお持ち下さいね。
このトンネルが終わると、スノートレッキングはほぼ高度差のない標高1500メートル位の平坦なルートになります。それではまた次回。
ツアーの詳細はホテルHPおよび以下のリンクからご覧下さい。
http://www.takayama-gh.com/pdf/kamikochi12wn.pdf

トンネルの入口で出発の準備をして、暗く急なトンネルを汗をかかないようにゆっくりと歩き始めます。ここでの必需品はこれ!

このツアーにご参加の方は、忘れずにヘッドランプか小さな懐中電灯をお持ち下さい。トンネル内にはほとんど灯りもなく、工事用の車両が落とした大きな雪(氷)の塊が落ちていることもあります。ついよそ見をして前を歩く人にぶつかったり、はたまた違うグループに付いて行ってしまったり・・・。 そんなこともこれがあると安心です。カップルでご参加の場合はふたりにひとつでも大丈夫です。おっと電池の残量は必ず確認してお持ち下さいね。
このトンネルが終わると、スノートレッキングはほぼ高度差のない標高1500メートル位の平坦なルートになります。それではまた次回。
ツアーの詳細はホテルHPおよび以下のリンクからご覧下さい。
http://www.takayama-gh.com/pdf/kamikochi12wn.pdf
2011年12月02日
スノートレッキング講座 vol.1
さて先日、来年2月の上高地スノートレッキングのお知らせをいたしました。これから数回に分けて初めて参加の方へのご案内を載せたいと思います。
第一回目はスノーシュー
スノーシューは雪の上を歩く道具で、日本でも「かんじき」という道具が古くから使われています。スノートレッキングではこの道具を履いて雪の上を歩きます。


ふかふかの雪の上を歩いても大きく沈まないようにプラスティックの輪っかが付いています。また裏面にはスパイクが付いており、横滑りを防ぎます。歩く時には左右のシューを踏まないように、少しがに股で歩きます。スノーシューにもたくさんの種類がありますが、高低差の少ない上高地スノートレッキングでは、写真のモデルのような軽いものが使いやすいでしょう。参加者の方には、スノーシューとストックのレンタルも承っています。

写真は大正池の手前から撮った早朝の岳沢です。ぜひ皆さんでこの景色を楽しみましょう。
ツアーの詳細はホテルHPおよび以下のリンクからご覧下さい。
http://www.takayama-gh.com/pdf/kamikochi12wn.pdf
第一回目はスノーシュー
スノーシューは雪の上を歩く道具で、日本でも「かんじき」という道具が古くから使われています。スノートレッキングではこの道具を履いて雪の上を歩きます。


ふかふかの雪の上を歩いても大きく沈まないようにプラスティックの輪っかが付いています。また裏面にはスパイクが付いており、横滑りを防ぎます。歩く時には左右のシューを踏まないように、少しがに股で歩きます。スノーシューにもたくさんの種類がありますが、高低差の少ない上高地スノートレッキングでは、写真のモデルのような軽いものが使いやすいでしょう。参加者の方には、スノーシューとストックのレンタルも承っています。

写真は大正池の手前から撮った早朝の岳沢です。ぜひ皆さんでこの景色を楽しみましょう。
ツアーの詳細はホテルHPおよび以下のリンクからご覧下さい。
http://www.takayama-gh.com/pdf/kamikochi12wn.pdf
2011年11月26日
上高地スノートレッキングのお知らせ
写真は今朝の高山からの北アルプスです。

久しぶりの快晴で冠雪した山々が綺麗に見えます。こんな日は夕日に染まる風景も期待できますね。
さて、来年の上高地スノートレッキングの詳細が決定しました。毎年好評につき来年度は2本設定となりました。いずれも2月の実施で、4日(土)宿泊・5日(日)入山と19日(日)宿泊・20日(月)入山です。一度行ってみたいけれども日曜日は都合が・・・という方もぜひご参加下さい。
詳細はこちらから:http://www.takayama-gh.com/pdf/kamikochi12wn.pdf
初めての方も大歓迎です。ぜひ白銀の上高地にご自身の足跡を残して下さい。

久しぶりの快晴で冠雪した山々が綺麗に見えます。こんな日は夕日に染まる風景も期待できますね。
さて、来年の上高地スノートレッキングの詳細が決定しました。毎年好評につき来年度は2本設定となりました。いずれも2月の実施で、4日(土)宿泊・5日(日)入山と19日(日)宿泊・20日(月)入山です。一度行ってみたいけれども日曜日は都合が・・・という方もぜひご参加下さい。
詳細はこちらから:http://www.takayama-gh.com/pdf/kamikochi12wn.pdf
初めての方も大歓迎です。ぜひ白銀の上高地にご自身の足跡を残して下さい。
2011年08月17日
鏡平・弓折岳トレッキングのお知らせ
猛暑の毎日が続いておりますが、皆様お元気ですか?
今日は9月に計画が決まった「北アルプス鏡平&弓折岳トレッキング」
のご案内です。なんとグリーンツアー初めての山小屋に泊まるツアーです。
鏡平ってどんなところ?と言う方は次の写真をご覧下さい。

こんな感じなんですが、鏡平の売りは次の景色です。

コメントは要りませんね。
ツアーの詳細は以下のPDFファイルをご覧下さい。お値段もお一人様
25,000円と大変お値打ちです。初秋の鏡平を是非お楽しみ下さい。
花の百名山「弓折岳」にも登る、とっても楽しいツアーです。
皆様のご参加をお待ちしています。ご不明の点はどしどしお問い合わせ下さい。
『写真提供:(社)岐阜県観光連盟』
今日は9月に計画が決まった「北アルプス鏡平&弓折岳トレッキング」
のご案内です。なんとグリーンツアー初めての山小屋に泊まるツアーです。
鏡平ってどんなところ?と言う方は次の写真をご覧下さい。

こんな感じなんですが、鏡平の売りは次の景色です。

コメントは要りませんね。
ツアーの詳細は以下のPDFファイルをご覧下さい。お値段もお一人様
25,000円と大変お値打ちです。初秋の鏡平を是非お楽しみ下さい。
花の百名山「弓折岳」にも登る、とっても楽しいツアーです。
皆様のご参加をお待ちしています。ご不明の点はどしどしお問い合わせ下さい。
『写真提供:(社)岐阜県観光連盟』
2011年06月22日
西穂高丸山トレッキングのお知らせ
梅雨なのにあまり雨の降らない飛騨高山です。ちょっと更新の間隔が空いてしまったこのブログですが、今日は7月のツアーのお知らせです。
「ベテランガイドと行く西穂丸山トレッキング」7月9日(土)宿泊、7月10日(日)入山。詳細はここをクリックして下さい。PDFファイルが見られない方はこちらから。
以前の写真を載せてみました。

ロープウェイを降りた千石平では「キヌガサソウ」がお待ちしているはずです。

穂高の稜線まで登ると、正面には前穂高岳の雄姿がご覧になれます。
現在お申し込みを受け付けています。ぜひ、お早めに!
「ベテランガイドと行く西穂丸山トレッキング」7月9日(土)宿泊、7月10日(日)入山。詳細はここをクリックして下さい。PDFファイルが見られない方はこちらから。
以前の写真を載せてみました。
ロープウェイを降りた千石平では「キヌガサソウ」がお待ちしているはずです。
穂高の稜線まで登ると、正面には前穂高岳の雄姿がご覧になれます。
現在お申し込みを受け付けています。ぜひ、お早めに!
2010年08月11日
乗鞍硫黄岳登山ツアー報告
ずいぶん遅れましたが、8月2日に行った乗鞍硫黄岳への登山ツアーをレポートします。
ホテルを出発する時の高山市内は霧の中でした。
盆地の霧はその日が晴れると教えてくれています。しかし梅雨明けが早かったため、8月に入ると山に雲がかかりやすくなっていました。
乗鞍硫黄岳<標高2554m>
畳平(8:10)〜桔梗ヶ原平湯登山口(9:10)〜硫黄岳頂上直下(10:45)〜北アルプス展望地点(11:00)〜戻る〜硫黄岳ふもと(11:20〜昼食〜12:00)〜旧道分岐(12:15)〜雪渓〜四ツ岳と大丹生岳の鞍部(13:10)乗鞍スカイライン〜高山着
畳平に着くと駐車場はまだガランとしていました。出発する時には団体バスが到着し始め、この日も剣ケ峰は大勢の登山者で賑わうことでしょう。
わたしたちは鶴ヶ池を見ながら乗鞍スカイラインを戻ります。
道の両わきには高山植物が咲いていました。

イワギキョウなど石垣の間から伸びているものも多く、ちょっと不思議な気分にさせられます。なにしろ生えているのは雑草ではなく高山植物なのですから。
乗鞍スカイラインを桔梗ヶ原まで下っていきます。
のんびりしたトレッキング。道沿いはお花畑。
前方には朝日を浴びた烏帽子岳が平原の向こうに見えています。

花壇のような状態でいろいろな花を観察しながら歩きました。

桔梗ヶ原に近づくと左手の斜面の下に池が見えました。
円空上人が魔物を閉じこめるために千体の木彫を沈めたと言い伝えられている大丹生池です。

別天地のような桔梗ヶ原の風景に、乗鞍スカイラインがひとすじ。
見えている2つの山は左が烏帽子岳、右が大丹生岳です。

桔梗ヶ原にはその名の通りイワギキョウが群生しています。コマクサも見られます。
枯れているハイマツはかつて乗鞍スカイラインを通ったたくさんの車の排ガスによるもの。ハイマツが枯れると自然再生は難しいとのことです。でもそのおかげで排ガスの減った沿道はハイマツではなく高山植物のお花畑になったんですね。少々複雑な心境です。
道の東側が荒れ地っぽいのに比べ、西側は緑が多くコバイケイソウやクロユリが群生している場所もありました。

畳平の方を振り返れば、剣ケ峰が見えていました。

そして右手はハイマツの向こうに硫黄岳が見えてきました。

硫黄岳、烏帽子岳、大丹生岳および猫岳は四ツ岳を囲む外輪山で、烏帽子火山帯を形成しています。外輪山である4つの山は天辺が尖っている或いは細長いのに比べ、四ツ岳はこんもりとして見えます。これは頂上が火口丘で4つに分かれているからです。四ツ岳の名称もこの形状から来ています。
かつての駐車スペースから急斜面を下ります。標柱の右手に入山口はあります。
下り着いたところは外輪山の底です。
左手にある小山の下をトラバースするようにハイマツとダケカンバの間の道を進んでいきます。
小さなピークに着いて小休止。

前方には硫黄岳が見えてきました。
ここから振り返ると四ツ岳の下に小さな雪渓が見えました。

この雪渓は平湯の旧登山道の途中にあるもので、帰りに通ってみることにしました。
ハイマツを抜け、岩が点在する尾根を登って行きます。
尾根がゆるやかになると細かい砂のザレ地となり、まだ小さなコマクサが一面に咲いていました。

その中央を通っている登山道は道とは言えず、気をつけないとコマクサを踏み荒らしてしまいます。

座れそうな岩があっても休憩は諦めた方が良いでしょう。
硫黄岳の頂上には登山道は通っていません。
その点、目的地としては物足りないかもしれません。

頂上の下をトラバースして展望の良くなる岩のあたりまで行ってみましょう。
ここで展望を楽しんだ後、来た道を引き返します。

硫黄岳を下り、コマクサの斜面を過ぎた辺りに休憩できる岩地があります。
今回はここで昼食となりました。
帰るルートはスカイライン下の急斜面を登らず、雪渓を通過して旧道を使うことにしました。
ただし長く廃道となっているため注意が必要です。今回は旧道経験者が2名いたので可能となりました。また、くれぐれも平湯方面には向かわないこと。
さっき見えていた雪渓へと向かいました。

雪渓の下は解けて、場所によっては崩れる危険があります。
雪渓歩きに詳しい経験者が通過ルートを判断して、解けて空洞ができ浮いているところは避けるようにします。
雪渓が遅くまで残るため、まわりは高山植物がお花畑を作ります。

チングルマが群生していました。
旧道は荒れてハイマツなどの薮を漕ぐところもあります。
道が消えているところはリーダーがルートを見つけるように進みます。
いったん広場に出ます。

目指す方向は大丹生岳を左手に見ながら烏帽子岳の方向の低くなっている辺り。そこに乗鞍スカイラインのヘアピンカーブの末端があります。
旧道はところどころ消えますが、跡は残っています。見失わなければ迷うことはないでしょう。
やがて原っぱのようになると終点です。

実はこの時やってきたパトロールの人から驚きの情報が。
ほんの15分ほど前に、このあたりで熊が目撃されたらしいのです。
鉢合わせとならず安堵しましたが、昨年の事件もあり緊張した一件でした。
また今回はツアー用車両を利用できましたが、個人でいかれる場合は入山路を往復し畳平へ戻るほうがよいでしょう。乗鞍スカイラインのヘアピンカーブを上るのは大変ですから。
お盆の時期を迎え、天候は不安定になりやすくなっています。
装備には十分な配慮が必要です。もしかしたら熊鈴も(笑)。
***************************************
今後のツアー
◎秋風吹く西穂高丸山へ 9月14日(火)入山
◎秋を迎えた乗鞍剣ケ峰 9月27日(月)入山
◎紅葉と北アルプス展望の天蓋山 10月13日(水)入山
◎飛騨の霊峰位山を周遊登山 10月23日(土)入山
◎上高地スノートレッキング 2月6日(日)入山
◎乗鞍高原スノートレッキング 3月6日(日)入山
ホテルを出発する時の高山市内は霧の中でした。
盆地の霧はその日が晴れると教えてくれています。しかし梅雨明けが早かったため、8月に入ると山に雲がかかりやすくなっていました。
乗鞍硫黄岳<標高2554m>
畳平(8:10)〜桔梗ヶ原平湯登山口(9:10)〜硫黄岳頂上直下(10:45)〜北アルプス展望地点(11:00)〜戻る〜硫黄岳ふもと(11:20〜昼食〜12:00)〜旧道分岐(12:15)〜雪渓〜四ツ岳と大丹生岳の鞍部(13:10)乗鞍スカイライン〜高山着
畳平に着くと駐車場はまだガランとしていました。出発する時には団体バスが到着し始め、この日も剣ケ峰は大勢の登山者で賑わうことでしょう。
わたしたちは鶴ヶ池を見ながら乗鞍スカイラインを戻ります。
道の両わきには高山植物が咲いていました。

イワギキョウなど石垣の間から伸びているものも多く、ちょっと不思議な気分にさせられます。なにしろ生えているのは雑草ではなく高山植物なのですから。
乗鞍スカイラインを桔梗ヶ原まで下っていきます。
のんびりしたトレッキング。道沿いはお花畑。
前方には朝日を浴びた烏帽子岳が平原の向こうに見えています。

花壇のような状態でいろいろな花を観察しながら歩きました。

桔梗ヶ原に近づくと左手の斜面の下に池が見えました。
円空上人が魔物を閉じこめるために千体の木彫を沈めたと言い伝えられている大丹生池です。

別天地のような桔梗ヶ原の風景に、乗鞍スカイラインがひとすじ。
見えている2つの山は左が烏帽子岳、右が大丹生岳です。

桔梗ヶ原にはその名の通りイワギキョウが群生しています。コマクサも見られます。
枯れているハイマツはかつて乗鞍スカイラインを通ったたくさんの車の排ガスによるもの。ハイマツが枯れると自然再生は難しいとのことです。でもそのおかげで排ガスの減った沿道はハイマツではなく高山植物のお花畑になったんですね。少々複雑な心境です。
道の東側が荒れ地っぽいのに比べ、西側は緑が多くコバイケイソウやクロユリが群生している場所もありました。

畳平の方を振り返れば、剣ケ峰が見えていました。

そして右手はハイマツの向こうに硫黄岳が見えてきました。

硫黄岳、烏帽子岳、大丹生岳および猫岳は四ツ岳を囲む外輪山で、烏帽子火山帯を形成しています。外輪山である4つの山は天辺が尖っている或いは細長いのに比べ、四ツ岳はこんもりとして見えます。これは頂上が火口丘で4つに分かれているからです。四ツ岳の名称もこの形状から来ています。
かつての駐車スペースから急斜面を下ります。標柱の右手に入山口はあります。
下り着いたところは外輪山の底です。
左手にある小山の下をトラバースするようにハイマツとダケカンバの間の道を進んでいきます。
小さなピークに着いて小休止。

前方には硫黄岳が見えてきました。
ここから振り返ると四ツ岳の下に小さな雪渓が見えました。

この雪渓は平湯の旧登山道の途中にあるもので、帰りに通ってみることにしました。
ハイマツを抜け、岩が点在する尾根を登って行きます。
尾根がゆるやかになると細かい砂のザレ地となり、まだ小さなコマクサが一面に咲いていました。

その中央を通っている登山道は道とは言えず、気をつけないとコマクサを踏み荒らしてしまいます。

座れそうな岩があっても休憩は諦めた方が良いでしょう。
硫黄岳の頂上には登山道は通っていません。
その点、目的地としては物足りないかもしれません。

頂上の下をトラバースして展望の良くなる岩のあたりまで行ってみましょう。
ここで展望を楽しんだ後、来た道を引き返します。

硫黄岳を下り、コマクサの斜面を過ぎた辺りに休憩できる岩地があります。
今回はここで昼食となりました。
帰るルートはスカイライン下の急斜面を登らず、雪渓を通過して旧道を使うことにしました。
ただし長く廃道となっているため注意が必要です。今回は旧道経験者が2名いたので可能となりました。また、くれぐれも平湯方面には向かわないこと。
さっき見えていた雪渓へと向かいました。

雪渓の下は解けて、場所によっては崩れる危険があります。
雪渓歩きに詳しい経験者が通過ルートを判断して、解けて空洞ができ浮いているところは避けるようにします。
雪渓が遅くまで残るため、まわりは高山植物がお花畑を作ります。

チングルマが群生していました。
旧道は荒れてハイマツなどの薮を漕ぐところもあります。
道が消えているところはリーダーがルートを見つけるように進みます。
いったん広場に出ます。

目指す方向は大丹生岳を左手に見ながら烏帽子岳の方向の低くなっている辺り。そこに乗鞍スカイラインのヘアピンカーブの末端があります。
旧道はところどころ消えますが、跡は残っています。見失わなければ迷うことはないでしょう。
やがて原っぱのようになると終点です。

実はこの時やってきたパトロールの人から驚きの情報が。
ほんの15分ほど前に、このあたりで熊が目撃されたらしいのです。
鉢合わせとならず安堵しましたが、昨年の事件もあり緊張した一件でした。
また今回はツアー用車両を利用できましたが、個人でいかれる場合は入山路を往復し畳平へ戻るほうがよいでしょう。乗鞍スカイラインのヘアピンカーブを上るのは大変ですから。
お盆の時期を迎え、天候は不安定になりやすくなっています。
装備には十分な配慮が必要です。もしかしたら熊鈴も(笑)。
***************************************
今後のツアー
◎秋風吹く西穂高丸山へ 9月14日(火)入山
◎秋を迎えた乗鞍剣ケ峰 9月27日(月)入山
◎紅葉と北アルプス展望の天蓋山 10月13日(水)入山
◎飛騨の霊峰位山を周遊登山 10月23日(土)入山
◎上高地スノートレッキング 2月6日(日)入山
◎乗鞍高原スノートレッキング 3月6日(日)入山
2010年07月23日
乗鞍硫黄岳登山ツアー
乗鞍硫黄岳への登山ツアーが10日後に迫りました。
入山日 8月2日(月)
ご宿泊とセットで、あるいはツアーだけのご参加も承っております。
ここで乗鞍硫黄岳について少し解説を。
乗鞍連峰は幾度かの火山活動によってできた複合火山。主な峰だけでも23峰あり、高山市街から眺める姿は南北に長い堂々とした山塊です。
乗鞍で登山といえば畳平から剣ケ峰を往復するコースが一般的です。
しかし夏山シーズンはとても混み合い、なかなかゆっくりとした山旅は望めません。
硫黄岳は畳平の手前にある桔梗ヶ原から平湯へ下る登山道沿いにあり、剣ケ峰とは違い歩く人も多くはありません。

乗鞍スカイラインから急なジグザグの道を下りいったん鞍部に着くと、あとはハイマツ帯を抜けて緩やかな稜線を硫黄岳へと登って行きます。
登山道は硫黄岳の頂上の下を通り、進行方向に北アルプス南部を見ながら続いていきます。
十石山との分岐からは樹林帯を平湯へ向かいますが、今回のツアーでは十石山を目前に眺める地点で戻ります。

危険個所もなく、急登もほとんどないので登山が始めての人でも無理なく楽しむことができるでしょう。
ちなみに硫黄岳と呼ばれるのは、白骨温泉乗鞍高原温泉の源泉が進行方向右にある谷から引かれているように、硫黄の匂いが微かにすることからと思われます。あくまでも想像ですが。

ぜひご自身で確かめてみては。
このツアーでの、もうひとつの楽しみは高山植物の花々です。
畳平周辺から乗鞍スカイラインの沿道には数多くの高山植物が自生しています。
マイカー規制が実施されてからの自然保護の成果を目にすることができます。
バスに乗っていると、ここまで沿道が花々で満たされていることに気がつきません。
最後に今回のツアーで見られるに違いない花々をいくつかご紹介します。

イワツメクサ

コバイケイソウ

ヨツバシオガマ、ウサギギク、そしてオンタデ

チングルマ

そして硫黄岳はコマクサの群生地です。
◎ツアーの詳細PDF
◎ツアーのお申し込みはネット予約のページで。
入山日 8月2日(月)
ご宿泊とセットで、あるいはツアーだけのご参加も承っております。
ここで乗鞍硫黄岳について少し解説を。
乗鞍連峰は幾度かの火山活動によってできた複合火山。主な峰だけでも23峰あり、高山市街から眺める姿は南北に長い堂々とした山塊です。
乗鞍で登山といえば畳平から剣ケ峰を往復するコースが一般的です。
しかし夏山シーズンはとても混み合い、なかなかゆっくりとした山旅は望めません。
硫黄岳は畳平の手前にある桔梗ヶ原から平湯へ下る登山道沿いにあり、剣ケ峰とは違い歩く人も多くはありません。

乗鞍スカイラインから急なジグザグの道を下りいったん鞍部に着くと、あとはハイマツ帯を抜けて緩やかな稜線を硫黄岳へと登って行きます。
登山道は硫黄岳の頂上の下を通り、進行方向に北アルプス南部を見ながら続いていきます。
十石山との分岐からは樹林帯を平湯へ向かいますが、今回のツアーでは十石山を目前に眺める地点で戻ります。

危険個所もなく、急登もほとんどないので登山が始めての人でも無理なく楽しむことができるでしょう。
ちなみに硫黄岳と呼ばれるのは、

ぜひご自身で確かめてみては。
このツアーでの、もうひとつの楽しみは高山植物の花々です。
畳平周辺から乗鞍スカイラインの沿道には数多くの高山植物が自生しています。
マイカー規制が実施されてからの自然保護の成果を目にすることができます。
バスに乗っていると、ここまで沿道が花々で満たされていることに気がつきません。
最後に今回のツアーで見られるに違いない花々をいくつかご紹介します。

イワツメクサ

コバイケイソウ

ヨツバシオガマ、ウサギギク、そしてオンタデ

チングルマ

そして硫黄岳はコマクサの群生地です。
◎ツアーの詳細PDF
◎ツアーのお申し込みはネット予約のページで。
2010年06月11日
今後の登山ツアー案内(7月〜9月)
7月以降のツアー催行日が決定しました。
ネットでの予約がまだ対応していませんので、よろしければ係まで電話でお申し込みください。ご宿泊もご希望の場合は、夏休み等の時期により満室となることがございますのでお早めのご予約をお願いいたします。

標高3,025mの乗鞍剣ケ峰に登る
<7月20日(火)入山>
難易度:★☆☆☆(初級者向) 体力度:★★☆☆(やや必要)
直通バスで乗鞍スカイラインを標高2,702mの畳平に到着。林道を肩ノ小屋まで歩き、いよいよ北アルプス最南端の3千m級の頂きへ。火山独特の砂礫地をゆっくりと登り、権現池を見下ろす鞍部に。あとは稜線を剣ケ峰へ一息。帰りはお高山植物の花畑へ。
[ひとこと追加コメント]梅雨明けすると一年で一番良いコンディションでの登山となります。

高山植物の道を歩き乗鞍硫黄岳へ
<8月2日(月)入山>
難易度:★☆☆☆(初級者向) 体力度:★☆☆☆(普通)
乗鞍スカイライン終点の畳平から来た道を徒歩で桔梗ヶ原まで下ると、硫黄岳を経て平湯へ向かう登山口。実はスカイラインは高山植物の群生する道。さらに硫黄岳はコマクサの群生地。乗鞍連峰のもうひとつの魅力を知る、花の山歩きを楽しもう。
[ひとこと追加コメント]梅雨明け後の安定した天候で穂高連峰が間近に見えることが多くなります。

秋風吹く西穂高丸山の稜線へ
<9月14日(火)入山>
難易度:★☆☆☆(初級者向) 体力度:★★☆☆(やや必要)
9月中旬ともなると飛騨山脈の稜線には秋風が吹き、稜線は紅葉が始まります。新緑の頃とは違う風景と空気を楽しみ、たった2ヶ月半前の同じ山を比べてみるのはいかがだろう。涼しくなるこの時期は、初めての北アルプス体験にもおすすめ。
[ひとこと追加コメント]新穂高ロープウェイでぐるりと飛騨山脈を大展望。

標高3,025mの乗鞍剣ケ峰に登る
<9月27日(月)入山>
難易度:★☆☆☆(初級者向) 体力度:★★☆☆(やや必要)
夏に続き秋の北アルプス最南端の3,000m峰に。登山シーズン終盤を迎え、すでに乗鞍スカイラインから見る高山帯は草紅葉が始まっている。晴れれば天高く深い青空が広がり、最高の登山日和に。稜線は寒いのでコンパクトな防寒着をザックにしのばせて。
[ひとこと追加コメント]夏とは違い登山客も少なくなります。ゆったりとした山行が楽しめるはず。
****************************************************
◎すでにご案内している登山ツアーです。
西穂高丸山<6月28日(月)入山>
こちらはネットでのご予約を承っております。
ツアーの詳細
ネットでの予約がまだ対応していませんので、よろしければ係まで電話でお申し込みください。ご宿泊もご希望の場合は、夏休み等の時期により満室となることがございますのでお早めのご予約をお願いいたします。

標高3,025mの乗鞍剣ケ峰に登る
<7月20日(火)入山>
難易度:★☆☆☆(初級者向) 体力度:★★☆☆(やや必要)
直通バスで乗鞍スカイラインを標高2,702mの畳平に到着。林道を肩ノ小屋まで歩き、いよいよ北アルプス最南端の3千m級の頂きへ。火山独特の砂礫地をゆっくりと登り、権現池を見下ろす鞍部に。あとは稜線を剣ケ峰へ一息。帰りはお高山植物の花畑へ。
[ひとこと追加コメント]梅雨明けすると一年で一番良いコンディションでの登山となります。

高山植物の道を歩き乗鞍硫黄岳へ
<8月2日(月)入山>
難易度:★☆☆☆(初級者向) 体力度:★☆☆☆(普通)
乗鞍スカイライン終点の畳平から来た道を徒歩で桔梗ヶ原まで下ると、硫黄岳を経て平湯へ向かう登山口。実はスカイラインは高山植物の群生する道。さらに硫黄岳はコマクサの群生地。乗鞍連峰のもうひとつの魅力を知る、花の山歩きを楽しもう。
[ひとこと追加コメント]梅雨明け後の安定した天候で穂高連峰が間近に見えることが多くなります。

秋風吹く西穂高丸山の稜線へ
<9月14日(火)入山>
難易度:★☆☆☆(初級者向) 体力度:★★☆☆(やや必要)
9月中旬ともなると飛騨山脈の稜線には秋風が吹き、稜線は紅葉が始まります。新緑の頃とは違う風景と空気を楽しみ、たった2ヶ月半前の同じ山を比べてみるのはいかがだろう。涼しくなるこの時期は、初めての北アルプス体験にもおすすめ。
[ひとこと追加コメント]新穂高ロープウェイでぐるりと飛騨山脈を大展望。

標高3,025mの乗鞍剣ケ峰に登る
<9月27日(月)入山>
難易度:★☆☆☆(初級者向) 体力度:★★☆☆(やや必要)
夏に続き秋の北アルプス最南端の3,000m峰に。登山シーズン終盤を迎え、すでに乗鞍スカイラインから見る高山帯は草紅葉が始まっている。晴れれば天高く深い青空が広がり、最高の登山日和に。稜線は寒いのでコンパクトな防寒着をザックにしのばせて。
[ひとこと追加コメント]夏とは違い登山客も少なくなります。ゆったりとした山行が楽しめるはず。
****************************************************
◎すでにご案内している登山ツアーです。
西穂高丸山<6月28日(月)入山>
こちらはネットでのご予約を承っております。
ツアーの詳細
2010年03月28日
福地山トレッキングツアー受付中
飛騨高山は3月に入り、春めいたり、また冬のようになったり気候が変化しています。
昨日の奥飛騨温泉郷では午後から吹雪となりました。
4月になると、この気候も一気に春へと向かうことでしょう。
今年度の登山・山歩きツアーのラインナップが決まりました。
催行日につきましては、夏以降がまだ決定していません。5月中にはすべての催行日を決定する予定です。
現在決定しているツアーは2つ。
◎残雪の「福地山」トレッキング 4月21日(水)入山
◎穂高連峰の稜線に立つ「西穂高丸山」 6月28日(月)入山
そこで気が早いのですが、まだ雪がたっぷりと残る福地山へ様子を見に行ってきました。
残念ながら予報通りの天候で、飛騨山脈はほとんど雲の中でした。唯一その姿を見せてくれたのは焼岳。こちらも午後には雲に隠れてしまいましたが・・・。
登山道の積雪は入山口ではさすがに少なく、上部でもスノーシューやワカンの出番はありませんでした。うっすらと積もった新雪の下は完全に締まった状態で、沈み込みもほとんどありませんでした。10日ほどすると入山口から東屋の辺りまではほとんど解けてしまう気がします。
今後は残雪がクラスト状になり足を取られ滑りやすくなるのですが、スノーシューは必要ないでしょう。むしろ足に負担がかかるので荷物を軽くする意味でも持たないほうが賢明です。
そのかわり軽アイゼンは活躍しそうです。ただし雪と枯れ葉が団子状になりアイゼンにくっつくので、道の状況を見て使うかどうかを判断することになります。着けっ放しで歩くと転倒することがありますので要注意。
現時点での東屋の上部の登山道は、まだ雪が十分残っています。

まだしばらくは本格的な春山を楽しむことができそうです。
ちなみに今回は終始雪のコンディションが良く、歩行装備を付けることはありませんでした。
無然平の直前にある分岐点は日当たりがよいので、ここだけ道の雪が消えていました。

分岐の手前と先には雪が残っています。こんな箇所がこれから増えていくでしょう。
篠原無然の小さな銅像と久しぶりの再会です。

ここから先は残雪が多くなります。
今のうちならショートカットができます。
旧登山道のある尾根の取り付きから見ると、木々の幹の周囲の雪が解けた根回りがきれいに並んでいます。

ここを右へショートカットし、尾根の左側にある新登山道に回り込みます。旧道(道とは言えない切り開き)にアプローチする踏み跡がありますが、雪のゆるむ時期にここを進むのはちょっと大変です。
新登山道はしっかりとした道ですが、急登で残雪が滑りやすいので、ゆっくりしっかり足を踏みしめて歩きました。
第三展望台の下を回り込む道だけは、終日陽が陰るので冬のようです。

ここは速やかに通過します。
西側から尾根を回り込んで東側に出ると飛騨山脈の展望が開けます。
今回は雲に隠れて残念でした。
ここから頂上へは稜線を歩き、10分もかからないうちに到着します。

焼岳はかろうじてまだ見えました。
穂高連峰や槍ケ岳、笠ケ岳の姿は雲の中。
頂上の積雪は1m弱(標識が見えているのでもっと少ないかも)。スコップで掘ると上部はクラスト状で下は凍っていました。
ツアーの時には、どのくらいの雪が残っていることか?
****************************************
高山グリーンツアー「残雪の福地山トレッキング」のお申し込みは
◎ネット予約
◎電話:0577-33-5000(代)
昨日の奥飛騨温泉郷では午後から吹雪となりました。
4月になると、この気候も一気に春へと向かうことでしょう。
今年度の登山・山歩きツアーのラインナップが決まりました。
催行日につきましては、夏以降がまだ決定していません。5月中にはすべての催行日を決定する予定です。
現在決定しているツアーは2つ。
◎残雪の「福地山」トレッキング 4月21日(水)入山
◎穂高連峰の稜線に立つ「西穂高丸山」 6月28日(月)入山
そこで気が早いのですが、まだ雪がたっぷりと残る福地山へ様子を見に行ってきました。
残念ながら予報通りの天候で、飛騨山脈はほとんど雲の中でした。唯一その姿を見せてくれたのは焼岳。こちらも午後には雲に隠れてしまいましたが・・・。
登山道の積雪は入山口ではさすがに少なく、上部でもスノーシューやワカンの出番はありませんでした。うっすらと積もった新雪の下は完全に締まった状態で、沈み込みもほとんどありませんでした。10日ほどすると入山口から東屋の辺りまではほとんど解けてしまう気がします。
今後は残雪がクラスト状になり足を取られ滑りやすくなるのですが、スノーシューは必要ないでしょう。むしろ足に負担がかかるので荷物を軽くする意味でも持たないほうが賢明です。
そのかわり軽アイゼンは活躍しそうです。ただし雪と枯れ葉が団子状になりアイゼンにくっつくので、道の状況を見て使うかどうかを判断することになります。着けっ放しで歩くと転倒することがありますので要注意。
現時点での東屋の上部の登山道は、まだ雪が十分残っています。

まだしばらくは本格的な春山を楽しむことができそうです。
ちなみに今回は終始雪のコンディションが良く、歩行装備を付けることはありませんでした。
無然平の直前にある分岐点は日当たりがよいので、ここだけ道の雪が消えていました。

分岐の手前と先には雪が残っています。こんな箇所がこれから増えていくでしょう。
篠原無然の小さな銅像と久しぶりの再会です。

ここから先は残雪が多くなります。
今のうちならショートカットができます。
旧登山道のある尾根の取り付きから見ると、木々の幹の周囲の雪が解けた根回りがきれいに並んでいます。

ここを右へショートカットし、尾根の左側にある新登山道に回り込みます。旧道(道とは言えない切り開き)にアプローチする踏み跡がありますが、雪のゆるむ時期にここを進むのはちょっと大変です。
新登山道はしっかりとした道ですが、急登で残雪が滑りやすいので、ゆっくりしっかり足を踏みしめて歩きました。
第三展望台の下を回り込む道だけは、終日陽が陰るので冬のようです。

ここは速やかに通過します。
西側から尾根を回り込んで東側に出ると飛騨山脈の展望が開けます。
今回は雲に隠れて残念でした。
ここから頂上へは稜線を歩き、10分もかからないうちに到着します。

焼岳はかろうじてまだ見えました。
穂高連峰や槍ケ岳、笠ケ岳の姿は雲の中。
頂上の積雪は1m弱(標識が見えているのでもっと少ないかも)。スコップで掘ると上部はクラスト状で下は凍っていました。
ツアーの時には、どのくらいの雪が残っていることか?
****************************************
高山グリーンツアー「残雪の福地山トレッキング」のお申し込みは
◎ネット予約
◎電話:0577-33-5000(代)
2010年03月21日
乗鞍高原スノートレッキングツアー
雪のちらつく乗鞍高原へ。大陸からの低気圧の影響で、強い風が吹いていました。
そのため、今回のツアーの唯一の難所といえば、トレッキングの出発点となる三本滝平までのリフト乗車。なにしろ風がまともに当たるのですから。
国民休暇村で車を降り、スノーシューとザックを持って、少し下ったリフト乗車口へ。
強風のため、リフトの調整に時間がかかっていました。
8時半に1本目のリフトに乗り、2本目を中継して三本滝平へ。
ゲレンデの脇にあるリスの小路に入り、林の中へ。林の中では風の影響もなく、氷点下の気温にもかかわらず、寒くはありません。

途中で正規のコースを外れ、前川林道(橋の手前が下りるポイント)に下りました。
明け方までの雪で、昨日つけたばかりの踏み跡が見当たりませんでした。
間違えずに下るには、斜め左を意識して下って行くこと。
途中で広場のような場所に出ることができたら正解です。
右方向に下ってしまうと、前川林道に沿って尾根を歩くことになり、いつまでたっても林道にたどり着けなくなりかねません。
やがて渓流の水音が聞こえてきたら、前川林道の谷に架かる橋の近くまで来ています。
崖のようになっているところを左に巻けば、前川林道の脇に下りてこられます。
あとは林道を下り、途中で左に入り、白樺の木が見えてきたら孫市平。東大ヒュッテに到着です。
孫市平の平原は風が通るので、東大ヒュッテの玄関口を借りて休憩しました。
建物と雪だまりが風よけになってくれました。
ここは乗鞍岳の恰好の展望地ですが、今回は雲に隠れて見ることができませんでした。
しかし雪の中を歩く楽しさは十分に楽しめました。スノーシューが可能にしてくれた雪の世界のアドベンチャー気分です。
東大ヒュッテから湿原を抜けて、乗鞍高原展望地に立ち寄りました。前川林道にふたたび合流しエコーラインを経由して今度は原生林の路を休暇村へ。休暇村に着いたのは12時過ぎ。これでツアーの本コースが終了しました。
時間がまだあったので、善五郎の滝を見に行くことにしました。
ここからはスノーシューはなし。雪も硬く、滝つぼまで下りて行く時に邪魔になるからです。
休暇村からふたたび遊歩道に入り、分岐を左に曲がり斜面をトラバース気味に下ると宿泊施設が見えてきます。その脇を車道に出て、まっすぐ進み標識の地点をふたたび遊歩道へ。あとは道なりに行けば善五郎の滝への階段です。

さすがにもう凍ってはいませんでしたが、雪解けが進んでいるのでしょう、水量は十分。なかなかの迫力でした。
滝見台へ登り、乗鞍がかすかでも見えることを期待しましたが残念ながら姿を現してはくれませんでした。

もし天候が良ければ、滝の上部に乗鞍岳が顔をのぞかせるツーショットを見ることができたのですが・・・。
駐車場へ戻る途中から、急に雪が本降りになってきました。まるでツアーの終了に合わせたかのように。
正直なところ、今回のツアーは天候が大変心配でした。
しかし早めの行動を心がけたこと、乗鞍高原という場所自体の比較的安全にスノートレッキングが楽しめる環境などで、無事に終えることができました。
もちろん前述の前川林道への下り方など、気をつけるべき点は多々あります。個人で行かれる時は、下調べと地形図の携帯をぜひお願いいたします。
さて、次の登山・山歩きツアーが決まりました。
◎残雪の福地山<4月21日(水)入山>
残雪の飛騨山脈を間近に眺める展望の山歩きです。福地山頂上付近では残雪歩きも楽しめるはずの4月下旬の開催としました。軽アイゼンでの安全な歩き方もガイドがレクチャーする予定です。また今年度は主に平日の開催としました。ツアー前日に宿泊される方が客室が空いていないために参加を諦められたことなどが主な理由ですが、他の登山者が少ない平日はツアー登山向きであるという利点もあります。登山はできるだけゆったりと楽しみたいですものね。
そのため、今回のツアーの唯一の難所といえば、トレッキングの出発点となる三本滝平までのリフト乗車。なにしろ風がまともに当たるのですから。
国民休暇村で車を降り、スノーシューとザックを持って、少し下ったリフト乗車口へ。
強風のため、リフトの調整に時間がかかっていました。
8時半に1本目のリフトに乗り、2本目を中継して三本滝平へ。
ゲレンデの脇にあるリスの小路に入り、林の中へ。林の中では風の影響もなく、氷点下の気温にもかかわらず、寒くはありません。

途中で正規のコースを外れ、前川林道(橋の手前が下りるポイント)に下りました。
明け方までの雪で、昨日つけたばかりの踏み跡が見当たりませんでした。
間違えずに下るには、斜め左を意識して下って行くこと。
途中で広場のような場所に出ることができたら正解です。
右方向に下ってしまうと、前川林道に沿って尾根を歩くことになり、いつまでたっても林道にたどり着けなくなりかねません。
やがて渓流の水音が聞こえてきたら、前川林道の谷に架かる橋の近くまで来ています。
崖のようになっているところを左に巻けば、前川林道の脇に下りてこられます。
あとは林道を下り、途中で左に入り、白樺の木が見えてきたら孫市平。東大ヒュッテに到着です。
孫市平の平原は風が通るので、東大ヒュッテの玄関口を借りて休憩しました。
建物と雪だまりが風よけになってくれました。
ここは乗鞍岳の恰好の展望地ですが、今回は雲に隠れて見ることができませんでした。
しかし雪の中を歩く楽しさは十分に楽しめました。スノーシューが可能にしてくれた雪の世界のアドベンチャー気分です。
東大ヒュッテから湿原を抜けて、乗鞍高原展望地に立ち寄りました。前川林道にふたたび合流しエコーラインを経由して今度は原生林の路を休暇村へ。休暇村に着いたのは12時過ぎ。これでツアーの本コースが終了しました。
時間がまだあったので、善五郎の滝を見に行くことにしました。
ここからはスノーシューはなし。雪も硬く、滝つぼまで下りて行く時に邪魔になるからです。
休暇村からふたたび遊歩道に入り、分岐を左に曲がり斜面をトラバース気味に下ると宿泊施設が見えてきます。その脇を車道に出て、まっすぐ進み標識の地点をふたたび遊歩道へ。あとは道なりに行けば善五郎の滝への階段です。

さすがにもう凍ってはいませんでしたが、雪解けが進んでいるのでしょう、水量は十分。なかなかの迫力でした。
滝見台へ登り、乗鞍がかすかでも見えることを期待しましたが残念ながら姿を現してはくれませんでした。

もし天候が良ければ、滝の上部に乗鞍岳が顔をのぞかせるツーショットを見ることができたのですが・・・。
駐車場へ戻る途中から、急に雪が本降りになってきました。まるでツアーの終了に合わせたかのように。
正直なところ、今回のツアーは天候が大変心配でした。
しかし早めの行動を心がけたこと、乗鞍高原という場所自体の比較的安全にスノートレッキングが楽しめる環境などで、無事に終えることができました。
もちろん前述の前川林道への下り方など、気をつけるべき点は多々あります。個人で行かれる時は、下調べと地形図の携帯をぜひお願いいたします。
さて、次の登山・山歩きツアーが決まりました。
◎残雪の福地山<4月21日(水)入山>
残雪の飛騨山脈を間近に眺める展望の山歩きです。福地山頂上付近では残雪歩きも楽しめるはずの4月下旬の開催としました。軽アイゼンでの安全な歩き方もガイドがレクチャーする予定です。また今年度は主に平日の開催としました。ツアー前日に宿泊される方が客室が空いていないために参加を諦められたことなどが主な理由ですが、他の登山者が少ない平日はツアー登山向きであるという利点もあります。登山はできるだけゆったりと楽しみたいですものね。
2010年03月20日
明日は乗鞍高原スノートレッキングツアー
明日にツアーを控えて、前日の下見に出かけてきました。
飛騨も良い天気でしたが、乗鞍高原も素晴らしい天候でした。
実は数日前から、21日は荒れた天気になるとの天気予報。
心配していましたが、今日になり、21日の松本方面は明け方まで雨が降り、日中は曇時々晴れという予報に変わっていました。ほっとしました。
松本市の明日の最低気温が5度C予想なので、乗鞍高原の上部のコースはー1度Cくらい。運が良ければ、新雪を楽しめるかもしれません。
やきもきしましたが、明日はなんとかツアーが実施できそうです。
ただし風が強いと予想されるので、風よけになる雨具などは必要です。もっとも、トレッキング中は森林の中を歩くので、この間の風は心配ないでしょう。休憩時に防風できるジャケットを着込むことで、体が冷えないように気をつけるためです。
肝心の雪はと言うと、まだまだ1500mあたりにはたっぷりと残り、適度に締まった理想的なコンディションです。
・・・これも1週間もすると、大きく変わってしまうことでしょう。
私見ですが、今日が乗鞍高原の春山としては最高の状態、もしくは明後日辺りもなかなかよいかもしれません。その間になる明日のトレッキングは、いったいどんな体験を私たちにもたらしてくれるのでしょうか。楽しみです。

・・・明日は残念ですが、こんな乗鞍は拝めません。
顔くらいはちょっと出してくれ〜(-_||_-)。
飛騨も良い天気でしたが、乗鞍高原も素晴らしい天候でした。
実は数日前から、21日は荒れた天気になるとの天気予報。
心配していましたが、今日になり、21日の松本方面は明け方まで雨が降り、日中は曇時々晴れという予報に変わっていました。ほっとしました。
松本市の明日の最低気温が5度C予想なので、乗鞍高原の上部のコースはー1度Cくらい。運が良ければ、新雪を楽しめるかもしれません。
やきもきしましたが、明日はなんとかツアーが実施できそうです。
ただし風が強いと予想されるので、風よけになる雨具などは必要です。もっとも、トレッキング中は森林の中を歩くので、この間の風は心配ないでしょう。休憩時に防風できるジャケットを着込むことで、体が冷えないように気をつけるためです。
肝心の雪はと言うと、まだまだ1500mあたりにはたっぷりと残り、適度に締まった理想的なコンディションです。
・・・これも1週間もすると、大きく変わってしまうことでしょう。
私見ですが、今日が乗鞍高原の春山としては最高の状態、もしくは明後日辺りもなかなかよいかもしれません。その間になる明日のトレッキングは、いったいどんな体験を私たちにもたらしてくれるのでしょうか。楽しみです。

・・・明日は残念ですが、こんな乗鞍は拝めません。
顔くらいはちょっと出してくれ〜(-_||_-)。
2010年03月11日
乗鞍高原スノートレッキングツアー
2月にはあまり降らなかった雪が、3月になって重い雪となって冬が戻ってきました。
今朝も雪がちらついていますが、気温が下がったのか軽めの雪質です。
3月21日(日)に実施予定の乗鞍高原スノートレッキングツアー。実はちょっと困っています。
実施日が連休のため、1ヶ月前にはホテル客室が満室になってしまったのです。
そのため、ご宿泊の予約がキャンセル待ち状態となり、ツアーのご宿泊込みのお申し込みができなくなってしまいました。
昨年は夏の乗鞍岳剣ケ峰登山ツアーでも同様の事態となり、ご迷惑をおかけしましたが、オフシーズンでは珍しい(うれしい?)現象です。
当ツアーは、地元の方向けに登山のみのご参加も受け付けております。他の宿泊施設をご利用の方も、同様にツアーにお申し込みいただけます。
ネット予約が満室となっているため、参加をあきらめられたお客様がいらっしゃいましたら、係まで電話にてお申し込みください。
tel.0577-33-5501(代)にて高山グリーンツアー係をご指名ください。

今朝も雪がちらついていますが、気温が下がったのか軽めの雪質です。
3月21日(日)に実施予定の乗鞍高原スノートレッキングツアー。実はちょっと困っています。
実施日が連休のため、1ヶ月前にはホテル客室が満室になってしまったのです。
そのため、ご宿泊の予約がキャンセル待ち状態となり、ツアーのご宿泊込みのお申し込みができなくなってしまいました。
昨年は夏の乗鞍岳剣ケ峰登山ツアーでも同様の事態となり、ご迷惑をおかけしましたが、オフシーズンでは珍しい(うれしい?)現象です。
当ツアーは、地元の方向けに登山のみのご参加も受け付けております。他の宿泊施設をご利用の方も、同様にツアーにお申し込みいただけます。
ネット予約が満室となっているため、参加をあきらめられたお客様がいらっしゃいましたら、係まで電話にてお申し込みください。
tel.0577-33-5501(代)にて高山グリーンツアー係をご指名ください。

2010年02月13日
上高地スノートレッキング〜おまけの焼岳
先日のツアーでご紹介し忘れました。
焼岳の雄姿です。独立峰の活火山だなっていう感じですね。

こんな姿が見られるのは、それまで天候がなかなか回復しなかったことのおかげでもあります。朝からピーカンの風景では、つまらないですものね。
もちろん最初から最後までダメな天気になることもありますけど。
今回はとってもラッキーだったと思います。
焼岳の雄姿です。独立峰の活火山だなっていう感じですね。

こんな姿が見られるのは、それまで天候がなかなか回復しなかったことのおかげでもあります。朝からピーカンの風景では、つまらないですものね。
もちろん最初から最後までダメな天気になることもありますけど。
今回はとってもラッキーだったと思います。
2010年02月10日
上高地スノートレッキング報告
上高地スノートレッキングツアー
入山日 2月7日(日)曇後晴れ
釜トンネル 8:13発〜釜トンネル出口 8:50〜林道分岐 8:50〜大正池ホテル 9:50発・大正池〜遊歩道〜田代湿原 10:45〜田代橋 11:22〜(梓川右岸)〜河童橋 11:50着<小梨平近くの梓川土手にて昼食タイム>〜出発 13:00〜(バスターミナル経由林道歩き)〜大正池 14:13着・休憩〜(大正池ホテルから林道を戻る)〜釜トンネル入口 15:40
前日からの大雪で出発からトラブル。若干遅れてホテルを出発しました。
雪が舞う中、凍結ぎみの国道158号線を釜トンネルへ。
ここ数年と比べて積雪はかなりのもの。トンネルの中まで吹き込んでいました。

雪を避け、トンネル内で入山準備。28名と人数が多いので、3つのグループに分け、各先頭と後尾にスタッフをつけて出発しました。

コースで唯一と言ってよい急斜面は釜トンネルの中。ガイドの大野さんのペースでゆっくりと歩いて行きました。
トンネルを抜けると、外はまだ雪が舞っていました。よく見ると東の上空がかすかに明るいことに気がつきました。
林道はトラック1台がやっと通れるだけの除雪がされていました。
何台か車がやってくるのでパスするのが大変です。何しろ除雪スペースに余裕がないのですから。除雪車がやってきて自動車と鉢合わせした時は見物でした。待避所確保のため除雪車がまわりの雪を除雪し始めたのです。
大正池に到着すると除雪は橋を渡って奥の作業道へ。

ここから先はたっぷりの雪の上を歩いて行きます。
大正池の全ぼうが見えてきましたが、霧のような雲に穂高は隠れていました。
大正池ホテルでトイレ休憩の後、いよいよスノーシューでトレッキングです。
ホテルの裏から大正池の河原へ下りました。すでに三脚を立てた人がいましたが、この天気ではシャッターはなかなか押せないようです。

私たちはというと、これから始るトレッキング体験にわくわくです。
遊歩道のコースを忠実にたどり、池のほとりにある木道を渡ります。昨年の閉山後に作られた手すりで、安全に歩くことができるようになっていました。

大正池の広い河原へ出て、思い思いに踏み跡をつけてみました。
15cmほど沈みますが、歩きにくいことはありませんでした。

大正池をあとに林の中へと。踏み跡は遊歩道ではなく、池の近くに沿ってつけられていました。ところどころ流れ込みにぶつかるので、雪の状態によっては踏み落ちないように気をつけます。

林の向こうに遊歩道のコースがあります。
途中で遊歩道に合流。田代池へと向かいました。
予定では田代湿原に踏み込むことにしていましたが、雪の状態がつかめずガイドの判断で中止しました。
田代池で休憩のあと、昨年に進入禁止の立て札があった湿原を回り込み、遊歩道へ合流し梓川沿いのコースを進みました。林道コースは途中から踏み跡がないので、ラッセルすることになるかもしれません。
田代橋に到着。

田代橋から見る梓川の風景は、今年の雪が多いことがよ〜く分ります。
穂高の展望がないので、距離の短い左岸ではなく、霞沢岳が展望できる右岸を選びました。
踏み跡をたどりましたが、雪が多いのでスノーシューは大活躍。
ウェストン碑のそばで、白樺の幹や枝の皮をむさぼる猿の群れに遭遇しました。

河童橋に到着しましたが、穂高連峰だけでなく焼岳も見ることはできませんでした。
一同がっかりですが、午後からに期待することに。

小梨平へ向い、梓川河畔のベンチへ。ここで昼食です。
ビジターセンターの向いに冬季トイレがあるので、河原からトイレまで雪を踏んで通路を作っておきました。
午後1時過ぎ、展望がないまま河童橋を後にしました。
帰りは夏には観光バスが行き交う林道をコースに選びました。
バスターミナルを経由して、ちょっとした壁のようになった雪の通路を歩いて行きました。

途中で振り返ると、林道の間から穂高が見え始めていました。
大正池の手前から林道をはずれて、河原に下りました。
焼岳が姿を見せていました。
そして河原からは穂高連峰が顔をのぞかせていました。

霞沢岳と六百山が深い青空にそびえていました。

皆さん、その姿に大感激。まさにご褒美です。
少し長めの休憩をとり、心行くまで大自然の中で気持ちの良い時間を楽しみました。
帰途振り返った風景は、上高地への憧れを満たすものでした。

上高地スノートレッキングは来年度も実施いたします。
どうぞご期待ください。
入山日 2月7日(日)曇後晴れ
釜トンネル 8:13発〜釜トンネル出口 8:50〜林道分岐 8:50〜大正池ホテル 9:50発・大正池〜遊歩道〜田代湿原 10:45〜田代橋 11:22〜(梓川右岸)〜河童橋 11:50着<小梨平近くの梓川土手にて昼食タイム>〜出発 13:00〜(バスターミナル経由林道歩き)〜大正池 14:13着・休憩〜(大正池ホテルから林道を戻る)〜釜トンネル入口 15:40
前日からの大雪で出発からトラブル。若干遅れてホテルを出発しました。
雪が舞う中、凍結ぎみの国道158号線を釜トンネルへ。
ここ数年と比べて積雪はかなりのもの。トンネルの中まで吹き込んでいました。

雪を避け、トンネル内で入山準備。28名と人数が多いので、3つのグループに分け、各先頭と後尾にスタッフをつけて出発しました。

コースで唯一と言ってよい急斜面は釜トンネルの中。ガイドの大野さんのペースでゆっくりと歩いて行きました。
トンネルを抜けると、外はまだ雪が舞っていました。よく見ると東の上空がかすかに明るいことに気がつきました。
林道はトラック1台がやっと通れるだけの除雪がされていました。
何台か車がやってくるのでパスするのが大変です。何しろ除雪スペースに余裕がないのですから。除雪車がやってきて自動車と鉢合わせした時は見物でした。待避所確保のため除雪車がまわりの雪を除雪し始めたのです。
大正池に到着すると除雪は橋を渡って奥の作業道へ。

ここから先はたっぷりの雪の上を歩いて行きます。
大正池の全ぼうが見えてきましたが、霧のような雲に穂高は隠れていました。
大正池ホテルでトイレ休憩の後、いよいよスノーシューでトレッキングです。
ホテルの裏から大正池の河原へ下りました。すでに三脚を立てた人がいましたが、この天気ではシャッターはなかなか押せないようです。

私たちはというと、これから始るトレッキング体験にわくわくです。
遊歩道のコースを忠実にたどり、池のほとりにある木道を渡ります。昨年の閉山後に作られた手すりで、安全に歩くことができるようになっていました。

大正池の広い河原へ出て、思い思いに踏み跡をつけてみました。
15cmほど沈みますが、歩きにくいことはありませんでした。

大正池をあとに林の中へと。踏み跡は遊歩道ではなく、池の近くに沿ってつけられていました。ところどころ流れ込みにぶつかるので、雪の状態によっては踏み落ちないように気をつけます。

林の向こうに遊歩道のコースがあります。
途中で遊歩道に合流。田代池へと向かいました。
予定では田代湿原に踏み込むことにしていましたが、雪の状態がつかめずガイドの判断で中止しました。
田代池で休憩のあと、昨年に進入禁止の立て札があった湿原を回り込み、遊歩道へ合流し梓川沿いのコースを進みました。林道コースは途中から踏み跡がないので、ラッセルすることになるかもしれません。
田代橋に到着。

田代橋から見る梓川の風景は、今年の雪が多いことがよ〜く分ります。
穂高の展望がないので、距離の短い左岸ではなく、霞沢岳が展望できる右岸を選びました。
踏み跡をたどりましたが、雪が多いのでスノーシューは大活躍。
ウェストン碑のそばで、白樺の幹や枝の皮をむさぼる猿の群れに遭遇しました。

河童橋に到着しましたが、穂高連峰だけでなく焼岳も見ることはできませんでした。
一同がっかりですが、午後からに期待することに。

小梨平へ向い、梓川河畔のベンチへ。ここで昼食です。
ビジターセンターの向いに冬季トイレがあるので、河原からトイレまで雪を踏んで通路を作っておきました。
午後1時過ぎ、展望がないまま河童橋を後にしました。
帰りは夏には観光バスが行き交う林道をコースに選びました。
バスターミナルを経由して、ちょっとした壁のようになった雪の通路を歩いて行きました。

途中で振り返ると、林道の間から穂高が見え始めていました。
大正池の手前から林道をはずれて、河原に下りました。
焼岳が姿を見せていました。
そして河原からは穂高連峰が顔をのぞかせていました。

霞沢岳と六百山が深い青空にそびえていました。

皆さん、その姿に大感激。まさにご褒美です。
少し長めの休憩をとり、心行くまで大自然の中で気持ちの良い時間を楽しみました。
帰途振り返った風景は、上高地への憧れを満たすものでした。

上高地スノートレッキングは来年度も実施いたします。
どうぞご期待ください。
2010年02月08日
上高地スノートレッキングツアー
上高地スノートレッキングツアーを2月7日行うことができました。
早朝から雪が舞い、上高地に入ってもなかなか天候がよくなりませんでした。
しかし帰りの大正池で穂高連峰が姿を見せてくれました。
ツアーの詳細はまたさせていただきますが、今日はその穂高の風景をご覧ください。

〜拡大表示できます
ご参加頂いた皆様、お疲れさまでした。
またご一緒できることを楽しみにしています。
早朝から雪が舞い、上高地に入ってもなかなか天候がよくなりませんでした。
しかし帰りの大正池で穂高連峰が姿を見せてくれました。
ツアーの詳細はまたさせていただきますが、今日はその穂高の風景をご覧ください。

〜拡大表示できます
ご参加頂いた皆様、お疲れさまでした。
またご一緒できることを楽しみにしています。
2010年02月05日
上高地スノートレッキングツアーまであと2日
いよいよ2月7日(日)は上高地スノートレッキングツアーです。
おかげさまで1月中旬には定員となり、お申し込みは締め切らせていただきました。
今週は雪が降ったり止んだりでしたが、7日は飛騨側・長野側とも良い天気になりそうです。

ご一緒させていただくスタッフも本当に楽しみにしています(^.^)/
ご参加される皆様へ老婆心ながらアドバイスを・・・
◎当日の服装等について
基本的なこととして、木綿素材の服は避けてください。特に下着は吸湿速乾性の素材を選んでください。
早朝7:30頃に釜トンネルを出発し上高地入りしますので、しばらくは大変寒く感じるでしょう。歩いているうちに体が温まり寒さも気にならなくなります。晴れて陽射しが出てくると気温も上がってきます。今度は暑くて汗をかくことでしょう。トレッキングでの服装は、こうした環境と体の変化に配慮しなくてはなりません。
具体的な例を挙げていきます。
まずは釜トンネルの歩行。行きは急坂を上るので、勇んで歩きガイドの前に出てしまうと大汗をかくことになります。すると厚めの防寒具で臨んだ寒さ対策が、釜トンネルを抜けてから汗で体を冷やしてしまう事態に。
対策としては、歩き始めは温かくして、体が温まってきたら上着または中間着を脱いで温度調節をします。そして何と言っても、ゆっくりガイドの後方をついて行くことです。
トンネルを抜けると日影の林道を歩きます。林道は冬の間も砂防工事の車両があり除雪されています。凍結していることがあるので滑らないように気をつけてください。気温が低く冷たい風が吹いています。スノーシューの出番ではまだありません。
大正池ホテルに到着して、ようやくスノーシューの出番です。歩行中に暑くなってきたら、上着または中間着を脱いで体温調節をします。
大正池ホテルには最初のトイレがあります。この後は田代橋までトイレはありません。最近トイレが近いという人は、釜トンネル到着の前に平湯バスターミナルに立ち寄りますので、ここでもトイレ休憩をとっておくととよいでしょう。
スノーシューを履いていても多少は雪に沈みます。特に新雪は裾から入りやすいので対策をとっておきます。防水性能を持つトレッキングシューズにスパッツを巻く。長めのスノーブーツを履く。あるいは裾の裏が雪の侵入を防ぐようになっているスキーウエアのパンツを履くなどが対策として考えられます。
◎ザックについて
当然ですがザックは(それもトレッキング用のザックは)必携です。それも20リットルくらいの容量は必要です。
予備の中間着、食料(ホテルで用意する弁当や行動食)、温かい飲み物を入れた保温ジャーや予備の水分(合計で1リットル以上)、トンネルを歩く時のライト(できれば頭の動きと連動して前を照らすヘッドランプが安全)と予備の電池、常用薬、汗を拭くタオルなど、トレッキングの際に持つべきものは意外と多いです。
スノーシューがザックに固定できることも大事です。スノーシューとストックを手に持って釜トンネルから大正池まで歩くのは不便です。凍った林道で転倒しそうになることも。ザックが装備を固定するストラップ付きかどうか確かめましょう。
◎その他
日焼け止めを塗る。帽子(耳が隠せるもの)、手袋は予備と合わせ二対(薄手と厚手にするのも有効な方法)を用意。携帯のバーナーとガスでコーヒーをいれても楽しい。カメラ(電池はありますか?フィルムあるいはデジカメの記録媒体は?)。携帯電話(充電しておくこと)。
地形図を持参してポイントで確かめてみる。などなど・・・
これを機会に登山を始めたくなった方は、入門書や専門雑誌(最近増えています)から足を踏み入れてみるのもよいでしょう。それに今出の登山ウエアはおしゃれです。
まずは日帰りの低山から手始めに・・・。最初は知識不足のため誰でも失敗します。でも失敗を補って余りある幸福も手に入れることでしょう。
そしてたまにはプロのガイドと山へ行ってみませんか。自己流登山で抱えた疑問や不安を解決する気持ちを持って参加すると、登山レベルを一歩上げることができるはずです。
それでは当日は体調を調えて、元気にご参加ください。
おかげさまで1月中旬には定員となり、お申し込みは締め切らせていただきました。
今週は雪が降ったり止んだりでしたが、7日は飛騨側・長野側とも良い天気になりそうです。

ご一緒させていただくスタッフも本当に楽しみにしています(^.^)/
ご参加される皆様へ老婆心ながらアドバイスを・・・
◎当日の服装等について
基本的なこととして、木綿素材の服は避けてください。特に下着は吸湿速乾性の素材を選んでください。
早朝7:30頃に釜トンネルを出発し上高地入りしますので、しばらくは大変寒く感じるでしょう。歩いているうちに体が温まり寒さも気にならなくなります。晴れて陽射しが出てくると気温も上がってきます。今度は暑くて汗をかくことでしょう。トレッキングでの服装は、こうした環境と体の変化に配慮しなくてはなりません。
具体的な例を挙げていきます。
まずは釜トンネルの歩行。行きは急坂を上るので、勇んで歩きガイドの前に出てしまうと大汗をかくことになります。すると厚めの防寒具で臨んだ寒さ対策が、釜トンネルを抜けてから汗で体を冷やしてしまう事態に。
対策としては、歩き始めは温かくして、体が温まってきたら上着または中間着を脱いで温度調節をします。そして何と言っても、ゆっくりガイドの後方をついて行くことです。
トンネルを抜けると日影の林道を歩きます。林道は冬の間も砂防工事の車両があり除雪されています。凍結していることがあるので滑らないように気をつけてください。気温が低く冷たい風が吹いています。スノーシューの出番ではまだありません。
大正池ホテルに到着して、ようやくスノーシューの出番です。歩行中に暑くなってきたら、上着または中間着を脱いで体温調節をします。
大正池ホテルには最初のトイレがあります。この後は田代橋までトイレはありません。最近トイレが近いという人は、釜トンネル到着の前に平湯バスターミナルに立ち寄りますので、ここでもトイレ休憩をとっておくととよいでしょう。
スノーシューを履いていても多少は雪に沈みます。特に新雪は裾から入りやすいので対策をとっておきます。防水性能を持つトレッキングシューズにスパッツを巻く。長めのスノーブーツを履く。あるいは裾の裏が雪の侵入を防ぐようになっているスキーウエアのパンツを履くなどが対策として考えられます。
◎ザックについて
当然ですがザックは(それもトレッキング用のザックは)必携です。それも20リットルくらいの容量は必要です。
予備の中間着、食料(ホテルで用意する弁当や行動食)、温かい飲み物を入れた保温ジャーや予備の水分(合計で1リットル以上)、トンネルを歩く時のライト(できれば頭の動きと連動して前を照らすヘッドランプが安全)と予備の電池、常用薬、汗を拭くタオルなど、トレッキングの際に持つべきものは意外と多いです。
スノーシューがザックに固定できることも大事です。スノーシューとストックを手に持って釜トンネルから大正池まで歩くのは不便です。凍った林道で転倒しそうになることも。ザックが装備を固定するストラップ付きかどうか確かめましょう。
◎その他
日焼け止めを塗る。帽子(耳が隠せるもの)、手袋は予備と合わせ二対(薄手と厚手にするのも有効な方法)を用意。携帯のバーナーとガスでコーヒーをいれても楽しい。カメラ(電池はありますか?フィルムあるいはデジカメの記録媒体は?)。携帯電話(充電しておくこと)。
地形図を持参してポイントで確かめてみる。などなど・・・
これを機会に登山を始めたくなった方は、入門書や専門雑誌(最近増えています)から足を踏み入れてみるのもよいでしょう。それに今出の登山ウエアはおしゃれです。
まずは日帰りの低山から手始めに・・・。最初は知識不足のため誰でも失敗します。でも失敗を補って余りある幸福も手に入れることでしょう。
そしてたまにはプロのガイドと山へ行ってみませんか。自己流登山で抱えた疑問や不安を解決する気持ちを持って参加すると、登山レベルを一歩上げることができるはずです。
それでは当日は体調を調えて、元気にご参加ください。
2009年11月18日
上高地スノートレッキングツアー
今日の夕方、夕陽を浴びた雲のすき間から、真っ白な笠ケ岳が見えていました。
明日の朝には、その全身を見られるかもしれません。
上高地が先日閉鎖され、釜トンネルを歩いて入山する時期となりました。
今日のホテル白樺荘さんのライブカメラをのぞいてみると、上高地は雪景色でした。
個人的な話ですが、今年の上高地へは2月にトレッキングツアーで行ったきりでした。
例年は開山中に何度か出かけていたのですが・・・長梅雨 だったせいで、ついつい行きそびれてしまいました。
だったせいで、ついつい行きそびれてしまいました。
そんなわけで、今度の連休に出かけてみたいと思っています。
昨年の12月7日に入山したときは、すっかり雪におおわれていました。

河童橋もこんな感じ。
11月だと、いったん雪が解けてしまうかもしれません。
さて、本題に・・・。
来年の2月7日(日)に、高山グリーンツアーでは「上高地スノートレッキングツアー」を催行いたします。
この時期は、冬型の天気が安定し、比較的好条件でスノートレッキングが楽しめます。
昨年も快晴に恵まれました(今回も良いとは限りませんが・・・)。
詳しくは登山・山歩きツアーの案内ページをご覧ください。
前回は早々に定員に達してしまい、お申し込みいただいてもお受けできない事態となってしまいました。そのため参加ご希望の方は、なるべくお早めにお申し込みくださるようお願いいたします。
明日の朝には、その全身を見られるかもしれません。
上高地が先日閉鎖され、釜トンネルを歩いて入山する時期となりました。
今日のホテル白樺荘さんのライブカメラをのぞいてみると、上高地は雪景色でした。
個人的な話ですが、今年の上高地へは2月にトレッキングツアーで行ったきりでした。
例年は開山中に何度か出かけていたのですが・・・長梅雨
 だったせいで、ついつい行きそびれてしまいました。
だったせいで、ついつい行きそびれてしまいました。そんなわけで、今度の連休に出かけてみたいと思っています。
昨年の12月7日に入山したときは、すっかり雪におおわれていました。

河童橋もこんな感じ。
11月だと、いったん雪が解けてしまうかもしれません。
さて、本題に・・・。
来年の2月7日(日)に、高山グリーンツアーでは「上高地スノートレッキングツアー」を催行いたします。
この時期は、冬型の天気が安定し、比較的好条件でスノートレッキングが楽しめます。
昨年も快晴に恵まれました(今回も良いとは限りませんが・・・)。
詳しくは登山・山歩きツアーの案内ページをご覧ください。
前回は早々に定員に達してしまい、お申し込みいただいてもお受けできない事態となってしまいました。そのため参加ご希望の方は、なるべくお早めにお申し込みくださるようお願いいたします。
2009年11月16日
インタープリターガイドツアー<三寺まいり>
毎年1月15日に飛騨古川で行われる伝統行事「三寺まいり」。
雪で作られた大ロウソクは、徹夜で行われる読経の際に明りが途切れないように巨大な和ロウソクを使うことに拠っているとか。
白壁土蔵に沿って流れる瀬戸川には、願を掛けて灯されたたくさんのロウソクが並びます。
若い女性たちが合掌する姿がロウソクの火に照らされて美しく見えます。

高山グリーンツアーでは、来年の三寺まいり<1月15日>にプロの案内人インタープリターによるガイドツアーを実施します。
詳しくは高山グリーンツアー案内ページをご覧ください。
雪で作られた大ロウソクは、徹夜で行われる読経の際に明りが途切れないように巨大な和ロウソクを使うことに拠っているとか。
白壁土蔵に沿って流れる瀬戸川には、願を掛けて灯されたたくさんのロウソクが並びます。
若い女性たちが合掌する姿がロウソクの火に照らされて美しく見えます。

高山グリーンツアーでは、来年の三寺まいり<1月15日>にプロの案内人インタープリターによるガイドツアーを実施します。
詳しくは高山グリーンツアー案内ページをご覧ください。