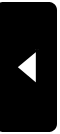スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2009年10月21日
川上岳その2
18日の川上岳ツアーでのスナップを追加します。
紅葉のピークにある木々。すでに終わりかけた木々。
夏場に陽の当たりが悪かった樹木は紅葉する前に枯れてしまっていました。
それでも秋の山は美しい。

同じ種類の木、多分ツツジ科の木が一部だけ真っ赤になっていました。
不思議で面白い自然。
登山道の上には落ち葉が敷き詰められていました。
淡い黄色の葉はコシアブラ(こんてつ)です。
5枚の小葉で1葉のため、落ちた葉は5枚まとめて落ちたように見えます。

まだら模様で秋らしい色合いのデザイン。
ついでに宮川の源流を見てきました。

この流れが高山市の真ん中へと旅をするのです。
さらに日本海へと。
川上岳は太平洋と日本海に流れていく源流の分岐点(分水嶺)のひとつ。
宮川は日本海へ、山之口川は太平洋へ。
紅葉のピークにある木々。すでに終わりかけた木々。
夏場に陽の当たりが悪かった樹木は紅葉する前に枯れてしまっていました。
それでも秋の山は美しい。

同じ種類の木、多分ツツジ科の木が一部だけ真っ赤になっていました。
不思議で面白い自然。
登山道の上には落ち葉が敷き詰められていました。
淡い黄色の葉はコシアブラ(こんてつ)です。
5枚の小葉で1葉のため、落ちた葉は5枚まとめて落ちたように見えます。

まだら模様で秋らしい色合いのデザイン。
ついでに宮川の源流を見てきました。

この流れが高山市の真ん中へと旅をするのです。
さらに日本海へと。
川上岳は太平洋と日本海に流れていく源流の分岐点(分水嶺)のひとつ。
宮川は日本海へ、山之口川は太平洋へ。
2009年10月19日
川上岳登山ツアー
昨日(10月18日)、高山グリーンツアー「登山・山歩きツアー」を行いました。
前日の夕方から雨が降り、久しぶりの雨だったこともあってか木の葉が洗われ光っていました。
数日前にガイドの大野さんが下見をした結果、予定していたルートの逆をとることとなりました。
チャーターした送迎車で一之宮町から宮川に沿って林道を進み、ツメタ林道への進入口(ゲート)で下車。
ゲートを抜けて、ツメタ林道を三差路にある登山口まで歩きました。
途中に下山口となる大イチイの分岐を確認。そこからさらに林道を上がり、登山口に到着したのは予定より少し早い8時45分、所要時間は約50分でした。
長い林道歩きで、体も登山準備万端。ロープで滑落を防止した細い尾根を登り始めます。
秋にしては霧が収まらず、昨日の雨の影響かと思われました。

それでも紅葉は今がピーク。
快晴の今日はもっと素晴らしかったことでしょう・・・少し残念です。
途中にある宮川源流へのわき道も歩いてみました。

中間点にあるベンチからは、斜面が美しく色づいている様子が眺められました。
ふたたび分岐に戻り、川上岳稜線への登りを進みました。
ここからは急登が続きます。
枯れ葉が積もり、滑りやすくなっていました。
最後にある短いが崖っぽい道を登ると稜線に出ます。
距離表示がされた標識がありますが、「川上岳頂上3.9km」は明らかに間違い。
多分登山口からの距離と思われます。

前方に目的地が見えてきます。
稜線上は曇で、風が通るので少し寒い状態でした。
サラサドウダンの紅葉は、登山道沿いは終わりに近く、笹の斜面は今がピークというところ。

山之口分岐の手前から、登って来た方向を振り返りました。
いつ見ても開放的で気持ちの良い風景です。
分岐を左折しいったん下り小ピークを越えると、左手に登ってきた登山口からの尾根が見えてきます。

ちょうど尾根の右端が登山口。
頂上まであと少し。

この辺から御嶽山が間近に見られるはずでしたが、この日は雲におおわれて見ることができませんでした。
11時半頃に頂上に到着。
温かいコーヒーを入れて、ホテルが用意したお昼のサンドウィッチをいただきました。
時々陽が射すので、御嶽が見えてこないか粘ってみましたが願いは叶いませんでした。
しかし稜線から下の斜面には赤くなったサラサドウダン。

奥にあるのは位山です。
この日は位山から尾根沿いを歩いてきた人が何組かいました。位山のスキー場からの道が整備されたため、川上岳間を往復する登山者が増えているようです。早い人で片道3時間半、平均4時間半というところのようです(つまり往復7時間から9時間・・・昼食時間入れない)。
12時半、雲行きが怪しくなってきたので下山にとりかかりました。
ほどなく雨が降り始め、雨具を着たり、笠をさしたり。
それも大イチイ分岐からは雨が止み両手が使えるようになったので、手袋をして熊笹をつかんで利用しながらの下山となりました。熊笹が有り難いと思えるのはこんな時です。
斜面の中間点では展望も開けます。

あいにく飛騨山脈は雲の中。
さらに斜面を下り、樹林帯の中へ入っていきます。
ここからは針葉樹の森の斜面に沿ったジグザグの道を下っていきます。
最後に大イチイの立つ広場に到着。

柵に囲まれた樹齢2000年の大イチイは、写真ではその大きさはよく分らないと思います。
イチイはさほど大きくならない樹木らしいので、この個体がこの大きさを持つことが大変なことなのでしょう。
広場の先の壊れかけた木橋を渡り、坂を上がれば朝歩いてきたツメタ林道です。
ここからゲートまでは15分ほど。
途中で振り返れば、下山してきた斜面が見えていました。

ホテルに戻り、ご参加のお客様に新しくなった温泉「新天領の湯」に入って汗を流していただきました。
飛騨の低山は、今月いっぱいで紅葉のピークを終えることでしょう。
飛騨山脈の穂高から槍ケ岳の稜線はもう雪でおおわれています。

秋はあっという間に過ぎてしまいます。これから登山にお出かけの時は、冬を想定した服装・装備を用意すると安心です。
前日の夕方から雨が降り、久しぶりの雨だったこともあってか木の葉が洗われ光っていました。
数日前にガイドの大野さんが下見をした結果、予定していたルートの逆をとることとなりました。
チャーターした送迎車で一之宮町から宮川に沿って林道を進み、ツメタ林道への進入口(ゲート)で下車。
ゲートを抜けて、ツメタ林道を三差路にある登山口まで歩きました。
途中に下山口となる大イチイの分岐を確認。そこからさらに林道を上がり、登山口に到着したのは予定より少し早い8時45分、所要時間は約50分でした。
長い林道歩きで、体も登山準備万端。ロープで滑落を防止した細い尾根を登り始めます。
秋にしては霧が収まらず、昨日の雨の影響かと思われました。

それでも紅葉は今がピーク。
快晴の今日はもっと素晴らしかったことでしょう・・・少し残念です。
途中にある宮川源流へのわき道も歩いてみました。

中間点にあるベンチからは、斜面が美しく色づいている様子が眺められました。
ふたたび分岐に戻り、川上岳稜線への登りを進みました。
ここからは急登が続きます。
枯れ葉が積もり、滑りやすくなっていました。
最後にある短いが崖っぽい道を登ると稜線に出ます。
距離表示がされた標識がありますが、「川上岳頂上3.9km」は明らかに間違い。
多分登山口からの距離と思われます。

前方に目的地が見えてきます。
稜線上は曇で、風が通るので少し寒い状態でした。
サラサドウダンの紅葉は、登山道沿いは終わりに近く、笹の斜面は今がピークというところ。

山之口分岐の手前から、登って来た方向を振り返りました。
いつ見ても開放的で気持ちの良い風景です。
分岐を左折しいったん下り小ピークを越えると、左手に登ってきた登山口からの尾根が見えてきます。

ちょうど尾根の右端が登山口。
頂上まであと少し。

この辺から御嶽山が間近に見られるはずでしたが、この日は雲におおわれて見ることができませんでした。
11時半頃に頂上に到着。
温かいコーヒーを入れて、ホテルが用意したお昼のサンドウィッチをいただきました。
時々陽が射すので、御嶽が見えてこないか粘ってみましたが願いは叶いませんでした。
しかし稜線から下の斜面には赤くなったサラサドウダン。

奥にあるのは位山です。
この日は位山から尾根沿いを歩いてきた人が何組かいました。位山のスキー場からの道が整備されたため、川上岳間を往復する登山者が増えているようです。早い人で片道3時間半、平均4時間半というところのようです(つまり往復7時間から9時間・・・昼食時間入れない)。
12時半、雲行きが怪しくなってきたので下山にとりかかりました。
ほどなく雨が降り始め、雨具を着たり、笠をさしたり。
それも大イチイ分岐からは雨が止み両手が使えるようになったので、手袋をして熊笹をつかんで利用しながらの下山となりました。熊笹が有り難いと思えるのはこんな時です。
斜面の中間点では展望も開けます。

あいにく飛騨山脈は雲の中。
さらに斜面を下り、樹林帯の中へ入っていきます。
ここからは針葉樹の森の斜面に沿ったジグザグの道を下っていきます。
最後に大イチイの立つ広場に到着。

柵に囲まれた樹齢2000年の大イチイは、写真ではその大きさはよく分らないと思います。
イチイはさほど大きくならない樹木らしいので、この個体がこの大きさを持つことが大変なことなのでしょう。
広場の先の壊れかけた木橋を渡り、坂を上がれば朝歩いてきたツメタ林道です。
ここからゲートまでは15分ほど。
途中で振り返れば、下山してきた斜面が見えていました。

ホテルに戻り、ご参加のお客様に新しくなった温泉「新天領の湯」に入って汗を流していただきました。
飛騨の低山は、今月いっぱいで紅葉のピークを終えることでしょう。
飛騨山脈の穂高から槍ケ岳の稜線はもう雪でおおわれています。

秋はあっという間に過ぎてしまいます。これから登山にお出かけの時は、冬を想定した服装・装備を用意すると安心です。
2009年09月15日
秋は低山がおすすめ
乗鞍では初氷が張ったとか。初雪もそのうちに降ることでしょう。
2500mくらいの高い山では紅葉も始っています。10月上旬には見ごろです。
でも秋は標高の低い山もいいものです。
特に紅葉が始り、落葉し、晩秋の枯れ葉を踏みしめて歩くまで、秋の登山の楽しみは続きます。
高山グリーンツアーでは10月に2つのトレッキングを予定しています。
1つは川上岳(かおれだけ)。
このブログでも何度か紹介しています。
2つ目は位山。
こちらも今年の春先に紹介しています。
先日、川上岳の様子を見に行ってきました。
入山口は高山市にあるツメタ林道です。
厳密にはツメタ林道登山口は一般車通行止めの林道ゲートです。
徒歩で林道を上がっていくと、橋を渡ったすぐに「宮の大イチイ」の看板があり、ここが第1の入山口です。しかし正式にツメタ林道入山口となっているのはもっと先にあります。
ツメタ林道入山口から川上岳に登るルートは往復が一般的です。コースも整備がされています。
しかし変化があっておもしろいのは大イチイの入山口から川上岳と位山を結ぶ稜線に乗越し、頂上からツメタ林道入山口へ周回するルートです。
9月6日に、下見を兼ねてこのルートをたどってみました。以前に歩いてからほぼ2年ぶりでした。
一之宮支所の前の道をまっすぐ、位山へ向かうカーブを曲がらないで、宮川沿いに進んでいくとヌクイ谷の林道です。
途中から林道は荒れてきますが、普通車で通行に問題はありません。ただし大雨の時は注意が必要です。
この林道に入ってくるのは渓流釣り客くらいのもので、登山者は山之口に比べ大変少ないと思います。
宮川防災ダムの1キロほど手前にツメタ林道の入口があります。前述のようにゲートは閉まっています。平日は道路工事車両が作業をしていることがあります。
ゲート手前に車を停めて林道に入ります。以前は砂利がむき出しの荒れた道でしたが、粘土質の土でおおわれていました。この土が靴の底にこびりつくと、湿った場所や石の上が滑りやすくなります。今回、ビブラムソールの滑り止め効果が発揮されないことが多々あり、後で考えたらどうも粘土質の土が原因だったような気がします。
ツメタ林道を進むと途中に流れ込みがあり、そこに架かる橋を渡るとすぐに宮の大イチイの看板が現れます。(ちなみに・・・林道のさらに先にもう一つ橋があります)
沢に向かう道を下りると木橋が架かっています。

橋は壊れる寸前です。特に渡り終える最後の橋板数枚が傾いて滑るのです(粘土質の土のせいかもしれません)。
渓流を渡ったら橋の左下の岩場に下りたほうが安全だと思います。
宮の大イチイはサクに囲われて10mほど奥に立っています。

しかし全貌はよく分りません。周辺の木々の葉が落ちた後の方が、姿が見えやすくなるでしょう。
登山道は急な斜面をジグザグに上って行きます。
何度か繰り返した後、前方が明るくなりいったん尾根に出ます。
短い尾根から左手にこれから乗越す川上岳への稜線が見えてきます。
しばらく登ってまたトラバースすると、笹の斜面が現れます。
周囲の木を伐採された笹の尾根を登って行きます。見晴らしは少し良くなります。
天候によっては北アルプスが展望できるはずです。

しかし笹が伸び放題でした。
普段はしないのですが、顔にかかる笹を折っては前へ進んだので、少しは歩きやすくなっているはずです。
時間をかけて尾根を登り、ふたたびジグザグの道になれば稜線まではもうすぐです。
それまで角度のあった道が突然平坦になり、ようやく位山から伸びてきた稜線に乗越したことが分ります。

登山道に合流したら、標識に従い南へ向かいます。
アップダウンを繰り返しますが、大したことはありません。

紅葉の時期には楽しみな稜線です。
川上岳頂上まであと少し。振り返ると位山(左)が見えてきました。

右奥が舟山です。頂上にはテレビの鉄塔が林立しています。
背の高い木がほとんどなくなり、周囲の見晴らしが良くなりました。
左手には御嶽が間近に見えます。位山の後方遥かには乗鞍や穂高連峰が。
そして頂上が見えてきます。

休日はいつも多くの登山者がいる頂上ですが、この日は中年男性がひとりだけ。
しかし実は直前まで、還暦祝いのタスキをかけた男性とそのお仲間で頂上は賑わっていたとか。
下山する頃にはご夫婦が一組登ってきました。
川上岳の頂上から見晴らしの良い道を歩いていきます。

左の小ピークから右奥のピークへ。
何と、ドウダンツツジのいくつかがすでに紅葉を迎えていました。

小ピークを越えると山之口へ向かう道との分岐があり、わたしは右に折れて前述のピークへと進みます。
小ピークからの下りは意外と急です。枯れた笹が滑りやすく転ばないように気をつけて。
ピークへ何度か登り返し、距離標識のあるピークに着くと登山道が直角におれて樹林帯の中へと入っていきます。
ここでいきなり急な下りが。下りきる直前の石の上で気をつけていたにもかかわらず見事に滑りました。しりもちを着く直前に両手で身体を支えて事無きを得ました。・・・この時、やけに今日は滑るなぁと首をひねりました。靴底を見るとうっすらと乾いた土でコーティングされたようになっていました。あの粘土質の土です。
この後は、ほとんどが急な尾根の下りが続くので、いつもに増して慎重に歩きました。
中間点辺りには新しく宮川の源流域へ行ける道ができていました。
その先に、1404m地点があります。

木々の間から川上岳が見えています。
ツメタ林道の入山口手前は林道のために尾根が削られて細くなっています。
そのためロープや杭で安全が図られていますが、十分に気をつける必要があります。
以前、関東の或る登山道の同様な場所で女性が足を滑らせて林道に落下し亡くなられた事故がありました。

下山後はツメタ林道を下ります。
林道から望む川上岳の稜線。

大イチイの入山口の手前(S字カーブを曲がりきると)登りの斜面と尾根が望めました。

ちょっと長い林道歩きですが、こうして今日の登山の余韻に浸れます。
川上岳登山ツアー<入山日:10月18日(日)>にご一緒しませんか?
詳しくは高山グリーンツアーのホームページをご覧ください。
最後に先日の奥穂高ジャンダルムでの事故のこと。
実は今回の川上岳への登りで岐阜県防災ヘリに遭遇しました。

若鮎2号機かどうか分りませんが、以前にも災害救助に飛び回っている防災ヘリを何度か見ることがありました。ただ、北アルプスの遭難救助では県警か民間ヘリの名は挙がっても、防災ヘリの名が挙がることは(私の知る限り)なかったと思います(県警ヘリなら救助のお金がかからないとか皆さんも話題にしませんか)。それが最初にニュースを知った時のちょっとした違和感でした。
今日の報道では、防災ヘリで3000m級の山岳地帯の救助経験がなかったとのことでした。遭難者の命を救うために緊急を最優先したとも言われています。ひとを救うと言う使命感には感服するとともに、その結果は残念でなりません。
また私たち登山者は自らの体調にもっと気を使わなければなりません。パーティでは仲間に遠慮して自分の不調を訴えないこともあります。それが今回の「病気遭難」となった要因かもしれません。
これからは中高年の登山はひとつのジャンルとの認識が必要です。登山の技術や知識、経験も重要ですが、体調管理も大切な世代です。
無理をしないで、楽しむ登山。そのために自分の健康について知っておきたいものです。
2500mくらいの高い山では紅葉も始っています。10月上旬には見ごろです。
でも秋は標高の低い山もいいものです。
特に紅葉が始り、落葉し、晩秋の枯れ葉を踏みしめて歩くまで、秋の登山の楽しみは続きます。
高山グリーンツアーでは10月に2つのトレッキングを予定しています。
1つは川上岳(かおれだけ)。
このブログでも何度か紹介しています。
2つ目は位山。
こちらも今年の春先に紹介しています。
先日、川上岳の様子を見に行ってきました。
入山口は高山市にあるツメタ林道です。
厳密にはツメタ林道登山口は一般車通行止めの林道ゲートです。
徒歩で林道を上がっていくと、橋を渡ったすぐに「宮の大イチイ」の看板があり、ここが第1の入山口です。しかし正式にツメタ林道入山口となっているのはもっと先にあります。
ツメタ林道入山口から川上岳に登るルートは往復が一般的です。コースも整備がされています。
しかし変化があっておもしろいのは大イチイの入山口から川上岳と位山を結ぶ稜線に乗越し、頂上からツメタ林道入山口へ周回するルートです。
9月6日に、下見を兼ねてこのルートをたどってみました。以前に歩いてからほぼ2年ぶりでした。
一之宮支所の前の道をまっすぐ、位山へ向かうカーブを曲がらないで、宮川沿いに進んでいくとヌクイ谷の林道です。
途中から林道は荒れてきますが、普通車で通行に問題はありません。ただし大雨の時は注意が必要です。
この林道に入ってくるのは渓流釣り客くらいのもので、登山者は山之口に比べ大変少ないと思います。
宮川防災ダムの1キロほど手前にツメタ林道の入口があります。前述のようにゲートは閉まっています。平日は道路工事車両が作業をしていることがあります。
ゲート手前に車を停めて林道に入ります。以前は砂利がむき出しの荒れた道でしたが、粘土質の土でおおわれていました。この土が靴の底にこびりつくと、湿った場所や石の上が滑りやすくなります。今回、ビブラムソールの滑り止め効果が発揮されないことが多々あり、後で考えたらどうも粘土質の土が原因だったような気がします。
ツメタ林道を進むと途中に流れ込みがあり、そこに架かる橋を渡るとすぐに宮の大イチイの看板が現れます。(ちなみに・・・林道のさらに先にもう一つ橋があります)
沢に向かう道を下りると木橋が架かっています。

橋は壊れる寸前です。特に渡り終える最後の橋板数枚が傾いて滑るのです(粘土質の土のせいかもしれません)。
渓流を渡ったら橋の左下の岩場に下りたほうが安全だと思います。
宮の大イチイはサクに囲われて10mほど奥に立っています。

しかし全貌はよく分りません。周辺の木々の葉が落ちた後の方が、姿が見えやすくなるでしょう。
登山道は急な斜面をジグザグに上って行きます。
何度か繰り返した後、前方が明るくなりいったん尾根に出ます。
短い尾根から左手にこれから乗越す川上岳への稜線が見えてきます。
しばらく登ってまたトラバースすると、笹の斜面が現れます。
周囲の木を伐採された笹の尾根を登って行きます。見晴らしは少し良くなります。
天候によっては北アルプスが展望できるはずです。

しかし笹が伸び放題でした。
普段はしないのですが、顔にかかる笹を折っては前へ進んだので、少しは歩きやすくなっているはずです。
時間をかけて尾根を登り、ふたたびジグザグの道になれば稜線まではもうすぐです。
それまで角度のあった道が突然平坦になり、ようやく位山から伸びてきた稜線に乗越したことが分ります。

登山道に合流したら、標識に従い南へ向かいます。
アップダウンを繰り返しますが、大したことはありません。

紅葉の時期には楽しみな稜線です。
川上岳頂上まであと少し。振り返ると位山(左)が見えてきました。

右奥が舟山です。頂上にはテレビの鉄塔が林立しています。
背の高い木がほとんどなくなり、周囲の見晴らしが良くなりました。
左手には御嶽が間近に見えます。位山の後方遥かには乗鞍や穂高連峰が。
そして頂上が見えてきます。

休日はいつも多くの登山者がいる頂上ですが、この日は中年男性がひとりだけ。
しかし実は直前まで、還暦祝いのタスキをかけた男性とそのお仲間で頂上は賑わっていたとか。
下山する頃にはご夫婦が一組登ってきました。
川上岳の頂上から見晴らしの良い道を歩いていきます。

左の小ピークから右奥のピークへ。
何と、ドウダンツツジのいくつかがすでに紅葉を迎えていました。

小ピークを越えると山之口へ向かう道との分岐があり、わたしは右に折れて前述のピークへと進みます。
小ピークからの下りは意外と急です。枯れた笹が滑りやすく転ばないように気をつけて。
ピークへ何度か登り返し、距離標識のあるピークに着くと登山道が直角におれて樹林帯の中へと入っていきます。
ここでいきなり急な下りが。下りきる直前の石の上で気をつけていたにもかかわらず見事に滑りました。しりもちを着く直前に両手で身体を支えて事無きを得ました。・・・この時、やけに今日は滑るなぁと首をひねりました。靴底を見るとうっすらと乾いた土でコーティングされたようになっていました。あの粘土質の土です。
この後は、ほとんどが急な尾根の下りが続くので、いつもに増して慎重に歩きました。
中間点辺りには新しく宮川の源流域へ行ける道ができていました。
その先に、1404m地点があります。

木々の間から川上岳が見えています。
ツメタ林道の入山口手前は林道のために尾根が削られて細くなっています。
そのためロープや杭で安全が図られていますが、十分に気をつける必要があります。
以前、関東の或る登山道の同様な場所で女性が足を滑らせて林道に落下し亡くなられた事故がありました。

下山後はツメタ林道を下ります。
林道から望む川上岳の稜線。

大イチイの入山口の手前(S字カーブを曲がりきると)登りの斜面と尾根が望めました。

ちょっと長い林道歩きですが、こうして今日の登山の余韻に浸れます。
川上岳登山ツアー<入山日:10月18日(日)>にご一緒しませんか?
詳しくは高山グリーンツアーのホームページをご覧ください。
最後に先日の奥穂高ジャンダルムでの事故のこと。
実は今回の川上岳への登りで岐阜県防災ヘリに遭遇しました。

若鮎2号機かどうか分りませんが、以前にも災害救助に飛び回っている防災ヘリを何度か見ることがありました。ただ、北アルプスの遭難救助では県警か民間ヘリの名は挙がっても、防災ヘリの名が挙がることは(私の知る限り)なかったと思います(県警ヘリなら救助のお金がかからないとか皆さんも話題にしませんか)。それが最初にニュースを知った時のちょっとした違和感でした。
今日の報道では、防災ヘリで3000m級の山岳地帯の救助経験がなかったとのことでした。遭難者の命を救うために緊急を最優先したとも言われています。ひとを救うと言う使命感には感服するとともに、その結果は残念でなりません。
また私たち登山者は自らの体調にもっと気を使わなければなりません。パーティでは仲間に遠慮して自分の不調を訴えないこともあります。それが今回の「病気遭難」となった要因かもしれません。
これからは中高年の登山はひとつのジャンルとの認識が必要です。登山の技術や知識、経験も重要ですが、体調管理も大切な世代です。
無理をしないで、楽しむ登山。そのために自分の健康について知っておきたいものです。
2009年08月23日
西穂高独標登山、無事終了。
本日、高山グリーンツアー「西穂高独標」を行いました。
コンディションは最高!
参加者全員が独標に登頂成功!・・・わたしを除く・・・
夏休み最後の日曜日とあって登山者が多く、独標に登る順番待ちに時間がかかるため、手前で荷物をデポして空身で向かっていただきました。わたしはその荷物番で、一緒の登頂ならず。
まれに見る好展望で(わたし個人は残念でしたが)、皆さん大満足の一日となられたようです。
本当にお疲れさまでした!
またご一緒できるのを楽しみにしております。

登山者が行列を成す独標への登山道でした。
コンディションは最高!
参加者全員が独標に登頂成功!・・・わたしを除く・・・
夏休み最後の日曜日とあって登山者が多く、独標に登る順番待ちに時間がかかるため、手前で荷物をデポして空身で向かっていただきました。わたしはその荷物番で、一緒の登頂ならず。
まれに見る好展望で(わたし個人は残念でしたが)、皆さん大満足の一日となられたようです。
本当にお疲れさまでした!
またご一緒できるのを楽しみにしております。

登山者が行列を成す独標への登山道でした。
2009年08月22日
明日は西穂高独標へ
いよいよ明日は西穂高独標登山ツアーです。
天気もなかなか良いとのこと。ご参加の皆様には展望をお楽しみいただけそうです。
先月に行った西穂丸山から見上げた場所へ。

陽射しが強いと思われますので、帽子や日焼け止めを必ずお持ちください(できればサングラスも・・・紫外線が目から吸収されると疲労が増すと言われています)。
水分も多めに持って行くとよいでしょう。500mlのペットボトルなら2本は最低必要です。
西穂山荘で自動販売機から購入もできます。
汗を吸収し発散する吸湿速乾素材のウエアを着用すると、稜線で休んでいる時に身体を冷やさないで済みます。綿素材のTシャツなどは少なくともアンダーウエアには着用しないでください。
ご参加の皆様、明日はいっしょに楽しみましょう!
天気もなかなか良いとのこと。ご参加の皆様には展望をお楽しみいただけそうです。
先月に行った西穂丸山から見上げた場所へ。

陽射しが強いと思われますので、帽子や日焼け止めを必ずお持ちください(できればサングラスも・・・紫外線が目から吸収されると疲労が増すと言われています)。
水分も多めに持って行くとよいでしょう。500mlのペットボトルなら2本は最低必要です。
西穂山荘で自動販売機から購入もできます。
汗を吸収し発散する吸湿速乾素材のウエアを着用すると、稜線で休んでいる時に身体を冷やさないで済みます。綿素材のTシャツなどは少なくともアンダーウエアには着用しないでください。
ご参加の皆様、明日はいっしょに楽しみましょう!
2009年08月09日
乗鞍硫黄岳〜平湯登山道を途中まで
前回の投稿の次の日、いきなり東海地方の梅雨が明けました。
しかしスッキリと夏を迎えたわけではありません。
特に2000mを越える山岳地帯は厚い雲におおわれて、ときどき上空の雲や霧が晴れても、周辺の山々は展望がかないません。
先日は白山から大白川へ下山中の男性が、豪雨に動けなくなり救助されました。
明日も天候はかんばしくないようです。
入山される方は十分お気をつけください。
昨日はひさびさに山へと向かいました。
この秋(9月23日)にツアーを予定している「乗鞍硫黄岳」。
平湯登山道が新しくなったとき(2005年開通)に歩いて以来なので4年ぶりでした。
夏のシーズンを迎え、畳平から剣ケ峰をめざす人々が畳平に集合しています。
しかし硫黄岳はひっそりとしていました。
畳平〜(乗鞍スカイラインを徒歩で下る)〜桔梗ヶ原〜入山口〜硫黄岳〜十石山分岐(祠)〜来た道を戻る〜畳平
前回は7月上旬に平湯まで下り、スキー場の裏からゲレンデが辛かった思い出があります。十石山との分岐からは暗い樹林帯の中で、展望もなく面白くはなかったなあと・・・。
今回は(晴れていれば)穂高連峰を見ながら歩ける尾根の往復をもくろみました。しかし残念ながら雲に展望を阻まれてしまいました。
乗鞍スカイラインを桔梗ヶ原まで下りながら驚いたのは、道路脇が想像以上に素晴らしい高山植物のお花畑になっていることでした。
チシマギキョウやチングルマの群生。イワツメクサやコマクサも。
ミネウスユキソウもありましたが、目にしたのはこの一群だけでした。

桔梗ヶ原にある平湯登山道の入山口。

ところがどこから進入するのかしばし困惑。
前回ははっきり分った入山地点が、伸びたハイマツにおおわれてしまっていました。
探し当てた道は標識の右、ハイマツのとぎれるあたりに崖を下るようについています。
霧がなければ、この地点からすでに硫黄岳が見えているのですが、昨日の入山時はまったく展望できませんでした。帰りに霧が流れる一瞬があり、登山道も目でたどることができましたが、今回のように視界が利かない時は迷うことがあるので気をつける必要があります。

帰途に乗鞍スカイライン下の斜面から撮影した硫黄岳。
登山道はすぐ崖のような斜面をジグザグに下り、コマクサが咲く底部に着いたら今度は右側の斜面沿いにハイマツ帯をトラバースします。左に小山(丸山)があり、地面が見えているところが道のように感じるかもしれませんので注意。
トラバースが終わると、眼前に硫黄岳が見えてきます。
硫黄岳直前の姫ヶ原には旧道との分岐がありますが、行き止まりのロープが張られているので迷い込むことはないでしょう。
硫黄岳をゆったりと登る登山道は2つの小ピークを越えたあと、頂上をはずれてトラバースしています。
残念ながら頂上への道はありません。
登山道上部の斜面が筋状に崩れて道のように見えますが、それも途中まで。むりやり登るとハイマツなどの植物を踏み荒らすので諦めます。
硫黄岳は今回の目的地でありながら、目的地らしさに欠けています。実は前回来た時は硫黄岳の存在をまったく認識していませんでした。
何となく不満が残るので、硫黄岳の気持ちのいい尾根をたどり、十石山の分岐地点まで足を伸ばしました。

十石山(金山岩)です。避難小屋のある頂上は(手前の金山岩より標高が低いので)見えないと思います。分岐から先は崩れたガレ場があり通行は危険だということなので十石山へ行くのは諦めたほうが良いでしょう。
お昼を過ぎた頃からようやく上空が晴れてきました。

硫黄岳へ登り返す途中から穂高連峰の方向を眺めます。
剣ケ峰からの眺めとはまた違った展望が見えるでしょう。
晴れ間は長くは続きませんでした。復路に硫黄岳を下る頃にはまた雲の中。

写真は硫黄岳の2つの小ピーク。
手前のピークにはコマクサが咲いています。
しかしこの時期以外は、ただの休憩スペースに見えてしまいます。

岩に座ろうとして踏み荒らしてしまう恐れがあり、気をつけなければなりませんね。
硫黄岳へのツアーのご案内は、ただいま準備中です。
畳平や剣ケ峰とは一味違う乗鞍を体験していただけるはずです。
興味のある方はぜひご参加ください。
しかしスッキリと夏を迎えたわけではありません。
特に2000mを越える山岳地帯は厚い雲におおわれて、ときどき上空の雲や霧が晴れても、周辺の山々は展望がかないません。
先日は白山から大白川へ下山中の男性が、豪雨に動けなくなり救助されました。
明日も天候はかんばしくないようです。
入山される方は十分お気をつけください。
昨日はひさびさに山へと向かいました。
この秋(9月23日)にツアーを予定している「乗鞍硫黄岳」。
平湯登山道が新しくなったとき(2005年開通)に歩いて以来なので4年ぶりでした。
夏のシーズンを迎え、畳平から剣ケ峰をめざす人々が畳平に集合しています。
しかし硫黄岳はひっそりとしていました。
畳平〜(乗鞍スカイラインを徒歩で下る)〜桔梗ヶ原〜入山口〜硫黄岳〜十石山分岐(祠)〜来た道を戻る〜畳平
前回は7月上旬に平湯まで下り、スキー場の裏からゲレンデが辛かった思い出があります。十石山との分岐からは暗い樹林帯の中で、展望もなく面白くはなかったなあと・・・。
今回は(晴れていれば)穂高連峰を見ながら歩ける尾根の往復をもくろみました。しかし残念ながら雲に展望を阻まれてしまいました。
乗鞍スカイラインを桔梗ヶ原まで下りながら驚いたのは、道路脇が想像以上に素晴らしい高山植物のお花畑になっていることでした。
チシマギキョウやチングルマの群生。イワツメクサやコマクサも。
ミネウスユキソウもありましたが、目にしたのはこの一群だけでした。

桔梗ヶ原にある平湯登山道の入山口。

ところがどこから進入するのかしばし困惑。
前回ははっきり分った入山地点が、伸びたハイマツにおおわれてしまっていました。
探し当てた道は標識の右、ハイマツのとぎれるあたりに崖を下るようについています。
霧がなければ、この地点からすでに硫黄岳が見えているのですが、昨日の入山時はまったく展望できませんでした。帰りに霧が流れる一瞬があり、登山道も目でたどることができましたが、今回のように視界が利かない時は迷うことがあるので気をつける必要があります。

帰途に乗鞍スカイライン下の斜面から撮影した硫黄岳。
登山道はすぐ崖のような斜面をジグザグに下り、コマクサが咲く底部に着いたら今度は右側の斜面沿いにハイマツ帯をトラバースします。左に小山(丸山)があり、地面が見えているところが道のように感じるかもしれませんので注意。
トラバースが終わると、眼前に硫黄岳が見えてきます。
硫黄岳直前の姫ヶ原には旧道との分岐がありますが、行き止まりのロープが張られているので迷い込むことはないでしょう。
硫黄岳をゆったりと登る登山道は2つの小ピークを越えたあと、頂上をはずれてトラバースしています。
残念ながら頂上への道はありません。
登山道上部の斜面が筋状に崩れて道のように見えますが、それも途中まで。むりやり登るとハイマツなどの植物を踏み荒らすので諦めます。
硫黄岳は今回の目的地でありながら、目的地らしさに欠けています。実は前回来た時は硫黄岳の存在をまったく認識していませんでした。
何となく不満が残るので、硫黄岳の気持ちのいい尾根をたどり、十石山の分岐地点まで足を伸ばしました。

十石山(金山岩)です。避難小屋のある頂上は(手前の金山岩より標高が低いので)見えないと思います。分岐から先は崩れたガレ場があり通行は危険だということなので十石山へ行くのは諦めたほうが良いでしょう。
お昼を過ぎた頃からようやく上空が晴れてきました。

硫黄岳へ登り返す途中から穂高連峰の方向を眺めます。
剣ケ峰からの眺めとはまた違った展望が見えるでしょう。
晴れ間は長くは続きませんでした。復路に硫黄岳を下る頃にはまた雲の中。

写真は硫黄岳の2つの小ピーク。
手前のピークにはコマクサが咲いています。
しかしこの時期以外は、ただの休憩スペースに見えてしまいます。

岩に座ろうとして踏み荒らしてしまう恐れがあり、気をつけなければなりませんね。
硫黄岳へのツアーのご案内は、ただいま準備中です。
畳平や剣ケ峰とは一味違う乗鞍を体験していただけるはずです。
興味のある方はぜひご参加ください。
2009年07月14日
飛騨高山から行く郡上踊りツアーお申し込み受付中
以前ご案内したインタープリターガイドツアーから、実施まで1ヶ月を切った「飛騨高山から行く郡上踊りツアー」を再度ご紹介します。
先日、今年の郡上踊りが始りました。お盆に行われる徹夜踊りを前に、郡上八幡町内はしだいに盛り上がっていきます。
当然、郡上踊り目当ての観光客の方も多く、町内は混雑します。ご宿泊が難しくなることもあり、飛騨高山からお出かけになる方も多くいらっしゃいます。
しかし自動車専用道路が整備され便利になったとは言え、いざ着いてみると駐車場に入れるのに時間がかかることもあります。
そんな時に、高山グリーンツアーをご利用ください。
しかもインタープリターが引率し、郡上八幡の歴史や文化を解説しますので、より郡上踊りの世界が楽しめるはずです。

実施は8月7日(金)。ご宿泊当日の夜です。
下駄と団扇をご用意しますので、ぜひ浴衣持参でご参加ください。
先日、今年の郡上踊りが始りました。お盆に行われる徹夜踊りを前に、郡上八幡町内はしだいに盛り上がっていきます。
当然、郡上踊り目当ての観光客の方も多く、町内は混雑します。ご宿泊が難しくなることもあり、飛騨高山からお出かけになる方も多くいらっしゃいます。
しかし自動車専用道路が整備され便利になったとは言え、いざ着いてみると駐車場に入れるのに時間がかかることもあります。
そんな時に、高山グリーンツアーをご利用ください。
しかもインタープリターが引率し、郡上八幡の歴史や文化を解説しますので、より郡上踊りの世界が楽しめるはずです。

実施は8月7日(金)。ご宿泊当日の夜です。
下駄と団扇をご用意しますので、ぜひ浴衣持参でご参加ください。
2009年07月12日
乗鞍岳剣ケ峰ツアー中止・・・そこで木曽駒ケ岳へ
今日の高山市街は曇時々晴れ。
西を見ると乗鞍は大きな雲のかたまりに包まれていました。
畳平のライブカメラで見ると、雨が降っています。
本日予定していた乗鞍岳剣ケ峰登山ツアーは、天候を心配されたご高齢者のグループが参加を止められたため催行人数割れとなり中止となっていました。
残念ですが、登山ではよくあることです(と、ガイドの大野さん)。
来年は梅雨時を避けて、シーズン時は休日を中心に長期のガイドで忙しい大野さんが空いている平日にするかと思案中。登山客も少ないし・・・。
そんな訳で、わたくしは昨日長野へと出かけてきました。
飛騨地方に関係ない山行ですが、これから始る夏山シーズンの参考になれば・・・。
今回は(・・・今回も)日帰り山行です。
目的地は甲斐駒ケ岳でしたが、あとわずかで計画が台無しになりました。
原因は交通情報を確認しなかったこと。
国道361号線が高根町で夜間通行止めになっていたのです(7月17日まで)。迂回路はありません。
そのため泣く泣く戻り、下呂から中津川へ、そして中央道で伊那まで行くことにしました。
5時半過ぎには仙流荘に着き、6時5分発の北沢峠行き登山者用バスに乗れる予定でした。
しかし到着したのは6時10分。次のバスが出るのは8時過ぎです。
2時間のロスは大きいです。甲斐駒登山は諦めて次の機会に。
この時間で日帰りで登れる山は・・・。思い浮かんだのは木曽駒ケ岳。
夏山シーズンに行きたくて、しかし敬遠してしまう木曽駒ケ岳。
しかし今ならまだ観光客も少ないだろうということで決めました。
高遠町から伊那市街を抜けて権兵衛トンネル方面へ。
途中で左に折れて中央道沿いに南へ(コスモ石油GSの向いにあるコンビニの向かって右側の道に入ります・・・左側にも道がありカレー屋さんの前を通るのは間違いです)。
駒ケ根ICまで行き、駒ケ根高原のロープウェイ客用駐車場に車を停めます。駐車場は5割の入り。前の方が空いていたのですぐに駐車できました。
往復のセット券を購入し、バスでロープウェイの駅まで。
圧倒的に登山客より観光客が多く、登山のスタイルをしているのは2割弱でしょうか。
バスの乗客がほぼ全員、待っていたロープウェイに乗ることができました。
しかしあと10日もすると、大変な混雑になるのでしょう。
千畳敷カールには雪渓が残り、高山植物の宝庫の面影はまだありませんでした。

スニーカーにジーンズの方も雪渓を渡っています。
千畳敷ホテルのスタッフでしょうか、雪渓をスコップで削り、観光客が滑らないように作業をされていました。
登山道は整備されています。登山者には物足りないくらいです。
軽装の人ができるだけ安全に登れるようにしてあるのでしょう。
同じロープウェイ駅である新穂高ロープウェイの西穂高口には、登山装備のない人に入山を控えるよう注意標識が立てられていますが、千畳敷では無理のようです。
登山経験のない人も日本アルプスの名峰に登れてしまうので、これを機会に登山が好きになってくれるとうれしいのですが。
宝剣岳と木曽駒ケ岳の両方に登りました(これを縦走と言って良いのでしょうか?)。
宝剣岳は高さはないのですが、なかなか登り甲斐のあるちょっと危険な岩山です。
スニーカーやジーンズでは絶対トライしないこと。滑落します(結果必ず死にます)。

宝剣岳の頂上から眺める千畳敷カール。ふもとの町、駒ケ根市が見えています。
遠くの山並みは南アルプス。中央に顔をのぞかせているのは富士山です。
木曽駒ケ岳は間に中岳をはさんで宝剣岳のほぼ向いにあります。
中岳から見た木曽駒ケ岳。

木曽駒ケ岳に向いロープウェイを使わない登山道がいくつかあります。いずれも手軽な道ではありません。往復するなら小屋かテント泊が必要です。
今度は木曽駒ケ岳から見た中岳とその奥にそびえる宝剣岳。

中岳には右に斜面を迂回するトラバース道が見えています。途中に岩を越えるため危険です。積雪期には滑落死亡事故がありました。
シーズンではないこともあり、木曽駒や宝剣岳への登山者は多くありませんでした。
しかし軽装の観光客が(下のカールから見えている)乗越浄土の鞍部まではたくさん登ってきていました。
もし行かれる方があれば、少なくともトレッキングシューズと動きやすいズボンで日本アルプス登山に挑戦してください。それだけで楽しさが数倍違いますし、安全です。
乗鞍岳剣ケ峰ツアーは催行できず残念でしたが、次回開催の「西穂高岳独標」は必ず実施したいと思います。参加のお申し込みも増えていますし・・・。
詳しくはツアーご案内のページをご覧ください。
西を見ると乗鞍は大きな雲のかたまりに包まれていました。
畳平のライブカメラで見ると、雨が降っています。
本日予定していた乗鞍岳剣ケ峰登山ツアーは、天候を心配されたご高齢者のグループが参加を止められたため催行人数割れとなり中止となっていました。
残念ですが、登山ではよくあることです(と、ガイドの大野さん)。
来年は梅雨時を避けて、シーズン時は休日を中心に長期のガイドで忙しい大野さんが空いている平日にするかと思案中。登山客も少ないし・・・。
そんな訳で、わたくしは昨日長野へと出かけてきました。
飛騨地方に関係ない山行ですが、これから始る夏山シーズンの参考になれば・・・。
今回は(・・・今回も)日帰り山行です。
目的地は甲斐駒ケ岳でしたが、あとわずかで計画が台無しになりました。
原因は交通情報を確認しなかったこと。
国道361号線が高根町で夜間通行止めになっていたのです(7月17日まで)。迂回路はありません。
そのため泣く泣く戻り、下呂から中津川へ、そして中央道で伊那まで行くことにしました。
5時半過ぎには仙流荘に着き、6時5分発の北沢峠行き登山者用バスに乗れる予定でした。
しかし到着したのは6時10分。次のバスが出るのは8時過ぎです。
2時間のロスは大きいです。甲斐駒登山は諦めて次の機会に。
この時間で日帰りで登れる山は・・・。思い浮かんだのは木曽駒ケ岳。
夏山シーズンに行きたくて、しかし敬遠してしまう木曽駒ケ岳。
しかし今ならまだ観光客も少ないだろうということで決めました。
高遠町から伊那市街を抜けて権兵衛トンネル方面へ。
途中で左に折れて中央道沿いに南へ(コスモ石油GSの向いにあるコンビニの向かって右側の道に入ります・・・左側にも道がありカレー屋さんの前を通るのは間違いです)。
駒ケ根ICまで行き、駒ケ根高原のロープウェイ客用駐車場に車を停めます。駐車場は5割の入り。前の方が空いていたのですぐに駐車できました。
往復のセット券を購入し、バスでロープウェイの駅まで。
圧倒的に登山客より観光客が多く、登山のスタイルをしているのは2割弱でしょうか。
バスの乗客がほぼ全員、待っていたロープウェイに乗ることができました。
しかしあと10日もすると、大変な混雑になるのでしょう。
千畳敷カールには雪渓が残り、高山植物の宝庫の面影はまだありませんでした。

スニーカーにジーンズの方も雪渓を渡っています。
千畳敷ホテルのスタッフでしょうか、雪渓をスコップで削り、観光客が滑らないように作業をされていました。
登山道は整備されています。登山者には物足りないくらいです。
軽装の人ができるだけ安全に登れるようにしてあるのでしょう。
同じロープウェイ駅である新穂高ロープウェイの西穂高口には、登山装備のない人に入山を控えるよう注意標識が立てられていますが、千畳敷では無理のようです。
登山経験のない人も日本アルプスの名峰に登れてしまうので、これを機会に登山が好きになってくれるとうれしいのですが。
宝剣岳と木曽駒ケ岳の両方に登りました(これを縦走と言って良いのでしょうか?)。
宝剣岳は高さはないのですが、なかなか登り甲斐のあるちょっと危険な岩山です。
スニーカーやジーンズでは絶対トライしないこと。滑落します(結果必ず死にます)。

宝剣岳の頂上から眺める千畳敷カール。ふもとの町、駒ケ根市が見えています。
遠くの山並みは南アルプス。中央に顔をのぞかせているのは富士山です。
木曽駒ケ岳は間に中岳をはさんで宝剣岳のほぼ向いにあります。
中岳から見た木曽駒ケ岳。

木曽駒ケ岳に向いロープウェイを使わない登山道がいくつかあります。いずれも手軽な道ではありません。往復するなら小屋かテント泊が必要です。
今度は木曽駒ケ岳から見た中岳とその奥にそびえる宝剣岳。

中岳には右に斜面を迂回するトラバース道が見えています。途中に岩を越えるため危険です。積雪期には滑落死亡事故がありました。
シーズンではないこともあり、木曽駒や宝剣岳への登山者は多くありませんでした。
しかし軽装の観光客が(下のカールから見えている)乗越浄土の鞍部まではたくさん登ってきていました。
もし行かれる方があれば、少なくともトレッキングシューズと動きやすいズボンで日本アルプス登山に挑戦してください。それだけで楽しさが数倍違いますし、安全です。
乗鞍岳剣ケ峰ツアーは催行できず残念でしたが、次回開催の「西穂高岳独標」は必ず実施したいと思います。参加のお申し込みも増えていますし・・・。
詳しくはツアーご案内のページをご覧ください。
2009年07月06日
西穂高丸山登山ツアー
昨日、この夏の登山ツアー第1弾「西穂高丸山」を行いました。
梅雨にもかかわらず(前日は大雨でした)、当日は幸運にも雨に降られることなく終えることができました。
心配していた登山道のぬかるみもほとんどなく、気温も汗ばむほど高くならず、この時期としては快適な登山となりました。
新穂高ロープウェイしらかば平駅に到着したのは、始発(8:45)の30分ほど前。第1ロープウェイからの乗客はまだ到着していませんでした。ところが始発便が1本繰り上がったらしく、突然どやどやと乗客の一団が現れました。まだ来ないと高をくくっていた私たちはあわてて列の中団に。第2ロープウェイも1本早く30分に発車となりました。
西穂高口を8:57出発。
天気は曇りながら、時々陽が射すことも。
2171ピーク付近から西穂山荘から丸山、独標、そして西穂高岳への連なりを展望。

稜線には霧が若干かかっていますが、時間が経てば上がってきそうです。
林の中を歩くので風はあまり吹いてきませんが気温は思ったほど上がらず、そのため虫も少なく、この時期の登山にはありがたい天候でした。
今年は雪が少なかったため、登山道沿いの花のピークは過ぎているようです。
そんな中で、マイヅルソウやゴゼンタチバナが開花時期を迎えていました。
西穂山荘の手前では今年もキヌガサソウが咲いていました。

白く大きな花びらのような部分はガクで、本当の花は中央に雄しべのように小さく付いています。と、ガイドの大野さんから教えられました。
西穂山荘で一休みし、西穂高の稜線上へ登りました。
岩を少し登ると、もうそこは森林限界です。
ハイマツの間にある大きな丸みのある岩群をよじ登るようにして上がっていきます。
しばらくすると西穂高岳が見えてきました。

右から二つ目の台形のピークが8月にツアーを行う独標です。
稜線に登りきれば、尾根は平坦に。
丸山とその先の急斜面が見えてきます。

写真では霧に隠れていますが、丸山でゆっくり過ごす間、独標や明神岳・前穂高岳が姿を見せてくれていました。
残念だったのは、西にそびえる飛騨の名峰・笠ケ岳が、その笠の部分だけを最後まで見せてくれなかったことです。・・・夏の独標登山ではきっと見えると期待しつつ、のんびりとしたランチタイムを終えて下山となりました。
梅雨にもかかわらず(前日は大雨でした)、当日は幸運にも雨に降られることなく終えることができました。
心配していた登山道のぬかるみもほとんどなく、気温も汗ばむほど高くならず、この時期としては快適な登山となりました。
新穂高ロープウェイしらかば平駅に到着したのは、始発(8:45)の30分ほど前。第1ロープウェイからの乗客はまだ到着していませんでした。ところが始発便が1本繰り上がったらしく、突然どやどやと乗客の一団が現れました。まだ来ないと高をくくっていた私たちはあわてて列の中団に。第2ロープウェイも1本早く30分に発車となりました。
西穂高口を8:57出発。
天気は曇りながら、時々陽が射すことも。
2171ピーク付近から西穂山荘から丸山、独標、そして西穂高岳への連なりを展望。

稜線には霧が若干かかっていますが、時間が経てば上がってきそうです。
林の中を歩くので風はあまり吹いてきませんが気温は思ったほど上がらず、そのため虫も少なく、この時期の登山にはありがたい天候でした。
今年は雪が少なかったため、登山道沿いの花のピークは過ぎているようです。
そんな中で、マイヅルソウやゴゼンタチバナが開花時期を迎えていました。
西穂山荘の手前では今年もキヌガサソウが咲いていました。

白く大きな花びらのような部分はガクで、本当の花は中央に雄しべのように小さく付いています。と、ガイドの大野さんから教えられました。
西穂山荘で一休みし、西穂高の稜線上へ登りました。
岩を少し登ると、もうそこは森林限界です。
ハイマツの間にある大きな丸みのある岩群をよじ登るようにして上がっていきます。
しばらくすると西穂高岳が見えてきました。

右から二つ目の台形のピークが8月にツアーを行う独標です。
稜線に登りきれば、尾根は平坦に。
丸山とその先の急斜面が見えてきます。

写真では霧に隠れていますが、丸山でゆっくり過ごす間、独標や明神岳・前穂高岳が姿を見せてくれていました。
残念だったのは、西にそびえる飛騨の名峰・笠ケ岳が、その笠の部分だけを最後まで見せてくれなかったことです。・・・夏の独標登山ではきっと見えると期待しつつ、のんびりとしたランチタイムを終えて下山となりました。
2009年06月26日
乗鞍岳剣ケ峰ツアー
先日からご紹介している夏の登山・山歩きツアー。
「西穂高丸山」に続き、第2弾は「乗鞍岳剣ケ峰」登山ツアーのご案内です。

乗鞍岳剣ケ峰<標高 3,025.6m>
入山日 7月12日(日)
高山から行く場合、濃飛バスセンターから乗鞍スカイラインで畳平までバスかタクシーの利用となります。マイカーでは乗鞍スカイラインに乗り入れられないので、ほおのき平スキー場のバス停で畳平行きのシャトルバスに乗り換えます。
ツアーではホテルからチャーターしたバスで畳平に直行しますので、乗り換えの手間がいりません。
畳平へは大勢の観光客と一部の登山客がいっしょになります。ザックやストックの荷物にも気を使います。登山者だけのツアーなら、そんな心配もありません。
畳平で登山準備を整え、剣ケ峰へいざ出発です。
昨年のツアーでは、夏休みに入った中学の集団登山といっしょになってしまい、予定通りに進むことができませんでした。
今回は夏休み前(夏山シーズン直前)の山行なので、この心配はないと思います。

コースの概略です。肩の小屋までは舗装された林道を歩くだけ。登山道は肩の小屋から始ります。
宇宙船観測所のある摩利支天岳との分岐を回り込むと、剣ケ峰の全体が見えてきます。

右から朝日岳、登山道が乗越す鞍部と小ピークの蚕玉岳、そして鋭く尖った剣ケ峰です。
登山道は火山岩がごろごろして、砂礫で滑りやすいので、ねん挫しないように注意して登ります。そして急登です。ガイドのペースでゆっくり登りましょう。
写真のように登山道のある斜面には、まだ雪が残っているかもしれません。

でも、ここまで来れば稜線の鞍部まであと少しです。
鞍部に着いたら休憩します。稜線の右側は火口跡。今は雪解け水をたたえる権現池です。
振り返れば雄大な景色が広がっています。
天候に恵まれれば穂高連峰や槍ケ岳、左手には笠ケ岳が見えています。
もう剣ケ峰はすぐそこです。
稜線を進み、頂上小屋の前を通り、岩場を登れば頂上です。
祠は信州側の朝日権現社。背中合わせの小屋は飛騨側の乗鞍本宮奥宮です。

下山は鳥居の奥にある下山専用の道を使います。浮き石に注意しましょう。あわてず岩の状態を確かめるように足を下ろせば問題ありません。
頂上付近には植物がほとんど見られません。
登山道から離れた斜面にコマクサの群生が見られます。
頂上小屋のそばの岩には、へばりつくようにしてわずかな高山植物が生きています。

小さな白い花はツガザクラ。ピンク色の花はコイワカガミです。・・・が、この写真では良く分りませんね。
下山したら畳平のお花畑に立ち寄りましょう。まだ雪渓が残っていると思います。
木道の奥に行けば、ハクサンイチゲの群落やアオノツガザクラ、コイワカガミ、咲き始めたばかりのクロユリが見られるかもしれません。
コマクサは鶴ヶ池周辺や畳平の裏にある魔王岳で目にすることができるでしょう。

畳平まで一気に乗り物で上がることにより、軽い高山病にかかることもあります。
対策は体調を調えておくことです。
またホテルに戻ってから温泉で汗を流していただける無料入浴券を用意しています。
ツアーの詳細は「乗鞍剣ケ峰」登山ツアーのページをご覧ください。
「西穂高丸山」に続き、第2弾は「乗鞍岳剣ケ峰」登山ツアーのご案内です。

乗鞍岳剣ケ峰<標高 3,025.6m>
入山日 7月12日(日)
高山から行く場合、濃飛バスセンターから乗鞍スカイラインで畳平までバスかタクシーの利用となります。マイカーでは乗鞍スカイラインに乗り入れられないので、ほおのき平スキー場のバス停で畳平行きのシャトルバスに乗り換えます。
ツアーではホテルからチャーターしたバスで畳平に直行しますので、乗り換えの手間がいりません。
畳平へは大勢の観光客と一部の登山客がいっしょになります。ザックやストックの荷物にも気を使います。登山者だけのツアーなら、そんな心配もありません。
畳平で登山準備を整え、剣ケ峰へいざ出発です。
昨年のツアーでは、夏休みに入った中学の集団登山といっしょになってしまい、予定通りに進むことができませんでした。
今回は夏休み前(夏山シーズン直前)の山行なので、この心配はないと思います。

コースの概略です。肩の小屋までは舗装された林道を歩くだけ。登山道は肩の小屋から始ります。
宇宙船観測所のある摩利支天岳との分岐を回り込むと、剣ケ峰の全体が見えてきます。

右から朝日岳、登山道が乗越す鞍部と小ピークの蚕玉岳、そして鋭く尖った剣ケ峰です。
登山道は火山岩がごろごろして、砂礫で滑りやすいので、ねん挫しないように注意して登ります。そして急登です。ガイドのペースでゆっくり登りましょう。
写真のように登山道のある斜面には、まだ雪が残っているかもしれません。

でも、ここまで来れば稜線の鞍部まであと少しです。
鞍部に着いたら休憩します。稜線の右側は火口跡。今は雪解け水をたたえる権現池です。
振り返れば雄大な景色が広がっています。
天候に恵まれれば穂高連峰や槍ケ岳、左手には笠ケ岳が見えています。
もう剣ケ峰はすぐそこです。
稜線を進み、頂上小屋の前を通り、岩場を登れば頂上です。
祠は信州側の朝日権現社。背中合わせの小屋は飛騨側の乗鞍本宮奥宮です。

下山は鳥居の奥にある下山専用の道を使います。浮き石に注意しましょう。あわてず岩の状態を確かめるように足を下ろせば問題ありません。
頂上付近には植物がほとんど見られません。
登山道から離れた斜面にコマクサの群生が見られます。
頂上小屋のそばの岩には、へばりつくようにしてわずかな高山植物が生きています。

小さな白い花はツガザクラ。ピンク色の花はコイワカガミです。・・・が、この写真では良く分りませんね。
下山したら畳平のお花畑に立ち寄りましょう。まだ雪渓が残っていると思います。
木道の奥に行けば、ハクサンイチゲの群落やアオノツガザクラ、コイワカガミ、咲き始めたばかりのクロユリが見られるかもしれません。
コマクサは鶴ヶ池周辺や畳平の裏にある魔王岳で目にすることができるでしょう。

畳平まで一気に乗り物で上がることにより、軽い高山病にかかることもあります。
対策は体調を調えておくことです。
またホテルに戻ってから温泉で汗を流していただける無料入浴券を用意しています。
ツアーの詳細は「乗鞍剣ケ峰」登山ツアーのページをご覧ください。
2009年06月17日
夏のツアー第1弾〜西穂高丸山
飛騨地方も梅雨に入ってしばらく経ちますが、今のところ災害が出るほどの降雨はありません。昨年は日本各地でゲリラ豪雨があり、温暖化の影響かと噂されました。
まだ梅雨は始ったばかり。昨日は東京でゲリラ豪雨があったとのことです。レジャーにお出かけの際は、天気予報に注意して準備万端に。
そんな時期ですが、森の緑が一年で一番美しいときでもあります。
高山帯の植物が花を咲かせ、登山者の目を楽しませてくれるのもこの時期。
台風でもなければ、多少の雨は登山者の楽しみを奪うこともありません。むしろ静かな山歩きが楽しめます。
高山グリーンツアーでは、そんな7月上旬に2つの登山ツアーを行います。
◎西穂高丸山 7月5日(日)入山
◎乗鞍岳剣ケ峰 7月12日(日)入山
今回は西穂高丸山への登山ツアーをご案内します。

このツアーは昨年も同じコースで行いました。
高山グリーンホテルに集合し、新穂高ロープウェイのしらかば平駅までマイクロバスで向かいました。ここから2階建のゴンドラで終点の西穂高口まで。
昨年は霧が深く、ゴンドラからの展望はいまひとつでした。2000mを超えて西穂高口駅まで上れば霧状の雲の上に出ることが多いので、今年こそはと期待しています。
登山道にはさまざまな高山植物が咲いています。
比較的遅く咲き始めるのがマイヅルソウ。7月上旬が見ごろです。

ゴゼンタチバナもこの時期に群生して見られます。

昨年はピンク色のイワカガミが群生し、白い小さな花を咲かせるコミヤマカタバミ(葉が三つ葉のクローバーのようです)、ひっそりと咲くツマトリソウ、ハスの葉のようなサンカヨウなど、見ることができました。
西穂山荘の木道沿いでは大きな花を咲かせるキヌガサソウに出会えます。

見つけたらガイドの大野さんが教えてくれますので、初めてでも高山植物にちょっと詳しくなれます。
西穂山荘は北アルプスでは数少ない年中無休の山小屋。テント場の回りにはシナノキンバイが群生しています。
ここでトイレ休憩の後、いよいよ西穂高の稜線に向かいます。山荘の北側の岩の斜面を登ると森林限界です。ハイマツの間を抜けていくと、展望が開けてきます。
眼下の山荘の後方には、噴煙たなびく焼岳。その後ろには優雅に横たわる乗鞍連峰が見えてきます。もちろん天候次第ですが。
西には雄大な笠ケ岳の稜線。その左に錫杖の岩峰。右に続くなだらかな稜線は双六岳で槍ケ岳からの尾根と合流しています。
ハイマツの中を丸山へ。
途中、眼下に梓川が流れる上高地を見下ろせます。その後ろにそびえる霞沢岳。
ケルンのある丸山から、西穂高へと向かう急斜面をあおぎ見ると、その上には独標が顔をのぞかせています。(上のタイトルの写真がその風景)
西穂高丸山はロープウェイを使うことで日帰り登山ができ、焼岳と穂高連峰の間の北アルプス稜線上にある一級の展望台といえます。(写真は独標へ向かう途中から見た丸山と後方に乗鞍岳)

丸山まで登ることができて自信がついたら、次は独標まで行ってみてはいかがでしょう。
高山グリーンツアーでは、8月23日(日)に西穂高岳独標に登ります。
ぜひ西穂高丸山と併せてご参加ください。
いずれのツアーもインターネット予約ができます。
(料金には新穂高ロープウェイの往復乗車料も含んでいます)
まだ梅雨は始ったばかり。昨日は東京でゲリラ豪雨があったとのことです。レジャーにお出かけの際は、天気予報に注意して準備万端に。
そんな時期ですが、森の緑が一年で一番美しいときでもあります。
高山帯の植物が花を咲かせ、登山者の目を楽しませてくれるのもこの時期。
台風でもなければ、多少の雨は登山者の楽しみを奪うこともありません。むしろ静かな山歩きが楽しめます。
高山グリーンツアーでは、そんな7月上旬に2つの登山ツアーを行います。
◎西穂高丸山 7月5日(日)入山
◎乗鞍岳剣ケ峰 7月12日(日)入山
今回は西穂高丸山への登山ツアーをご案内します。

このツアーは昨年も同じコースで行いました。
高山グリーンホテルに集合し、新穂高ロープウェイのしらかば平駅までマイクロバスで向かいました。ここから2階建のゴンドラで終点の西穂高口まで。
昨年は霧が深く、ゴンドラからの展望はいまひとつでした。2000mを超えて西穂高口駅まで上れば霧状の雲の上に出ることが多いので、今年こそはと期待しています。
登山道にはさまざまな高山植物が咲いています。
比較的遅く咲き始めるのがマイヅルソウ。7月上旬が見ごろです。

ゴゼンタチバナもこの時期に群生して見られます。

昨年はピンク色のイワカガミが群生し、白い小さな花を咲かせるコミヤマカタバミ(葉が三つ葉のクローバーのようです)、ひっそりと咲くツマトリソウ、ハスの葉のようなサンカヨウなど、見ることができました。
西穂山荘の木道沿いでは大きな花を咲かせるキヌガサソウに出会えます。

見つけたらガイドの大野さんが教えてくれますので、初めてでも高山植物にちょっと詳しくなれます。
西穂山荘は北アルプスでは数少ない年中無休の山小屋。テント場の回りにはシナノキンバイが群生しています。
ここでトイレ休憩の後、いよいよ西穂高の稜線に向かいます。山荘の北側の岩の斜面を登ると森林限界です。ハイマツの間を抜けていくと、展望が開けてきます。
眼下の山荘の後方には、噴煙たなびく焼岳。その後ろには優雅に横たわる乗鞍連峰が見えてきます。もちろん天候次第ですが。
西には雄大な笠ケ岳の稜線。その左に錫杖の岩峰。右に続くなだらかな稜線は双六岳で槍ケ岳からの尾根と合流しています。
ハイマツの中を丸山へ。
途中、眼下に梓川が流れる上高地を見下ろせます。その後ろにそびえる霞沢岳。
ケルンのある丸山から、西穂高へと向かう急斜面をあおぎ見ると、その上には独標が顔をのぞかせています。(上のタイトルの写真がその風景)
西穂高丸山はロープウェイを使うことで日帰り登山ができ、焼岳と穂高連峰の間の北アルプス稜線上にある一級の展望台といえます。(写真は独標へ向かう途中から見た丸山と後方に乗鞍岳)

丸山まで登ることができて自信がついたら、次は独標まで行ってみてはいかがでしょう。
高山グリーンツアーでは、8月23日(日)に西穂高岳独標に登ります。
ぜひ西穂高丸山と併せてご参加ください。
いずれのツアーもインターネット予約ができます。
(料金には新穂高ロープウェイの往復乗車料も含んでいます)
2009年05月26日
5月30日、天生県立自然公園オープン
長く冬季閉鎖していた天生峠道路が5月30日から開通します。
ようやく天生湿原や原生林を抜けて籾糠山まで、一般の登山者でも行くことができるようになります。
天生県立自然公園は、昨年その自然保護の取り組みにより表彰された、今注目の場所です。
天生峠道路は豪雪地帯にあるため、冬の間に崖崩れや道路の破損が起こる道です。
つづら折りの林道は、慣れない人には少し緊張を強いられることになるかもしれません。ぜひ安全運転を。
参考までに、オープン時期の天生県立自然公園の様子をご紹介します。
いずれも'07年5月28日に撮影したものです。
天生峠の駐車場から入山し、約30〜40分ほどで到着するのが第一湿原です。中心に匠神社の祠があり、ひょうたん型の植生の豊かな湿原です。
ミズバショウの開花時期ですが、小規模な第二湿原の方が群生しています。

白いのがミズバショウ、黄色いのはリュウキンカです。
小さな湿原を横断し、原生林に入ってすぐに標識がありますので、渓流を渡ってください。
入山口で自然保護協力金500円を払うと案内パンフレットをもらえます。
この湿原に向かう際に通り抜けるのがブナを始めとした巨木が並ぶ原生林。

見上げれば、若葉におおわれた枝が風にゆったりと揺れています。
第二湿原の左手に、籾糠山へ向かう登山道があります。最初は急登が続く道ですが、新緑に染まる大変気持ちのいいコースです。
多くの登山者は第二湿原へ寄り道しないで、渓流沿いを進んで行きます。
登山道の両わきにはニリンソウ・サンカヨウなど高山植物が群生して、登山者を迎えてくれるでしょう。

こちらのコースは木平湿原との分岐を過ぎたあたりから急登が始ります。
多分、ムラサキヤシオツツジが咲いています。
平坦な地形になり、この先で籾糠山へのふたつの登山道は合流します。
針葉樹林帯を抜け、小さな谷を越え(多分まだ残雪があります)、籾糠山が見えてきます。
もうひと登りすれば、ちょっと狭いですが籾糠山の頂上に到着します。

タムシバが咲いている山頂からは、天候がよければ東に天生の山々と飛騨山脈が遠望できるはずです。
西には猿ヶ馬場山(白山は隠れて見えません)、南には御前岳や栗ヶ岳があります。
下山は登りに使わなかったコースをたどるのがおすすめです。
高山グリーンツアーでは、インタープリター(自然案内人)ガイドツアー「天生の原生林を歩きミズバショウに出会う」<6月6日(土)宿泊・7日(日)実施>を行います。
籾糠山登山は行いませんが、天生県立自然公園の豊かな植生を知るには恰好の機会です。興味のある方はぜひご参加ください。
ようやく天生湿原や原生林を抜けて籾糠山まで、一般の登山者でも行くことができるようになります。
天生県立自然公園は、昨年その自然保護の取り組みにより表彰された、今注目の場所です。
天生峠道路は豪雪地帯にあるため、冬の間に崖崩れや道路の破損が起こる道です。
つづら折りの林道は、慣れない人には少し緊張を強いられることになるかもしれません。ぜひ安全運転を。
参考までに、オープン時期の天生県立自然公園の様子をご紹介します。
いずれも'07年5月28日に撮影したものです。
天生峠の駐車場から入山し、約30〜40分ほどで到着するのが第一湿原です。中心に匠神社の祠があり、ひょうたん型の植生の豊かな湿原です。
ミズバショウの開花時期ですが、小規模な第二湿原の方が群生しています。

白いのがミズバショウ、黄色いのはリュウキンカです。
小さな湿原を横断し、原生林に入ってすぐに標識がありますので、渓流を渡ってください。
入山口で自然保護協力金500円を払うと案内パンフレットをもらえます。
この湿原に向かう際に通り抜けるのがブナを始めとした巨木が並ぶ原生林。

見上げれば、若葉におおわれた枝が風にゆったりと揺れています。
第二湿原の左手に、籾糠山へ向かう登山道があります。最初は急登が続く道ですが、新緑に染まる大変気持ちのいいコースです。
多くの登山者は第二湿原へ寄り道しないで、渓流沿いを進んで行きます。
登山道の両わきにはニリンソウ・サンカヨウなど高山植物が群生して、登山者を迎えてくれるでしょう。

こちらのコースは木平湿原との分岐を過ぎたあたりから急登が始ります。
多分、ムラサキヤシオツツジが咲いています。
平坦な地形になり、この先で籾糠山へのふたつの登山道は合流します。
針葉樹林帯を抜け、小さな谷を越え(多分まだ残雪があります)、籾糠山が見えてきます。
もうひと登りすれば、ちょっと狭いですが籾糠山の頂上に到着します。

タムシバが咲いている山頂からは、天候がよければ東に天生の山々と飛騨山脈が遠望できるはずです。
西には猿ヶ馬場山(白山は隠れて見えません)、南には御前岳や栗ヶ岳があります。
下山は登りに使わなかったコースをたどるのがおすすめです。
高山グリーンツアーでは、インタープリター(自然案内人)ガイドツアー「天生の原生林を歩きミズバショウに出会う」<6月6日(土)宿泊・7日(日)実施>を行います。
籾糠山登山は行いませんが、天生県立自然公園の豊かな植生を知るには恰好の機会です。興味のある方はぜひご参加ください。
2009年05月19日
今年度のツアーラインナップ
高山グリーンツアーも今年が2年目。
まだまだ始ったばかりのツアー事業ですが、第三種旅行業資格取得の3年前から準備はしてきました。
当時は資格取得前でしたので、ホテルの無料サービスとしての実施でした。飛騨地域内のあまり知られていない自然や文化も含み、送迎サービスや散策を行ってきました。
資格取得後は、高山市に隣接する市町村に限りツアーを行うことが可能になり、現在ふたつの柱で募集しています。
◎インタープリター(自然案内人・自然と文化案内人)ガイドツアー
◎ベテラン山岳ガイドと行く登山・山歩きツアー
詳しくは高山グリーンツアーのTOPページをご覧ください。
また登山・山歩きツアーのラインナップを公開しました。初心者向けから今年度は中級者向けのツアー(西穂高独標・焼岳)も追加しました。
まだまだ始ったばかりのツアー事業ですが、第三種旅行業資格取得の3年前から準備はしてきました。
当時は資格取得前でしたので、ホテルの無料サービスとしての実施でした。飛騨地域内のあまり知られていない自然や文化も含み、送迎サービスや散策を行ってきました。
資格取得後は、高山市に隣接する市町村に限りツアーを行うことが可能になり、現在ふたつの柱で募集しています。
◎インタープリター(自然案内人・自然と文化案内人)ガイドツアー
◎ベテラン山岳ガイドと行く登山・山歩きツアー
詳しくは高山グリーンツアーのTOPページをご覧ください。
また登山・山歩きツアーのラインナップを公開しました。初心者向けから今年度は中級者向けのツアー(西穂高独標・焼岳)も追加しました。
2009年03月22日
乗鞍高原スノートレッキングツアー
連休の中日、3月21日は雲ひとつない快晴となりました。
ところがツアー翌日の今日は朝から雨が止みません。
先月の上高地行きとあわせ、この冬のツアーは天候に恵まれ、運が良かったなあと思います。
乗鞍高原スノートレッキングツアーにご参加いただいたのはすべて女性。
それも皆さん若く、昨今の中高年登山ブームとは違う年齢層でのツアーとなりました。
登山経験の少ない方が大半で、これをきっかけに山へと安全に楽しくお出かけいただけるとうれしいです。
行程
高山グリーンホテル発<6:35>〜乗鞍高原国民休暇村着<8:25>〜休暇村第1リフト乗車<8:45>〜リフト下車・スノーシュー装着して出発<9:10>〜三本滝レストハウス・最終トイレ休憩<9:40>〜子リスの路<10:00>〜子リスの路をはずれて南斜面を下る〜前川林道と伊奈川合流点(橋あり)に降り立つ<11:00>〜東大ヒュッテ着<11:10>昼食<12:10>〜前川林道〜エコーライン合流点<12:45>〜原生林の小路<13:00>〜牛留池〜国民休暇村着<13:35>〜高山グリーンホテル着<15:30>
出発時の気温は約ー2度C。霧が降りていますが、上空は快晴と想像されます。
安房トンネルを抜けると、まぶしい陽の光を浴びました。
釜トンネルを横目に、先月の上高地ツアーを思い出します。
今日の入山者は多そうです。
国民休暇村に着き、準備を整えたら車道を下りリフト乗車口へ。

ストレッチの後、スノーシューが始めての方がいるので装着の練習をしていざ出発。と思ったらリフトはスノーシューを履いて乗れませんでした。
そんなこともありますので、ザックはスノーシューを装着できるものが必要です。
第1リフトを降りて三本滝レストハウスまでは、ゲレンデをスノーシューで歩きました。

今回のコース唯一の登りであり、スノーシューを使っての歩行練習に丁度良いからです。
とはいえ、ゲレンデですから滑ってくるスキーヤーやボーダーには注意が必要。
コースはゲレンデ脇の林を選びます。
いきなりの登りでしたが、みんな若くて体力があるので難なくクリア。
ほどなく三本滝レストハウスに到着しました。
最後のトイレ休憩の後、いよいよトレッキングコースへ。
ガイドの大野さんから森の木々の話を聞きながら、少々固めの雪面を森の奥へと歩いていきました。
途中、予定のコースの小リスの路をはずれて、南側の斜面へ。例年はほとんど見られない踏み跡がありました。
雪が少ないため、小リスの路はスノーシューで歩くにはコンディションが悪いのかもしれません。
足を踏み入れにくい(自然保護のため入ってはいけないが正しい)無雪期の南側斜面ですが、方向を間違えなければ積雪期にトレッキングコースとして利用できます。
急斜面がほとんどなく、針葉樹の暗い森を歩く小リスの路と違い、明るい林でした。
やがて沢の流れる音が聞こえてくると前川林道が眼下に。慎重に斜面を下り林道に降り立ちます。
伊奈川と前川林道が合流し、小さな橋が架かっています。
前川林道を左へ(橋を渡らない方向)。途中、小さな札が架かっていて、それは林道はクロスカントリーのコースなのでスノーシューで踏み荒らさないようにとの注意書きでした。
しかし、すでにクロカンのシュプールはすっかりスノーシューで踏まれて消えていました。
昨年の前川林道にはクロカンのシュプールがちゃんと残っていたので、今年は暖冬による雪不足がこんなところにも影響していると感じました。
東大ヒュッテに11時過ぎに到着。
乗鞍岳を目の前に、昼食をいただきました。
ツアーにはお弁当が付いています。今回はミックスサンドウィッチにバナナ、ミニトマト、ゆで卵付です。
大野さん持参のコーヒーもみんなでいただきました。

東大ヒュッテでツアースタッフもいっしょに記念撮影。
雲ひとつない快晴のスノートレッキングでした。
これで1年目の登山・山歩きツアーは終了です。
2年目を迎え、さらに内容を充実させてラインナップしました。
2009年 登山・山歩きツアーラインナップ
まずは「飛騨乗鞍高原・日影峠〜かぶと山」(5月31日入山)からです。
ところがツアー翌日の今日は朝から雨が止みません。
先月の上高地行きとあわせ、この冬のツアーは天候に恵まれ、運が良かったなあと思います。
乗鞍高原スノートレッキングツアーにご参加いただいたのはすべて女性。
それも皆さん若く、昨今の中高年登山ブームとは違う年齢層でのツアーとなりました。
登山経験の少ない方が大半で、これをきっかけに山へと安全に楽しくお出かけいただけるとうれしいです。
行程
高山グリーンホテル発<6:35>〜乗鞍高原国民休暇村着<8:25>〜休暇村第1リフト乗車<8:45>〜リフト下車・スノーシュー装着して出発<9:10>〜三本滝レストハウス・最終トイレ休憩<9:40>〜子リスの路<10:00>〜子リスの路をはずれて南斜面を下る〜前川林道と伊奈川合流点(橋あり)に降り立つ<11:00>〜東大ヒュッテ着<11:10>昼食<12:10>〜前川林道〜エコーライン合流点<12:45>〜原生林の小路<13:00>〜牛留池〜国民休暇村着<13:35>〜高山グリーンホテル着<15:30>
出発時の気温は約ー2度C。霧が降りていますが、上空は快晴と想像されます。
安房トンネルを抜けると、まぶしい陽の光を浴びました。
釜トンネルを横目に、先月の上高地ツアーを思い出します。
今日の入山者は多そうです。
国民休暇村に着き、準備を整えたら車道を下りリフト乗車口へ。

ストレッチの後、スノーシューが始めての方がいるので装着の練習をしていざ出発。と思ったらリフトはスノーシューを履いて乗れませんでした。
そんなこともありますので、ザックはスノーシューを装着できるものが必要です。
第1リフトを降りて三本滝レストハウスまでは、ゲレンデをスノーシューで歩きました。

今回のコース唯一の登りであり、スノーシューを使っての歩行練習に丁度良いからです。
とはいえ、ゲレンデですから滑ってくるスキーヤーやボーダーには注意が必要。
コースはゲレンデ脇の林を選びます。
いきなりの登りでしたが、みんな若くて体力があるので難なくクリア。
ほどなく三本滝レストハウスに到着しました。
最後のトイレ休憩の後、いよいよトレッキングコースへ。
ガイドの大野さんから森の木々の話を聞きながら、少々固めの雪面を森の奥へと歩いていきました。
途中、予定のコースの小リスの路をはずれて、南側の斜面へ。例年はほとんど見られない踏み跡がありました。
雪が少ないため、小リスの路はスノーシューで歩くにはコンディションが悪いのかもしれません。
足を踏み入れにくい(自然保護のため入ってはいけないが正しい)無雪期の南側斜面ですが、方向を間違えなければ積雪期にトレッキングコースとして利用できます。
急斜面がほとんどなく、針葉樹の暗い森を歩く小リスの路と違い、明るい林でした。
やがて沢の流れる音が聞こえてくると前川林道が眼下に。慎重に斜面を下り林道に降り立ちます。
伊奈川と前川林道が合流し、小さな橋が架かっています。
前川林道を左へ(橋を渡らない方向)。途中、小さな札が架かっていて、それは林道はクロスカントリーのコースなのでスノーシューで踏み荒らさないようにとの注意書きでした。
しかし、すでにクロカンのシュプールはすっかりスノーシューで踏まれて消えていました。
昨年の前川林道にはクロカンのシュプールがちゃんと残っていたので、今年は暖冬による雪不足がこんなところにも影響していると感じました。
東大ヒュッテに11時過ぎに到着。
乗鞍岳を目の前に、昼食をいただきました。
ツアーにはお弁当が付いています。今回はミックスサンドウィッチにバナナ、ミニトマト、ゆで卵付です。
大野さん持参のコーヒーもみんなでいただきました。

東大ヒュッテでツアースタッフもいっしょに記念撮影。
雲ひとつない快晴のスノートレッキングでした。
これで1年目の登山・山歩きツアーは終了です。
2年目を迎え、さらに内容を充実させてラインナップしました。
2009年 登山・山歩きツアーラインナップ
まずは「飛騨乗鞍高原・日影峠〜かぶと山」(5月31日入山)からです。
2009年03月20日
明日は乗鞍高原へ
明日は乗鞍高原スノートレッキングツアーです。
天気予報は快晴。
青空のなかに白い乗鞍岳がくっきり見えることでしょう。
暖冬により、例年に比べやはり積雪が少ないようです。
今日午前中に出発点の国民休暇村にでかけたガイドの大野さんから連絡がありました。
休暇村周辺のゲレンデはところどころ地面が見えているとのこと。
第1リフトで上った標高1700mくらいは問題なく積雪があると思われます(時間がなかったので未確認)。・・・滑り降りてくるスキー客は多かったので。
明日の気温は今日より低くなりますが、午前中から暖かくなるでしょう。
行動中に体温が上がり汗が出やすくなります。
真冬ほどではありませんが、休憩時に衣類が汗を吸収して冷たくなってきます。特にアンダーウェアは吸湿速乾性のある材質のものを着用することが必要です。
日焼け止めを塗ることも大切です。紫外線の雪からの照り返しは、帽子では防げません。
当然、厚着も必要ありません。
ただし冷たい風が吹く可能性がありますので、防風性能のある上着を用意するといいでしょう。
日曜日には天気は崩れると予想され、まさに明日が最高のツアー日となりそうです。
ご参加の皆様、めいっぱいお楽しみください。

休暇村第1リフトを降りたあたりから見た乗鞍岳。
ここからスノーシューで歩いて(登って)、三本滝レストハウスまで行くと、スノーシューの練習にちょうどよい。・・・三本滝レストハウスは、写真手前のリフトが終わる丘のあたりにあり、登る練習になります。
天気予報は快晴。
青空のなかに白い乗鞍岳がくっきり見えることでしょう。
暖冬により、例年に比べやはり積雪が少ないようです。
今日午前中に出発点の国民休暇村にでかけたガイドの大野さんから連絡がありました。
休暇村周辺のゲレンデはところどころ地面が見えているとのこと。
第1リフトで上った標高1700mくらいは問題なく積雪があると思われます(時間がなかったので未確認)。・・・滑り降りてくるスキー客は多かったので。
明日の気温は今日より低くなりますが、午前中から暖かくなるでしょう。
行動中に体温が上がり汗が出やすくなります。
真冬ほどではありませんが、休憩時に衣類が汗を吸収して冷たくなってきます。特にアンダーウェアは吸湿速乾性のある材質のものを着用することが必要です。
日焼け止めを塗ることも大切です。紫外線の雪からの照り返しは、帽子では防げません。
当然、厚着も必要ありません。
ただし冷たい風が吹く可能性がありますので、防風性能のある上着を用意するといいでしょう。
日曜日には天気は崩れると予想され、まさに明日が最高のツアー日となりそうです。
ご参加の皆様、めいっぱいお楽しみください。

休暇村第1リフトを降りたあたりから見た乗鞍岳。
ここからスノーシューで歩いて(登って)、三本滝レストハウスまで行くと、スノーシューの練習にちょうどよい。・・・三本滝レストハウスは、写真手前のリフトが終わる丘のあたりにあり、登る練習になります。
2009年03月13日
乗鞍高原スノートレッキングツアーまで1週間
来週の土曜日、3月22日(土)にいよいよ「乗鞍高原スノートレッキングツアー」を実施します。
暖冬ですが、スノートレッキングの舞台となる一帯はまだまだ積雪がたっぷりあります。
実はお申し込みされた方から、暖冬による積雪の心配をいただきました。確かにここ数年は雪が少ないのですが、今度のツアー実施時期の積雪は十分あると考えています。
昨年は4月に同じコースでツアーを行いましたが、当初の心配は杞憂に終わりました。
2008年3月29日に行った下見のレポートをご覧いただくと、納得していただけるかもしれません。
◎2008年度・乗鞍高原スノートレッキングツアー下見レポート
今回は昨年の実施日より2週間早めています。
週間天気予報によると、今のところ天候の崩れはなさそうです。
遅い春の訪れを実感するツアーになることでしょう。

昨年のツアーの様子(2008年4月5日)。
暖冬ですが、スノートレッキングの舞台となる一帯はまだまだ積雪がたっぷりあります。
実はお申し込みされた方から、暖冬による積雪の心配をいただきました。確かにここ数年は雪が少ないのですが、今度のツアー実施時期の積雪は十分あると考えています。
昨年は4月に同じコースでツアーを行いましたが、当初の心配は杞憂に終わりました。
2008年3月29日に行った下見のレポートをご覧いただくと、納得していただけるかもしれません。
◎2008年度・乗鞍高原スノートレッキングツアー下見レポート
今回は昨年の実施日より2週間早めています。
週間天気予報によると、今のところ天候の崩れはなさそうです。
遅い春の訪れを実感するツアーになることでしょう。

昨年のツアーの様子(2008年4月5日)。
2009年02月10日
上高地スノートレッキング
2月8日、高山グリーンツアー「上高地スノートレッキング」を行いました。
現地の天候は晴れ。気温も思ったほど低くはありませんでしたが、時折強風が吹き雪が舞いました。
ご参加いただいたのは33名の方。ツアーとしては大所帯となりました。
ガイドの大野さんとホテルスタッフ、そしてわたしで引率となりましたが、パーティーとしては先頭と後続が離れてしまうなど不備もございました。
これが上高地ではなく、登山だとしたら問題が起こることもあったかもしれません。主催者として反省すべきことは多いと感じました。
それはさておき、素晴らしいトレッキングコンディションでした。
前日の雪が適度に積もり、固い雪面歩行を強いられることなくフカフカの状態。スノーシューの出番も多く、楽しんでいただけたようです。

釜トンネルを出て、除雪された林道を歩くこと20分。砂防事務所の入口を過ぎてカーブを曲がると、目の前に穂高連峰の全貌が現れました。
朝日に照らされて、白く輝いています。しばらく立ち止まり、峰々の同定を楽しみました。
坂を下っていくと大正池です。暖かいため(それでも日影では身体が冷えます)、期待していた霧氷は見られませんでした。
林道が除雪されていない地点からスノーシューを装着。大正池ホテルから遊歩道に下り、池の河原を抜けて田代湿原へ向かいます。行く手には穂高連峰が見えます。
林を抜けたところにある田代湿原をスノーシューで歩きました。
その先には田代池が。これが特に皆さんに見てほしかった景色です。
青空と雪原と静かな池。そして穂高の山並み。

踏み跡をふたたたびたどり、遊歩道に戻りました。
田代橋からバスターミナルまで、梓川に沿って歩きます。

人数が多いため、先頭と後続が大きく離れてしまいました。
でも、のんびり自分のペースで歩きたくなる天候の一日でしたから。
バスターミナルで昼食休憩です。

ここで大野さんによるセルフレスキューのレクチャー。
ストック2組を縛り、ツェルト(あるいは衣類)を組み合わせて担架を作りました。
またザックを背負子に変身させる技も。
詳しく知りたい場合は、市販の技術書などで確認してみてください。
・・・単に登るだけのツアーだけでなく、こうした講座を催すのも高山グリーンツアーに加えてもいいかもしれません。
ところで、以前から上高地の冬季トイレが3ヶ所と書いていましたが、今回バスターミナルにも冬季トイレがあることを知りました。
昨年は設けられていなかったので、てっきりないものと思い込んでいました。
改めて冬季トイレは、大正池ホテル、田代橋、バスターミナル、そして小梨平キャンプ場入口の4ヶ所にあります。
今回のツアーにご参加いただいた皆様。お疲れさまでした。
冬の上高地はいかがだったでしょうか。
河童橋で撮った記念写真は、後ほど係より皆様に送らせていただきます。楽しみにお待ちください。
またどこかの山行にご一緒できたら幸いです。
次回のツアーは「乗鞍高原スノートレッキング」。
実施は寒さもゆるむ3月21日ですので、今回のような厳しい防寒対策は必要ありません。
詳しくは高山グリーンツアーのホームページをご覧ください。
現地の天候は晴れ。気温も思ったほど低くはありませんでしたが、時折強風が吹き雪が舞いました。
ご参加いただいたのは33名の方。ツアーとしては大所帯となりました。
ガイドの大野さんとホテルスタッフ、そしてわたしで引率となりましたが、パーティーとしては先頭と後続が離れてしまうなど不備もございました。
これが上高地ではなく、登山だとしたら問題が起こることもあったかもしれません。主催者として反省すべきことは多いと感じました。
それはさておき、素晴らしいトレッキングコンディションでした。
前日の雪が適度に積もり、固い雪面歩行を強いられることなくフカフカの状態。スノーシューの出番も多く、楽しんでいただけたようです。

釜トンネルを出て、除雪された林道を歩くこと20分。砂防事務所の入口を過ぎてカーブを曲がると、目の前に穂高連峰の全貌が現れました。
朝日に照らされて、白く輝いています。しばらく立ち止まり、峰々の同定を楽しみました。
坂を下っていくと大正池です。暖かいため(それでも日影では身体が冷えます)、期待していた霧氷は見られませんでした。
林道が除雪されていない地点からスノーシューを装着。大正池ホテルから遊歩道に下り、池の河原を抜けて田代湿原へ向かいます。行く手には穂高連峰が見えます。
林を抜けたところにある田代湿原をスノーシューで歩きました。
その先には田代池が。これが特に皆さんに見てほしかった景色です。
青空と雪原と静かな池。そして穂高の山並み。

踏み跡をふたたたびたどり、遊歩道に戻りました。
田代橋からバスターミナルまで、梓川に沿って歩きます。

人数が多いため、先頭と後続が大きく離れてしまいました。
でも、のんびり自分のペースで歩きたくなる天候の一日でしたから。
バスターミナルで昼食休憩です。

ここで大野さんによるセルフレスキューのレクチャー。
ストック2組を縛り、ツェルト(あるいは衣類)を組み合わせて担架を作りました。
またザックを背負子に変身させる技も。
詳しく知りたい場合は、市販の技術書などで確認してみてください。
・・・単に登るだけのツアーだけでなく、こうした講座を催すのも高山グリーンツアーに加えてもいいかもしれません。
ところで、以前から上高地の冬季トイレが3ヶ所と書いていましたが、今回バスターミナルにも冬季トイレがあることを知りました。
昨年は設けられていなかったので、てっきりないものと思い込んでいました。
改めて冬季トイレは、大正池ホテル、田代橋、バスターミナル、そして小梨平キャンプ場入口の4ヶ所にあります。
今回のツアーにご参加いただいた皆様。お疲れさまでした。
冬の上高地はいかがだったでしょうか。
河童橋で撮った記念写真は、後ほど係より皆様に送らせていただきます。楽しみにお待ちください。
またどこかの山行にご一緒できたら幸いです。
次回のツアーは「乗鞍高原スノートレッキング」。
実施は寒さもゆるむ3月21日ですので、今回のような厳しい防寒対策は必要ありません。
詳しくは高山グリーンツアーのホームページをご覧ください。
2008年12月18日
上高地スノートレッキング受付終了

高山グリーンツアーで募集しておりました「上高地スノートレッキングツアー」が定員に達しましたので、受付終了とさせていただきました。
3月には「乗鞍高原スノートレッキングツアー」を行います。こちらはひきつづき参加者募集中です。
2008年11月17日
上高地が15日に閉山〜気が早い冬のトレッキング
11月15日、上高地が閉山しました。
飛騨および信州からのシャトルバスやタクシーの運行は来年4月下旬までありません。
しか〜し、これを待っていた人も意外と多いはず。
雪が降る前の上高地、積もりはじめの上高地、雪におおわれた上高地。
上高地が本来の山岳地帯に戻る時期にこそ出かけてみたいと思うのです。
釜トンネルが新しくなってから、冬の入山者も増えてきました。
昔々は大正池まで林道を通らないで、梓川沿いに焼岳側の岸を歩いていたそうです。
・・・この頃の冬の上高地は北アルプスへの入山口としての存在でした・・・
時代も変わり、今では上高地はスノートレッキングの盛んな場所のひとつに。
まずはアクセス。
国道158号線沿いにある釜トンネル入口まで。高山〜松本間の路線バスを利用します。
自家用車の場合は、飛騨側は平湯バスターミナルで、信州側は沢渡のバス乗り場で乗り換えます。
路線バスの本数は少ないです。
1本乗り遅れると大変なことに。事前に確認しておきましょう。
入山準備を整えて、釜トンネルをひたすら歩きます。
寒さと上り傾斜に息があがる人もいます。ゆるい上りですから、準備運動のつもりで歩きましょう。
トンネルを抜けたら一休み。ここからスノートレッキングの始りです。

焼岳が左前方に見えています。
林道は工事車両のために除雪されていることが多いので、まだスノーシューの出番ではありません。
林道を上り下りしながら歩く際には、山側の雪に注意。雪崩れてくることがあるからです。
やがてカーブした林道を曲がると、穂高連峰が目の前に見えてきます(雪が降っていなければですが)。

うっすらと凍った大正池も見えてきます。

林道の先には大正池ホテル。ここでトイレ休憩。
ようやくここでスノーシューを履いて遊歩道へ下りていきます。

大正池の様子も、夏とはずいぶん違います。

朝の陽射しに樹氷がきらきらと光っていたり、河原に積もった雪の上を歩いてみたり。
雪って楽しい!って思うんですよね、こんな時。
2月になれば、雪の量も十分なので、遊歩道のコースをはずれても大丈夫です。
ただし、足下には十分気をつけて。
わたしのおすすめは田代池。
田代湿原に入り、雪の無い時期には見ることのできない田代池を見に行きます。

池の向こうには穂高連峰がそびえています。
池の水面にその姿が映っています。本当に神秘的で美しい。
田代池を後にして、11時半までには河童橋に到着するよう心がけます。
なぜなら昼休みを少し長めに取って、帰りの路線バスに間に合うためには、ある程度の余裕が必要だからです。・・・帰りのバスの時刻表を確認しておきましょう。

田代橋から穂高を眺めながら河童橋へ。
向かって右の岸には猿の群れがたむろしていることがあるので気をつけます。
逃げたり、恐がったりしないこと。一番強そうなオスザルをにらみながら(つまり隙を見せないで)堂々と前へ。
ただし脅したりするとかえって逆効果。
目の前で食事をするなんてもっての他。
冬の上高地は彼らの方が家主です。

冬季閉鎖中の建物の軒下で昼食。しかし屋根からの落雪には気をつけます。
できれば携帯コンロを持参して温かい飲みものを楽しみたいものです。
少なくとも30分はゆっくりし、人で混雑していない河童橋から、穂高や焼を眺めるのはいい気分です。
帰りは路線バスに間に合うように時間を稼ぐため、林道を使って戻ります。
吹雪いたりして天候の悪い日は無理をしないで引き返しましょう。
そんな日は、期待していた北アルプス展望もかなわない日なのですから。
飛騨および信州からのシャトルバスやタクシーの運行は来年4月下旬までありません。
しか〜し、これを待っていた人も意外と多いはず。
雪が降る前の上高地、積もりはじめの上高地、雪におおわれた上高地。
上高地が本来の山岳地帯に戻る時期にこそ出かけてみたいと思うのです。
釜トンネルが新しくなってから、冬の入山者も増えてきました。
昔々は大正池まで林道を通らないで、梓川沿いに焼岳側の岸を歩いていたそうです。
・・・この頃の冬の上高地は北アルプスへの入山口としての存在でした・・・
時代も変わり、今では上高地はスノートレッキングの盛んな場所のひとつに。
まずはアクセス。
国道158号線沿いにある釜トンネル入口まで。高山〜松本間の路線バスを利用します。
自家用車の場合は、飛騨側は平湯バスターミナルで、信州側は沢渡のバス乗り場で乗り換えます。
路線バスの本数は少ないです。
1本乗り遅れると大変なことに。事前に確認しておきましょう。
入山準備を整えて、釜トンネルをひたすら歩きます。
寒さと上り傾斜に息があがる人もいます。ゆるい上りですから、準備運動のつもりで歩きましょう。
トンネルを抜けたら一休み。ここからスノートレッキングの始りです。

焼岳が左前方に見えています。
林道は工事車両のために除雪されていることが多いので、まだスノーシューの出番ではありません。
林道を上り下りしながら歩く際には、山側の雪に注意。雪崩れてくることがあるからです。
やがてカーブした林道を曲がると、穂高連峰が目の前に見えてきます(雪が降っていなければですが)。

うっすらと凍った大正池も見えてきます。

林道の先には大正池ホテル。ここでトイレ休憩。
ようやくここでスノーシューを履いて遊歩道へ下りていきます。

大正池の様子も、夏とはずいぶん違います。

朝の陽射しに樹氷がきらきらと光っていたり、河原に積もった雪の上を歩いてみたり。
雪って楽しい!って思うんですよね、こんな時。
2月になれば、雪の量も十分なので、遊歩道のコースをはずれても大丈夫です。
ただし、足下には十分気をつけて。
わたしのおすすめは田代池。
田代湿原に入り、雪の無い時期には見ることのできない田代池を見に行きます。

池の向こうには穂高連峰がそびえています。
池の水面にその姿が映っています。本当に神秘的で美しい。
田代池を後にして、11時半までには河童橋に到着するよう心がけます。
なぜなら昼休みを少し長めに取って、帰りの路線バスに間に合うためには、ある程度の余裕が必要だからです。・・・帰りのバスの時刻表を確認しておきましょう。

田代橋から穂高を眺めながら河童橋へ。
向かって右の岸には猿の群れがたむろしていることがあるので気をつけます。
逃げたり、恐がったりしないこと。一番強そうなオスザルをにらみながら(つまり隙を見せないで)堂々と前へ。
ただし脅したりするとかえって逆効果。
目の前で食事をするなんてもっての他。
冬の上高地は彼らの方が家主です。

冬季閉鎖中の建物の軒下で昼食。しかし屋根からの落雪には気をつけます。
できれば携帯コンロを持参して温かい飲みものを楽しみたいものです。
少なくとも30分はゆっくりし、人で混雑していない河童橋から、穂高や焼を眺めるのはいい気分です。
帰りは路線バスに間に合うように時間を稼ぐため、林道を使って戻ります。
吹雪いたりして天候の悪い日は無理をしないで引き返しましょう。
そんな日は、期待していた北アルプス展望もかなわない日なのですから。
2008年11月10日
この冬はスノートレッキングへ
晩秋を迎える飛騨高山。ここ数日は太陽が顔をのぞかせないので、いっそう寂しさつのる趣です。
日本海に面した地方(富山県など)では、豪雪地帯のイメージがある一方で、水気を含んだ雪は解けやすいという特徴があります。一方、内陸にあり山に囲まれた飛騨北中部では、水気の少ないいわゆるパウダースノーが降り積もります。この雪は解けにくく、根雪になると堅く凍り手がつけられません。
この2年、雪の少ない冬が続きましたが、今度はどんな冬になるのでしょう。
雪が生活に深く関わっていると、雪をむしろ楽しもうという気持ちがわいてきます。・・・そんなことはない、という飛騨在住の方も多いと思いますが。
ウインタースポーツはゲレンデスキーやスノーボードがこの地方でも主流ですが、一方で山岳スキーを楽しむ人も少なからずいます。
穂高などの北アルプスから滑降してくる熟練者から、登山道のない低山を積雪期にこそ楽しむという人まで、冬山はテレマークスキーにより無雪期とは違う楽しみが広がります。
しかしスキーはちょっと、という人でも雪山を楽しめる道具があります。
どちらかというと雪山登山の1ツールとして使われることが多いワカン(和かんじき)にくらべ、トレッキングの色々な状況に対応できるスノーシューは、積雪期の山を諦めていた人も雪山へと足を向けさせるようになりました。
スノーシューが特に得意なのは、アップダウンのある森の中や平坦な雪原です。
夏は規制があり足を踏み込めない湿原も、スノーシューでなら歩くこともできます。
もちろん自然を荒らさないよう気をつける必要があります。雪の下に隠れて流れている小川に足を踏み抜いてしまった、という事故も時には起こります。
また知らない山域に入る時は、そこに詳しい人と一緒に行くか、登山道を外れないように気をつけてください。積雪期の道迷いは時に致命的な結果をもたらすことになってしまいます。
高山グリーンツアーでは、特に人気の高い2つのスノートレッキングコースを選び、山行を実施します。

積雪が十分あり、足を踏み入れても湿原などを荒らすことがない2月には「上高地」へ。
入山日:2月8日(日)

そして、雪解けが始るころの春間近3月下旬には「乗鞍高原」に出かけます。
入山日:3月21日(土)・・・前日は春分の日
詳しくは高山グリーンツアー・登山専用のホームページをご覧ください。
日本海に面した地方(富山県など)では、豪雪地帯のイメージがある一方で、水気を含んだ雪は解けやすいという特徴があります。一方、内陸にあり山に囲まれた飛騨北中部では、水気の少ないいわゆるパウダースノーが降り積もります。この雪は解けにくく、根雪になると堅く凍り手がつけられません。
この2年、雪の少ない冬が続きましたが、今度はどんな冬になるのでしょう。
雪が生活に深く関わっていると、雪をむしろ楽しもうという気持ちがわいてきます。・・・そんなことはない、という飛騨在住の方も多いと思いますが。
ウインタースポーツはゲレンデスキーやスノーボードがこの地方でも主流ですが、一方で山岳スキーを楽しむ人も少なからずいます。
穂高などの北アルプスから滑降してくる熟練者から、登山道のない低山を積雪期にこそ楽しむという人まで、冬山はテレマークスキーにより無雪期とは違う楽しみが広がります。
しかしスキーはちょっと、という人でも雪山を楽しめる道具があります。
どちらかというと雪山登山の1ツールとして使われることが多いワカン(和かんじき)にくらべ、トレッキングの色々な状況に対応できるスノーシューは、積雪期の山を諦めていた人も雪山へと足を向けさせるようになりました。
スノーシューが特に得意なのは、アップダウンのある森の中や平坦な雪原です。
夏は規制があり足を踏み込めない湿原も、スノーシューでなら歩くこともできます。
もちろん自然を荒らさないよう気をつける必要があります。雪の下に隠れて流れている小川に足を踏み抜いてしまった、という事故も時には起こります。
また知らない山域に入る時は、そこに詳しい人と一緒に行くか、登山道を外れないように気をつけてください。積雪期の道迷いは時に致命的な結果をもたらすことになってしまいます。
高山グリーンツアーでは、特に人気の高い2つのスノートレッキングコースを選び、山行を実施します。

積雪が十分あり、足を踏み入れても湿原などを荒らすことがない2月には「上高地」へ。
入山日:2月8日(日)

そして、雪解けが始るころの春間近3月下旬には「乗鞍高原」に出かけます。
入山日:3月21日(土)・・・前日は春分の日
詳しくは高山グリーンツアー・登山専用のホームページをご覧ください。