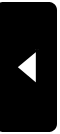スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2012年02月05日
上高地スノートレッキング2012
早朝は身を切るような寒さでしたが、太陽が顔を出すと手も快適なトレッキングでした。3年連続で参加している管理人も改めて感動するほどのベストコンディション。参加の皆様も大変感激されていました。今日はこの一枚を載せて、詳細はまた明日書きます。

山岳ガイドの大野さんのサングラスを見れば今日の晴天はお分かりでしょう(笑) 田代池にて。

山岳ガイドの大野さんのサングラスを見れば今日の晴天はお分かりでしょう(笑) 田代池にて。
2011年10月28日
国見山
飛騨地方は今日も快晴。飛騨山脈の展望台となりそうな国見山に登ってきました。丹生川から上宝に抜ける駒鼻峠から15分も登ると山頂です。紅葉も真っ盛りでベストシーズンです。

標高は1318.2mです。麓の呂瀬(ろっせ)から見上げるとなかなか姿の良い山です。

山頂からの乗鞍岳。南は御岳から北は剣岳(頭だけ)まで、天気も良く本当に綺麗に見えました。惜しむらくは槍ヶ岳が笠ヶ岳の陰になって見えないことでしょうか。
この山は「飛騨の山」にも飛騨から日本海が見えるという山として紹介されています。残念ながら峠に戻ってからこの話を思い出してので、今日は検証できませんでした。気楽に登れる山ですし、駒鼻峠は高山から奥飛騨に抜ける隠れルートでもあります。ぜひ、天気の良い日にお訪ね下さい。

標高は1318.2mです。麓の呂瀬(ろっせ)から見上げるとなかなか姿の良い山です。

山頂からの乗鞍岳。南は御岳から北は剣岳(頭だけ)まで、天気も良く本当に綺麗に見えました。惜しむらくは槍ヶ岳が笠ヶ岳の陰になって見えないことでしょうか。
この山は「飛騨の山」にも飛騨から日本海が見えるという山として紹介されています。残念ながら峠に戻ってからこの話を思い出してので、今日は検証できませんでした。気楽に登れる山ですし、駒鼻峠は高山から奥飛騨に抜ける隠れルートでもあります。ぜひ、天気の良い日にお訪ね下さい。
2011年10月20日
錫杖岳
秋の高山祭りが晴天に恵まれて終わった翌日に、錫杖岳に登ってきました。岐阜県の名峰笠ヶ岳の南にあるこの山はロッククライマーには名が通っていますが、一般にはまだまだ知られていない山です。山と渓谷社の「岐阜県の山」に飛騨の怪峰として収録されていますが、あまり一般向きの山とは言えません。

山麓の中尾温泉付近からはこの山の険しさがよく判ります。写真は笠ヶ岳へ通じるクリヤ谷の登山道から錫杖沢へ降りた辺りからのものです。

明確な登山道はなく、ひたすら大木場ノ辻へ伸びる尾根の鞍部を目指して沢を詰めていきます。我々は途中でルートよりも左の沢に入ってしましい、1時間ほど強烈な藪漕ぎをすることになりました。

頂上はP1からP3に分かれており、P3には有名なピッケルが岩の間に刺さっています。今回はP2まで行きましたが、P1への明瞭な踏み跡がわからず、そこで断念しました。

復路の沢では紅葉が始まっており、疲れた体が癒されます。
この山は十分な経験と体力が要求されますが、久方ぶりに大変面白い山行となりました。

山麓の中尾温泉付近からはこの山の険しさがよく判ります。写真は笠ヶ岳へ通じるクリヤ谷の登山道から錫杖沢へ降りた辺りからのものです。

明確な登山道はなく、ひたすら大木場ノ辻へ伸びる尾根の鞍部を目指して沢を詰めていきます。我々は途中でルートよりも左の沢に入ってしましい、1時間ほど強烈な藪漕ぎをすることになりました。

頂上はP1からP3に分かれており、P3には有名なピッケルが岩の間に刺さっています。今回はP2まで行きましたが、P1への明瞭な踏み跡がわからず、そこで断念しました。

復路の沢では紅葉が始まっており、疲れた体が癒されます。
この山は十分な経験と体力が要求されますが、久方ぶりに大変面白い山行となりました。
2011年09月11日
位山 1529.2m
台風12号が通り過ぎた先日、飛騨の分水嶺となっている名山霊峰「位山」へ登ってきました。一般的にはモンデウススキー場からの尾根ルートが登られていますが、今回は西側の山腹を巻く「ダナ平林道」へ車を乗り入れて、終点から巨石群を見ながら登る最短ルートです。

ダナ平林道の終点には立派なトイレと展望台があり、穂高連峰から北の山々がこの日もよく見えました。山頂までは約1.5キロで、最初の1/3がかなりの急登です。

途中でこんな看板が。西田天香さんという方をよく知りませんが、登山にも通じる言葉のように思えます。この辺りから傾斜が落ちて、登山路は山頂の広い台地部分にさしかかります。

この看板が見えると頂上はすぐそこです。残念ながら山頂からは木々に邪魔をされて展望がありませんが、御岳展望台、乗鞍展望台、白山展望台などから絶景を楽しむことが出来ます。

写真は乗鞍展望台から。飛騨山脈が冠雪したらぜひまた来てみたいですね。
ダナ平林道は普通乗用車でも走れますが、状況は道の駅などで確認されることをお勧めします。山頂直下には「天の泉」と名付けられた水場もありトイレも完備しています。思い立ったら気楽に上れるルートです。次回は雪のある時にモンデウススキー場から登ってみたいと思いました。
現在募集中のツアーです。

ダナ平林道の終点には立派なトイレと展望台があり、穂高連峰から北の山々がこの日もよく見えました。山頂までは約1.5キロで、最初の1/3がかなりの急登です。

途中でこんな看板が。西田天香さんという方をよく知りませんが、登山にも通じる言葉のように思えます。この辺りから傾斜が落ちて、登山路は山頂の広い台地部分にさしかかります。

この看板が見えると頂上はすぐそこです。残念ながら山頂からは木々に邪魔をされて展望がありませんが、御岳展望台、乗鞍展望台、白山展望台などから絶景を楽しむことが出来ます。

写真は乗鞍展望台から。飛騨山脈が冠雪したらぜひまた来てみたいですね。
ダナ平林道は普通乗用車でも走れますが、状況は道の駅などで確認されることをお勧めします。山頂直下には「天の泉」と名付けられた水場もありトイレも完備しています。思い立ったら気楽に上れるルートです。次回は雪のある時にモンデウススキー場から登ってみたいと思いました。
現在募集中のツアーです。
2011年09月06日
下呂御前山(空谷山)
久しぶりに青空の飛騨地方です。天気も悪く仕事も忙しくて少し山から遠ざかって今したので、ナイト明けの眠たい体に活をいれて、下呂御前山に登って来ました。

下呂の町から北東方向を望むと顕著なピークが見えます。これが下呂御前山です。国土地理院の二万五千分の一地図では空谷山と表示されています。今日は短期決戦のため、下呂小坂林道の観音峠から尾根通しに頂上を狙いました。

残念ながら御岳には雲がかかっていましたが、下呂の町がはっきりと俯瞰出来ます。

今日は私めの愛犬と一緒に登ってきました。

帰りに見つけた「ヤマジノホトトギス」だと思うのですが・・・。
南飛騨にも面白そうな山がたくさんあります。機会を見つけてご紹介します。
今日のコースタイム: 観音峠12:35--山頂13:15-13:25-観音峠13:05
現在9月21日宿泊で「北アルプス鏡平&弓折岳トレッキングツアー」を募集中です。
詳細は以下のリンクからどうぞ! 皆様のご参加をお待ちしております。
http://www.takayama-gh.com/pdf/2011kagamidaira.pdf

下呂の町から北東方向を望むと顕著なピークが見えます。これが下呂御前山です。国土地理院の二万五千分の一地図では空谷山と表示されています。今日は短期決戦のため、下呂小坂林道の観音峠から尾根通しに頂上を狙いました。

残念ながら御岳には雲がかかっていましたが、下呂の町がはっきりと俯瞰出来ます。

今日は私めの愛犬と一緒に登ってきました。

帰りに見つけた「ヤマジノホトトギス」だと思うのですが・・・。
南飛騨にも面白そうな山がたくさんあります。機会を見つけてご紹介します。
今日のコースタイム: 観音峠12:35--山頂13:15-13:25-観音峠13:05
現在9月21日宿泊で「北アルプス鏡平&弓折岳トレッキングツアー」を募集中です。
詳細は以下のリンクからどうぞ! 皆様のご参加をお待ちしております。
http://www.takayama-gh.com/pdf/2011kagamidaira.pdf
2011年08月02日
岐阜県自然公園エコツーリズムモデル事業
なかなか天気が安定しませんが、みなさん楽しい山登りをしていらっしゃいますか?今日は先月24日~25日に実施された「岐阜県自然公園エコツーリズムモデル事業」の『乗鞍お花畑と打津江四十八滝散策ツアー』の様子をお伝えします。このツアーは名古屋発で当ホテルが実施し、スタッフが添乗員としてご案内させて頂きました。既に姉妹ブログにも記事が出ています。

乗鞍では畳平から少し下ったお花畑で、案内人の解説のもと高山植物を楽しんで頂けました。

チングルマやクロユリなどたくさんの花が咲いています。

翌日はホテルからバスで20分ほどの宇津江四十八滝へご案内しました。

山登りと言うよりはハイキングに近いツアーですが専門の案内人の説明があり、皆さん大変ご満足頂けました。
今月27日には同じシリーズの伊吹山ツアーが実施されます。詳細は以下のリンクからご覧下さい。

乗鞍では畳平から少し下ったお花畑で、案内人の解説のもと高山植物を楽しんで頂けました。

チングルマやクロユリなどたくさんの花が咲いています。

翌日はホテルからバスで20分ほどの宇津江四十八滝へご案内しました。

山登りと言うよりはハイキングに近いツアーですが専門の案内人の説明があり、皆さん大変ご満足頂けました。
今月27日には同じシリーズの伊吹山ツアーが実施されます。詳細は以下のリンクからご覧下さい。
2011年07月11日
丸山で見かけた花
飛騨地方は今日も梅雨明けの夏空です。こんな時、夕方からは積乱雲の発達で夕立となり、思わぬ事態に遭遇することもあるので、山では早立ち早着が大原則です。
昨日の丸山で見かけた高山植物をご紹介します。

コイワカガミです。山荘から丸山へのハイマツの陰などにまとまって咲いています。

イワツメクサ。丸山周辺で簡単に見つけられます。

こちらはコケモモ。丸山で食事中に見つけました。名前がすぐに分からない時や自信がない時もデジカメで撮っておくと後で簡単に調べられます。

オオサクラソウは診療所脇の立入禁止区域に咲いていました。ちょっと望遠で。

最後はベニバナイチゴ。花の感じが似ているので「シラネアオイ」ではとご案内したかも知れませんが、全くの勘違い。シラネアオイはもっと草丈の低い植物です。
この他にもたくさんの花が見られます。名前を覚えるのも山登りの楽しみです。
昨日の丸山で見かけた高山植物をご紹介します。

コイワカガミです。山荘から丸山へのハイマツの陰などにまとまって咲いています。

イワツメクサ。丸山周辺で簡単に見つけられます。

こちらはコケモモ。丸山で食事中に見つけました。名前がすぐに分からない時や自信がない時もデジカメで撮っておくと後で簡単に調べられます。

オオサクラソウは診療所脇の立入禁止区域に咲いていました。ちょっと望遠で。

最後はベニバナイチゴ。花の感じが似ているので「シラネアオイ」ではとご案内したかも知れませんが、全くの勘違い。シラネアオイはもっと草丈の低い植物です。
この他にもたくさんの花が見られます。名前を覚えるのも山登りの楽しみです。
2011年07月10日
西穂丸山トレッキング 2011
梅雨明け三日目の日曜日。今日は西穂高の丸山へトレッキングに出かけてきました。お客様は4組のご夫婦。お供はガイドの大野さんとアシスタントの廣田さん、フロントから私めがお手伝いに行って参りました。皆様の心がけがよほど良かったのか晴天の登山日和です。

ロープウェーを降りると正面には笠ヶ岳の雄姿がはっきりくっきり、皆さんの意気が上がります。恒例のストレッチをして早速出発。

千石平ではお約束の「キヌガサソウ」が今を盛りと皆さんを待っています。晴天ですが風が涼しく快適に確実に西穂山荘を目指します。

山荘からは少し岩の混じったルートになります。安全のためにストック利用の方はしばらく仕舞って歩いて頂きました。ハイマツの間には、イワカガミやイワネツメクサが咲いていて和ませてくれます。

一時ガスの中に消えた笠ヶ岳が、丸山到着と同時にまた姿を現しました。独標へ向かう登山者を見送りながら、今日はここでゆっくりと昼食。回りの景色を楽しみます。

今日ご参加の皆様です。晴天に恵まれて皆様大変喜んで頂きました。ぜひまたご一緒しましょう。
今日のコースタイム:西穂口09:00-西穂山荘10:45-丸山11:10-11:50-西穂山荘12:10-12:30-西穂口14:00

ロープウェーを降りると正面には笠ヶ岳の雄姿がはっきりくっきり、皆さんの意気が上がります。恒例のストレッチをして早速出発。

千石平ではお約束の「キヌガサソウ」が今を盛りと皆さんを待っています。晴天ですが風が涼しく快適に確実に西穂山荘を目指します。

山荘からは少し岩の混じったルートになります。安全のためにストック利用の方はしばらく仕舞って歩いて頂きました。ハイマツの間には、イワカガミやイワネツメクサが咲いていて和ませてくれます。

一時ガスの中に消えた笠ヶ岳が、丸山到着と同時にまた姿を現しました。独標へ向かう登山者を見送りながら、今日はここでゆっくりと昼食。回りの景色を楽しみます。

今日ご参加の皆様です。晴天に恵まれて皆様大変喜んで頂きました。ぜひまたご一緒しましょう。
今日のコースタイム:西穂口09:00-西穂山荘10:45-丸山11:10-11:50-西穂山荘12:10-12:30-西穂口14:00
2011年03月21日
乗鞍高原スノートレッキング2011
2011年3月6日(日)に実施された乗鞍高原スノートレッキングの様子をアップします。
管理人は残念ながら業務の都合で参加できませんでしたので、データは元管理人さん
から頂きました。
それでは~
少し晴れ間の見える高山を出発して乗鞍高原へ。
凍えるほどの寒さでしたが、バスの窓からは青空と乗鞍岳を望む事ができました。
バスの利用は除雪の最終地点である国民休暇村まで。ここで準備を整え休暇村の
リフトに乗車します。
実は今回のトレッキングでは、リフトに乗っている間が一番寒さを感じました。
そのため風を通さないジャケットを着て防寒対策。
晴れていても風が吹き抜けるので必要です。
リフトを2つ乗り継いで、三本滝レストハウス前のゲレンデを向いの樹林帯へ横
断します。
雪におおわれていなければ小リスの径と呼ばれる遊歩道はすぐ分りますが、積雪
期は赤い布きれが入口の目印です。
スノーシューで樹林帯に入り、しばらく進むと拓けた場所に出ました。

実はここは小さな沼地と湿原。
雪がたっぷりあるこの時期は、まるで雪の広場のようです。
雪に残された踏み跡は数日来の積雪でほとんど分りません。
ガイドの大野さんのあとを一列になって進み、やがて突き当たりに斜面が現われ
ました。
小リスの径は斜面の手前を左手に曲がり下っていますが、この時期は利用する人
はほとんどいません。
わたしたち一行も突き当たりの斜面を利用します。
流れ込みがあるので落ちないように気をつけましょう。
初めての場合は地形図で場所を確認。下を通る林道に向かいます。
東大ヒュッテのある左方向を意識するのがポイントです。
林道にかかる橋の前に下りられたら、林道を左へ。
途中で樹林帯を進むと、やがて東大ヒュッテに到着しました。
ここで早めの昼食です。
朝見えていた乗鞍岳は雲に隠れていました。
東大ヒュッテからは大野さんに続き思い思いにスノーシューのトレースを雪の上
につけて楽しみました。
乗鞍高原を望む展望地に上がり、その下に広がる湿原地帯を歩きます。
 樹林帯を抜けてエコーラインを横断し原生林の小径に。
樹林帯を抜けてエコーラインを横断し原生林の小径に。
オオシラビソの中を国民休暇村へ戻りました。
今回のスノーシューツアーはここまで。
オプションで氷結した善五郎の滝を見に行く事にしました。
滝つぼへの下りは圧雪と氷で大変滑りやすく注意が必要で、スノーシューではかえって危険です。

滝ではアイスクライミングを楽しむ人たちが。
氷瀑は美しく迫力がありました。
今回のトレッキングはほとんどを下るので体力的には楽でした。
身体を冷やすので心配していた汗もかき過ぎる事はなく一安心。
個人で行く場合は必ずコースの下調べと地形図の持参をおすすめします。
今回ご参加頂いた皆様、また一緒に楽しみましょうね!
*********************************************
次回のトレッキングは
安全に楽しく山歩きを楽しむための登山実践教室を企画しました!
初心者の方や登山を基本から学びたい方におすすめです。
管理人は残念ながら業務の都合で参加できませんでしたので、データは元管理人さん
から頂きました。
それでは~
少し晴れ間の見える高山を出発して乗鞍高原へ。
凍えるほどの寒さでしたが、バスの窓からは青空と乗鞍岳を望む事ができました。
バスの利用は除雪の最終地点である国民休暇村まで。ここで準備を整え休暇村の
リフトに乗車します。
実は今回のトレッキングでは、リフトに乗っている間が一番寒さを感じました。
そのため風を通さないジャケットを着て防寒対策。
晴れていても風が吹き抜けるので必要です。
リフトを2つ乗り継いで、三本滝レストハウス前のゲレンデを向いの樹林帯へ横
断します。
雪におおわれていなければ小リスの径と呼ばれる遊歩道はすぐ分りますが、積雪
期は赤い布きれが入口の目印です。
スノーシューで樹林帯に入り、しばらく進むと拓けた場所に出ました。

実はここは小さな沼地と湿原。
雪がたっぷりあるこの時期は、まるで雪の広場のようです。
雪に残された踏み跡は数日来の積雪でほとんど分りません。
ガイドの大野さんのあとを一列になって進み、やがて突き当たりに斜面が現われ
ました。
小リスの径は斜面の手前を左手に曲がり下っていますが、この時期は利用する人
はほとんどいません。
わたしたち一行も突き当たりの斜面を利用します。
流れ込みがあるので落ちないように気をつけましょう。
初めての場合は地形図で場所を確認。下を通る林道に向かいます。
東大ヒュッテのある左方向を意識するのがポイントです。
林道にかかる橋の前に下りられたら、林道を左へ。
途中で樹林帯を進むと、やがて東大ヒュッテに到着しました。
ここで早めの昼食です。
朝見えていた乗鞍岳は雲に隠れていました。
東大ヒュッテからは大野さんに続き思い思いにスノーシューのトレースを雪の上
につけて楽しみました。
乗鞍高原を望む展望地に上がり、その下に広がる湿原地帯を歩きます。
 樹林帯を抜けてエコーラインを横断し原生林の小径に。
樹林帯を抜けてエコーラインを横断し原生林の小径に。オオシラビソの中を国民休暇村へ戻りました。
今回のスノーシューツアーはここまで。
オプションで氷結した善五郎の滝を見に行く事にしました。
滝つぼへの下りは圧雪と氷で大変滑りやすく注意が必要で、スノーシューではかえって危険です。

滝ではアイスクライミングを楽しむ人たちが。
氷瀑は美しく迫力がありました。
今回のトレッキングはほとんどを下るので体力的には楽でした。
身体を冷やすので心配していた汗もかき過ぎる事はなく一安心。
個人で行く場合は必ずコースの下調べと地形図の持参をおすすめします。
今回ご参加頂いた皆様、また一緒に楽しみましょうね!
*********************************************
次回のトレッキングは
安全に楽しく山歩きを楽しむための登山実践教室を企画しました!
初心者の方や登山を基本から学びたい方におすすめです。
2011年02月26日
上高地スノートレッキング 2011
大変遅くなりましたが、今月6日に実施された「上高地スノートレッキング」の報告をさせて頂ます。今年も昨年同様にスタッフ4名を含めて30名の大所帯となりました。当日の天候は晴れで申し分なく、あまり寒くもない恵まれた環境で上高地を楽しんできました。

上高地への入り口「釜トンネル」です。今回のスノートレッキングでは唯一の登りです。全長1,310メートル斜度11%の寒いトンネルをヘッドランプを頼りに登ります。
トンネルを抜けてしばらく歩くと大正池に出ます。唐松の枝に付いた霧氷がとても幻想的な風景を醸し出しています。帰りにはすっかり融けていますので、しっかり目に焼き付けておきましょう。


霧氷がどのように付いているのかちょっと寄って撮ってみました。

大正池ホテルで最初の大休止を取り、いよいよスノーシューを履いて池畔へ出ます。

この日は一日中、穂高連峰がよく見えていました。田代湿原は遊歩道以外への踏み込みが出来ないようにロープで規制線が作られています。冬の上高地もすっかりポピュラーになって週末にはかなりの登山者が入山しているようです。

田代橋から梓川左岸を歩いて、小梨平の入口で昼食。お昼の後はガイドの大野さんからレスキューの講習もありました。本で勉強するよりも実物を見ておけば、何かの時にきっと役に立ちそうです。

復路は河童橋から林道沿いに大正池に戻りました。途中で猿のグループが素知らぬ顔で横切って行きました。

今回、グリーンツアーにご参加の皆さんです。本当に天候に恵まれて、皆さん大変感激されていらっしゃいました。ぜひ来年のツアーにはこのブログをご覧のあなたもご参加下さい。お待ちいたしております。
今回のコースタイム:釜トンネル(07:45)~大正池(08:50-09:10)~田代池(10:00)~田代橋(10:35-11:00)~小梨平(11:40-12:30)~大正池(14:00-14:15)~釜トンネル(15:10)

上高地への入り口「釜トンネル」です。今回のスノートレッキングでは唯一の登りです。全長1,310メートル斜度11%の寒いトンネルをヘッドランプを頼りに登ります。
トンネルを抜けてしばらく歩くと大正池に出ます。唐松の枝に付いた霧氷がとても幻想的な風景を醸し出しています。帰りにはすっかり融けていますので、しっかり目に焼き付けておきましょう。


霧氷がどのように付いているのかちょっと寄って撮ってみました。

大正池ホテルで最初の大休止を取り、いよいよスノーシューを履いて池畔へ出ます。

この日は一日中、穂高連峰がよく見えていました。田代湿原は遊歩道以外への踏み込みが出来ないようにロープで規制線が作られています。冬の上高地もすっかりポピュラーになって週末にはかなりの登山者が入山しているようです。

田代橋から梓川左岸を歩いて、小梨平の入口で昼食。お昼の後はガイドの大野さんからレスキューの講習もありました。本で勉強するよりも実物を見ておけば、何かの時にきっと役に立ちそうです。

復路は河童橋から林道沿いに大正池に戻りました。途中で猿のグループが素知らぬ顔で横切って行きました。

今回、グリーンツアーにご参加の皆さんです。本当に天候に恵まれて、皆さん大変感激されていらっしゃいました。ぜひ来年のツアーにはこのブログをご覧のあなたもご参加下さい。お待ちいたしております。
今回のコースタイム:釜トンネル(07:45)~大正池(08:50-09:10)~田代池(10:00)~田代橋(10:35-11:00)~小梨平(11:40-12:30)~大正池(14:00-14:15)~釜トンネル(15:10)
2010年06月12日
天生県立自然公園
天生峠の冬季閉鎖が6月11日に解除されました。
例年より10日以上遅い開通です。
これで飛騨地方の冬季閉鎖はすべてなくなりました。
今日はさっそく籾糠山へ出かけてみました。
家を9時15分に出発。河合町から峠へと入りました。
約1時間で峠にある駐車場に到着すると、すでに満車状態。あふれた車が路上駐車していました。

ちょうど帰るところだった新聞社の車が出たので、係の人にお願いして入れさせてもらいました。
ちなみにこの時点で飛騨ナンバーの車は2台目だったそうです。県外の車も多く、関東や関西のナンバーも目立ちました。
自然保護協力金500円(任意)を収め、入山します。
湿原や原生林までを目的とした人も多く、籾糠山へ行く人の数と合わせて200人以上はいたのでは。
開通が遅れたので、第一湿原のミズバショウは花がほとんど終わっていました。

代わってリュウキンカやコバイケイソウが咲き始めていました。
湿原周辺にはさまざまな亜高山帯の植物が見られます。しかし小さくて気付かないものも多く、詳しいガイドと一緒に回ると楽しいことでしょう。
第一湿原から林を下るとまた小さな湿原があり、こちらにはリュウキンカやニリンソウ、サンカヨウなどがお花畑となっていました。
原生林に入り、第二湿原へ。こちらはまだミズバショウが一面に咲いていました。
籾糠山への登りは第二湿原近くの入山口からブナの原生林の急登コースを歩きました。

こちらの道は歩く人も少なく、静かな山歩きが楽しめます。
道沿いにはツバメオモトやバイカオウレン、ミヤマカタバミなどが咲いていました。ユキザサやマイヅルソウはこれからです。
登山道がゆるやかになると、谷から上がってくる主要登山道と合流です。
ベンチが新しくなっていました。
ここから籾糠山までの道は登山者の列ができていました。
頂上直下の急登を登り、息を切らせて到着した頂上は座る場所もないので(展望もない日だったので)すぐに下山しました。
下山路は谷沿いのコースを使いました。
カツラの門が近づくとサンカヨウの群生です。

キヌガサソウが咲き始めていましたので、この後も楽しみです。
帰りに匠神社側の遊歩道を歩いていると、伸び始めのササユリを見つけました。いくつかは蕾が出ています。今月下旬には見ごろになるかもしれません。
**************************************
インタープリター(自然案内人)がガイドする天生県立自然公園
◎催行日 1)7月25日泊・7月26日実施 2)8月1日泊・8月2日実施
◎ツアーの詳しい案内と予約
○こちらは登山ツアーではありません(籾糠山には登りませんので予めご了承ください)
例年より10日以上遅い開通です。
これで飛騨地方の冬季閉鎖はすべてなくなりました。
今日はさっそく籾糠山へ出かけてみました。
家を9時15分に出発。河合町から峠へと入りました。
約1時間で峠にある駐車場に到着すると、すでに満車状態。あふれた車が路上駐車していました。

ちょうど帰るところだった新聞社の車が出たので、係の人にお願いして入れさせてもらいました。
ちなみにこの時点で飛騨ナンバーの車は2台目だったそうです。県外の車も多く、関東や関西のナンバーも目立ちました。
自然保護協力金500円(任意)を収め、入山します。
湿原や原生林までを目的とした人も多く、籾糠山へ行く人の数と合わせて200人以上はいたのでは。
開通が遅れたので、第一湿原のミズバショウは花がほとんど終わっていました。

代わってリュウキンカやコバイケイソウが咲き始めていました。
湿原周辺にはさまざまな亜高山帯の植物が見られます。しかし小さくて気付かないものも多く、詳しいガイドと一緒に回ると楽しいことでしょう。
第一湿原から林を下るとまた小さな湿原があり、こちらにはリュウキンカやニリンソウ、サンカヨウなどがお花畑となっていました。
原生林に入り、第二湿原へ。こちらはまだミズバショウが一面に咲いていました。
籾糠山への登りは第二湿原近くの入山口からブナの原生林の急登コースを歩きました。

こちらの道は歩く人も少なく、静かな山歩きが楽しめます。
道沿いにはツバメオモトやバイカオウレン、ミヤマカタバミなどが咲いていました。ユキザサやマイヅルソウはこれからです。
登山道がゆるやかになると、谷から上がってくる主要登山道と合流です。
ベンチが新しくなっていました。
ここから籾糠山までの道は登山者の列ができていました。
頂上直下の急登を登り、息を切らせて到着した頂上は座る場所もないので(展望もない日だったので)すぐに下山しました。
下山路は谷沿いのコースを使いました。
カツラの門が近づくとサンカヨウの群生です。

キヌガサソウが咲き始めていましたので、この後も楽しみです。
帰りに匠神社側の遊歩道を歩いていると、伸び始めのササユリを見つけました。いくつかは蕾が出ています。今月下旬には見ごろになるかもしれません。
**************************************
インタープリター(自然案内人)がガイドする天生県立自然公園
◎催行日 1)7月25日泊・7月26日実施 2)8月1日泊・8月2日実施
◎ツアーの詳しい案内と予約
○こちらは登山ツアーではありません(籾糠山には登りませんので予めご了承ください)
2010年06月06日
サラサドウダンは?新緑の位山
サラサドウダンは深山に自生するドウダンツツジ科の樹木です。
位山の頂上一帯に自生しているものは、冬の間の積雪のためあまり背が伸びません。
そろそろ花が咲く頃と、風邪気味の体にむち打って出かけてみました。
ダナ平から往復するため、林道を入山口まで車を走らせます。
林道は上り始めから中ほどまでが荒れています。平日は舗装道路工事が行われていますが、通行はできます。
駐車場からは青空にくっきりと浮かぶ飛騨山脈が見えました。

北の端には劒岳と立山も。
巨石群の登山道を登り、天の岩戸を経由して白山展望台まで約50分。
途中からサラサドウダンの中を歩きますが、花が咲くどころか蕾さえまばらでした。

花の見ごろが目的なら6月中旬が狙い目のようです。
白山展望台にはスキー場から登ってきた登山者がつぎつぎと到着。

地元の登山者はダナ平から登る傾向があります。ふたつの登山口から登ってきた人たちで賑わってきました。

展望台から見る白山とその南には別山。
積雪期には見える川上岳は低潅木に隠れて今は見えません。
帰りは頂上に回り乗鞍展望台に下ります。

ここからは乗鞍が正面に、右手に御嶽が見えています。
御嶽の下に見える平坦な山は舟山(船を逆さにした形)。
帰りは、来た道を戻ります。
駐車場に戻るとサラサドウダンの花を見つけました。

この辺りになると位山頂上とは違いサラサドウダンの木も背が高い。
◎現在募集中
西穂高丸山<6月28日(月)入山>
ツアーの詳細
位山の頂上一帯に自生しているものは、冬の間の積雪のためあまり背が伸びません。
そろそろ花が咲く頃と、風邪気味の体にむち打って出かけてみました。
ダナ平から往復するため、林道を入山口まで車を走らせます。
林道は上り始めから中ほどまでが荒れています。平日は舗装道路工事が行われていますが、通行はできます。
駐車場からは青空にくっきりと浮かぶ飛騨山脈が見えました。

北の端には劒岳と立山も。
巨石群の登山道を登り、天の岩戸を経由して白山展望台まで約50分。
途中からサラサドウダンの中を歩きますが、花が咲くどころか蕾さえまばらでした。

花の見ごろが目的なら6月中旬が狙い目のようです。
白山展望台にはスキー場から登ってきた登山者がつぎつぎと到着。

地元の登山者はダナ平から登る傾向があります。ふたつの登山口から登ってきた人たちで賑わってきました。

展望台から見る白山とその南には別山。
積雪期には見える川上岳は低潅木に隠れて今は見えません。
帰りは頂上に回り乗鞍展望台に下ります。

ここからは乗鞍が正面に、右手に御嶽が見えています。
御嶽の下に見える平坦な山は舟山(船を逆さにした形)。
帰りは、来た道を戻ります。
駐車場に戻るとサラサドウダンの花を見つけました。

この辺りになると位山頂上とは違いサラサドウダンの木も背が高い。
◎現在募集中
西穂高丸山<6月28日(月)入山>
ツアーの詳細
2010年05月31日
新緑の中を歩く〜奥穂高岳入山口まで
新緑が目にも鮮やかな季節になりました。
飛騨の低山の残雪もほとんど消えて、山歩きには最適な時期を迎えました。
限られた時間の中で登れる低山を選び頂上を目指すこともひとつの楽しみ方。しかし飛騨山脈高峰の頂上までは無理でも、その途中を目的地にすれば飛騨山脈のふところを感じる山歩きが体験できます。
例を挙げれば新穂高を基点に、わさび平経由で鏡平まで。そして今回の白出沢出合から奥穂高岳登山道を笠ケ岳の好展望地まで・・・などです。
このふたつの共通点は最終目的地からの飛騨山脈展望が素晴らしいこと。余裕を持って日帰りできることです。
鏡平の場合は往復約7〜8時間。早朝に歩き始め、昼前には下山するようにします。
7月10日から鏡平山荘が小屋開けするので、名物のラーメンを楽しみに登ると頑張れます。
詳しくは鏡平山荘往復<2008.7.19入山>
もうひとつは新穂高から右俣林道を穂高平経由で白出沢出合(奥穂高岳登山口)、さらに奥穂高岳への登山道を40分ほど登る山歩きです。
往復約5〜6時間と比較的楽に歩けるコースなので、登山初心者でも安心して楽しめます。
この日は林道歩きを楽しむグループや家族連れに出会いました。
まずは穂高平まで。
ロープウェイ駐車場脇のゲートを入り右俣林道を進みます。
再びゲートのある小鍋谷に架かる橋を渡った後200mほど歩いたら、時間稼ぎとトレッキング気分を味わうため穂高平への近道に入ります。
斜面のトラバースを林道を左下に見ながら進みます。深い樹林の前方が明るくなり、せせらぎの音が聞こえたら穂高平に到着です。

穂高平小屋の後方に蒲田富士。北穂高岳は雲の中。
牧場脇にはニリンソウが咲いていました。
ふたたび新緑の林道を歩いていきます。まだ数少ないですが沿道には花も咲き始めていました。エンレイソウやシロバナエンレイソウも見ることができました。

柳谷の砂防施設のカーブから見た白出沢へ向かう道。

雪形が現われた山は中岳?陽射しに新緑が鮮やか。
白出沢までに林道はいくつもの小さな沢と合流します。
沢にはまだ雪が残り、雪解け水がたっぷりと流れていました。
白出沢の小屋跡に到着。トイレは閉まって使えません。
ここから樹林帯に入り、奥穂高への登山道を30〜40分登ります。
穂高岳山荘へのボッカ道だけあり、よく整備されています。しかし小屋開けしたばかりなので、冬の間に多少荒れたところがそのままです。
コメツガなどの針葉樹林帯が明るくなってくると、左手に白出沢が見えてきます。

ちょうどよい休憩ポイントの一つです。
ここから程なくして、樹林帯を抜け低潅木帯になります。

このあたりの登山道にはまだ雪が残り、折れた木が道をふさいでいました。
ここで突然左手から驚いたような声がしました。
声のした方を見ると、折れ曲がった木々の向こう、5mほどの距離にカモシカがいました。

檻の様な低潅木に守られていると思ったのか、カモシカは逃げることなく木の芽を何度か食むとゆっくり沢の方へ下りて行きました。
熊でなくて良かったと思いながらも、うれしい野生動物とのしばしの遭遇でした。
谷にある低潅木帯を左の尾根に上がると、そこが目的の笠ケ岳の展望地です。
数人が休めるスペースがあり、ここで眺めを楽しみながらコーヒータイム。
思いがけずニリンソウが咲いていました。

花の季節はもうそこまで来ています。
軽食とコーヒーを楽しんでいるうちに雲に隠れていた笠ケ岳が顔を出しました。

笠の右手には小笠も見えています。

杓子平には残雪がまだたっぷりと残っています。

雪が消えるのは7月中旬〜下旬。
この先の穂高岳山荘に向かう道は長くて厳しい登りとなり、今の時期はまだアイゼンやピッケルが必要となります。しかし今回はここまで。帰りは来たコースを戻ります。天候に恵まれれば奥穂を眺めながらの山歩き。短時間の日帰りとしては最適なコースです。
***************************************************************
◎現在募集中
西穂高丸山<6月28日(月)入山>
ツアーの詳細
飛騨の低山の残雪もほとんど消えて、山歩きには最適な時期を迎えました。
限られた時間の中で登れる低山を選び頂上を目指すこともひとつの楽しみ方。しかし飛騨山脈高峰の頂上までは無理でも、その途中を目的地にすれば飛騨山脈のふところを感じる山歩きが体験できます。
例を挙げれば新穂高を基点に、わさび平経由で鏡平まで。そして今回の白出沢出合から奥穂高岳登山道を笠ケ岳の好展望地まで・・・などです。
このふたつの共通点は最終目的地からの飛騨山脈展望が素晴らしいこと。余裕を持って日帰りできることです。
鏡平の場合は往復約7〜8時間。早朝に歩き始め、昼前には下山するようにします。
7月10日から鏡平山荘が小屋開けするので、名物のラーメンを楽しみに登ると頑張れます。
詳しくは鏡平山荘往復<2008.7.19入山>
もうひとつは新穂高から右俣林道を穂高平経由で白出沢出合(奥穂高岳登山口)、さらに奥穂高岳への登山道を40分ほど登る山歩きです。
往復約5〜6時間と比較的楽に歩けるコースなので、登山初心者でも安心して楽しめます。
この日は林道歩きを楽しむグループや家族連れに出会いました。
まずは穂高平まで。
ロープウェイ駐車場脇のゲートを入り右俣林道を進みます。
再びゲートのある小鍋谷に架かる橋を渡った後200mほど歩いたら、時間稼ぎとトレッキング気分を味わうため穂高平への近道に入ります。
斜面のトラバースを林道を左下に見ながら進みます。深い樹林の前方が明るくなり、せせらぎの音が聞こえたら穂高平に到着です。

穂高平小屋の後方に蒲田富士。北穂高岳は雲の中。
牧場脇にはニリンソウが咲いていました。
ふたたび新緑の林道を歩いていきます。まだ数少ないですが沿道には花も咲き始めていました。エンレイソウやシロバナエンレイソウも見ることができました。

柳谷の砂防施設のカーブから見た白出沢へ向かう道。

雪形が現われた山は中岳?陽射しに新緑が鮮やか。
白出沢までに林道はいくつもの小さな沢と合流します。
沢にはまだ雪が残り、雪解け水がたっぷりと流れていました。
白出沢の小屋跡に到着。トイレは閉まって使えません。
ここから樹林帯に入り、奥穂高への登山道を30〜40分登ります。
穂高岳山荘へのボッカ道だけあり、よく整備されています。しかし小屋開けしたばかりなので、冬の間に多少荒れたところがそのままです。
コメツガなどの針葉樹林帯が明るくなってくると、左手に白出沢が見えてきます。

ちょうどよい休憩ポイントの一つです。
ここから程なくして、樹林帯を抜け低潅木帯になります。

このあたりの登山道にはまだ雪が残り、折れた木が道をふさいでいました。
ここで突然左手から驚いたような声がしました。
声のした方を見ると、折れ曲がった木々の向こう、5mほどの距離にカモシカがいました。

檻の様な低潅木に守られていると思ったのか、カモシカは逃げることなく木の芽を何度か食むとゆっくり沢の方へ下りて行きました。
熊でなくて良かったと思いながらも、うれしい野生動物とのしばしの遭遇でした。
谷にある低潅木帯を左の尾根に上がると、そこが目的の笠ケ岳の展望地です。
数人が休めるスペースがあり、ここで眺めを楽しみながらコーヒータイム。
思いがけずニリンソウが咲いていました。

花の季節はもうそこまで来ています。
軽食とコーヒーを楽しんでいるうちに雲に隠れていた笠ケ岳が顔を出しました。

笠の右手には小笠も見えています。

杓子平には残雪がまだたっぷりと残っています。

雪が消えるのは7月中旬〜下旬。
この先の穂高岳山荘に向かう道は長くて厳しい登りとなり、今の時期はまだアイゼンやピッケルが必要となります。しかし今回はここまで。帰りは来たコースを戻ります。天候に恵まれれば奥穂を眺めながらの山歩き。短時間の日帰りとしては最適なコースです。
***************************************************************
◎現在募集中
西穂高丸山<6月28日(月)入山>
ツアーの詳細
2010年05月16日
乗鞍剣ケ峰へ春山登山
快晴の昨日(5月15日)、いよいよ乗鞍スカイラインが開通しました。
同時に(個人的に)恒例にしている開通日剣ケ峰登山の日でもあります。
家族を送りだし、ようやく家を出たのは9時20分。とっくに開通日の始発は出ています。
バス停のあるほおのき平駐車場に着いた時は、1台のバスがもうじき出るところでした。
係の人が待たせてくれて、10時発の便に乗ることができました。・・・あわてて日焼け止めを車の中に置いてきてしまいましたが。おかげで現在も顔がひりひりします。
スカイラインからはまず白山が見えてきて、すぐに穂高と槍がくっきりと青い空に浮かんでいるのが目に飛び込んできました。
四ツ岳下のヘアピンカーブの両わきには巨大な雪の壁が現われてきました。次の大丹生岳下のカーブもなかなかのものです。
桔梗ヶ原に出ると、その周辺の雪は大分解けてきていました。
ほどなく畳平に到着すると、ちょうど開山祭の真っ最中。

鏡開きが終わり、地元丹生川板殿地区の獅子舞が奉納中。後方は富士見岳。
畳平ですでに標高は2702m。鶴ヶ池はまだ雪に埋もれています。
10時50分に剣ケ峰へと出発しました。
鶴ヶ池を半周し、大黒岳と富士見岳との鞍部から林道を上ります。
鞍部にある富士見岳の標識にはびっしりとエビの尻尾が付いていました。

林道にはまだ雪がたくさん残り、20mほど歩いただけで道は消えました。
雪質が硬く、林道ではなく山の斜面をトラバースする形になります。
アイゼンはよく効きました。こうしたところが登山の練習になるのです。
開通日に剣ケ峰をめざすには、できるだけ冬に近い3000m級の山を登る良い機会だからなんですね〜。しかも事情により昨年から早朝に山へと出かけられなくなった自分には、短時間でアプローチできる貴重な山でもあるのです。ありがたや。
閉鎖になったコロナ観測所のある摩利支天岳下を肩ノ小屋に向かう林道も同様の状態です。
しかもこちらはバランスを崩して斜面から滑れば、100m以上も落ちていきます。

でも帰りに通過した時には(多分、肩ノ小屋の)スタッフがスコップで斜面を削り道を付けていたので、現在は比較的安全に通過できます。
肩ノ小屋へ向かう摩利支天岳の鞍部から見ると、剣ケ峰へ向かう人の列が。
ほとんどが位ヶ原からのスキーヤー達です。
位ヶ原までバスが入るようになったことと、15日が土曜日であることが理由です。
こちらはまず肩ノ小屋から朝日岳への斜面を直登します。
途中で斜面をトラバースしながら進むと、件のスキーヤーの群れに合流。

この日は剣ケ峰に登る登山者の9割方が、この位ヶ原からのスキーヤーでした。
実は写真に写っているスキーヤー軍団を、スキーを担いでいない自分は朝日岳の鞍部に乗越す前に追い越してしまいました。位ヶ原からのスキー登山の大変さがよ〜く分ります。
この日は肩ノ小屋から約35分で朝日岳の鞍部に乗越。
ちなみに下の写真に写る皆さんが上の写真のスキーヤーの列の先頭にいた人たちです。

鞍部から振り返ればご覧のような大展望でした。
あとは稜線を蚕玉岳から剣ケ峰へと向かいます。

頂上神社の壁にも白く雪がこびりつき、剣ケ峰は陽射しを浴びて本当に美しい眺め。大勢の登山者が頂上に登っていました。
10分ほどで頂上へ到着。鳥居のある飛騨側へ回り、昼食にしました。

鳥居にもびっしりとエビの尻尾が付着。ここまでくると芸術。
大日岳と今日はくっきりと見える御嶽山。

大日岳の頂上にも珍しくスキーヤーがいます。一人が高天ケ原へと滑降。楽しみ方はいろいろ、気候に恵まれた今日は何でもありだ。
まるで冬のように空気が澄んで、飛騨山脈の名峰が今日ははっきり見える。

拡大して見る時はクリックを!
特に気になる穂高連峰と槍ケ岳の眺めはアップで。

次に自分の一番好きな飛騨の山、笠ケ岳。

この展望はゴールデンウィークを思い出します。
また寒くなったりするのだろうか・・・?
スキーヤーはあっというまに滑り降りていきますが、実は自分のような登山者もすごく早く下っていけます。
もちろん朝日岳鞍部からはアイゼンを効かせてゆっくりと靴底の接地はフラットに。それでも肩ノ小屋まで10分で下りてしまいました。
畳平の上部からは鶴ヶ池の向こうにも飛騨山脈が見えていました。

まだしばらくの間は気温が低い日には、畳平周辺の山も登山道が凍ることがあります。
その際は足下に十分お気をつけください。
乗鞍畳平へはほおのき平駐車場からバスに乗り換えです。
詳しくは濃飛バスのサイトで。時刻表がPDFで用意されています。
******************************************
◎高山グリーンツアーでは夏と秋の乗鞍剣ケ峰に登ります。
7月下旬と9月下旬を予定。催行日が決まり次第ブログで発表します。
ちゃんと準備すれば登山初心者も大丈夫です!ぜひご参加ください。
◎現在募集中
西穂高丸山<6月28日(月)入山>
ツアーの詳細
同時に(個人的に)恒例にしている開通日剣ケ峰登山の日でもあります。
家族を送りだし、ようやく家を出たのは9時20分。とっくに開通日の始発は出ています。
バス停のあるほおのき平駐車場に着いた時は、1台のバスがもうじき出るところでした。
係の人が待たせてくれて、10時発の便に乗ることができました。・・・あわてて日焼け止めを車の中に置いてきてしまいましたが。おかげで現在も顔がひりひりします。
スカイラインからはまず白山が見えてきて、すぐに穂高と槍がくっきりと青い空に浮かんでいるのが目に飛び込んできました。
四ツ岳下のヘアピンカーブの両わきには巨大な雪の壁が現われてきました。次の大丹生岳下のカーブもなかなかのものです。
桔梗ヶ原に出ると、その周辺の雪は大分解けてきていました。
ほどなく畳平に到着すると、ちょうど開山祭の真っ最中。

鏡開きが終わり、地元丹生川板殿地区の獅子舞が奉納中。後方は富士見岳。
畳平ですでに標高は2702m。鶴ヶ池はまだ雪に埋もれています。
10時50分に剣ケ峰へと出発しました。
鶴ヶ池を半周し、大黒岳と富士見岳との鞍部から林道を上ります。
鞍部にある富士見岳の標識にはびっしりとエビの尻尾が付いていました。

林道にはまだ雪がたくさん残り、20mほど歩いただけで道は消えました。
雪質が硬く、林道ではなく山の斜面をトラバースする形になります。
アイゼンはよく効きました。こうしたところが登山の練習になるのです。
開通日に剣ケ峰をめざすには、できるだけ冬に近い3000m級の山を登る良い機会だからなんですね〜。しかも事情により昨年から早朝に山へと出かけられなくなった自分には、短時間でアプローチできる貴重な山でもあるのです。ありがたや。
閉鎖になったコロナ観測所のある摩利支天岳下を肩ノ小屋に向かう林道も同様の状態です。
しかもこちらはバランスを崩して斜面から滑れば、100m以上も落ちていきます。

でも帰りに通過した時には(多分、肩ノ小屋の)スタッフがスコップで斜面を削り道を付けていたので、現在は比較的安全に通過できます。
肩ノ小屋へ向かう摩利支天岳の鞍部から見ると、剣ケ峰へ向かう人の列が。
ほとんどが位ヶ原からのスキーヤー達です。
位ヶ原までバスが入るようになったことと、15日が土曜日であることが理由です。
こちらはまず肩ノ小屋から朝日岳への斜面を直登します。
途中で斜面をトラバースしながら進むと、件のスキーヤーの群れに合流。

この日は剣ケ峰に登る登山者の9割方が、この位ヶ原からのスキーヤーでした。
実は写真に写っているスキーヤー軍団を、スキーを担いでいない自分は朝日岳の鞍部に乗越す前に追い越してしまいました。位ヶ原からのスキー登山の大変さがよ〜く分ります。
この日は肩ノ小屋から約35分で朝日岳の鞍部に乗越。
ちなみに下の写真に写る皆さんが上の写真のスキーヤーの列の先頭にいた人たちです。

鞍部から振り返ればご覧のような大展望でした。
あとは稜線を蚕玉岳から剣ケ峰へと向かいます。

頂上神社の壁にも白く雪がこびりつき、剣ケ峰は陽射しを浴びて本当に美しい眺め。大勢の登山者が頂上に登っていました。
10分ほどで頂上へ到着。鳥居のある飛騨側へ回り、昼食にしました。

鳥居にもびっしりとエビの尻尾が付着。ここまでくると芸術。
大日岳と今日はくっきりと見える御嶽山。

大日岳の頂上にも珍しくスキーヤーがいます。一人が高天ケ原へと滑降。楽しみ方はいろいろ、気候に恵まれた今日は何でもありだ。
まるで冬のように空気が澄んで、飛騨山脈の名峰が今日ははっきり見える。

拡大して見る時はクリックを!
特に気になる穂高連峰と槍ケ岳の眺めはアップで。

次に自分の一番好きな飛騨の山、笠ケ岳。

この展望はゴールデンウィークを思い出します。
また寒くなったりするのだろうか・・・?
スキーヤーはあっというまに滑り降りていきますが、実は自分のような登山者もすごく早く下っていけます。
もちろん朝日岳鞍部からはアイゼンを効かせてゆっくりと靴底の接地はフラットに。それでも肩ノ小屋まで10分で下りてしまいました。
畳平の上部からは鶴ヶ池の向こうにも飛騨山脈が見えていました。

まだしばらくの間は気温が低い日には、畳平周辺の山も登山道が凍ることがあります。
その際は足下に十分お気をつけください。
乗鞍畳平へはほおのき平駐車場からバスに乗り換えです。
詳しくは濃飛バスのサイトで。時刻表がPDFで用意されています。
******************************************
◎高山グリーンツアーでは夏と秋の乗鞍剣ケ峰に登ります。
7月下旬と9月下旬を予定。催行日が決まり次第ブログで発表します。
ちゃんと準備すれば登山初心者も大丈夫です!ぜひご参加ください。
◎現在募集中
西穂高丸山<6月28日(月)入山>
ツアーの詳細
2010年05月03日
残雪の焼岳
ゴールデンウィーク。高山市内は観光客の皆さんで混雑しています。
北アルプスにもたくさんの人が入山していますが、奥穂高岳が現在は非常に危険な状態です。
穂高岳山荘から奥穂高への登山路が凍っており、アイスクライミングの技術が必要だとのことです。温かくなり雪崩れも起きやすくなっていますのでご注意ください。
そんななか、事情により日帰り登山しかできないわたしも、焼岳へ春山日帰り登山に出かけてきました。
◎焼岳<標高2393m(北峰)> 2010年5月1日(土)快晴
中の湯新登山口<10:30発>〜旧登山道分岐<12:00>〜焼岳コル<13:23>〜下山<13:40>〜分岐<14:20>〜登山口<15:25>
安房峠は平湯側がまだゲート閉鎖されており、中の湯登山口へは安房トンネルを抜けて信州側から向かいました。

登山口には主に県外からの車が数台駐車しており(飛騨ナンバー1台、長野・松本は0台でした)、時間から言ってわたしが最後の入山者。
登山口が標高約1500mなので、焼岳までは標高差約900mを登ります。
残雪が多く、登山道で地面の出ている箇所はわずかでした。
まずは樹林帯を登りますが、この日はまだ雪面が硬く、途中でアイゼンを装着。
下りてきた人に上部の状況を聞くと、焼岳の斜面の雪はゆるいとの返事。
気を引き締める。
1時間半で樹林帯を抜け、ブナの疎林に囲まれた広場に到着しました。

無雪期は背の高い笹藪に囲まれていますが、雪におおわれて素晴らしい展望台となっていました。
焼岳を見上げ、大正池を作った崩壊地と無雪期の登山道がある斜面、そして焼岳南峰に向かう尾根を展望します。トレースは崩壊地に沿った斜面をコルに向かって直登していました。
厳冬期から残雪期は雪崩れの心配があるので南峰へ向かう尾根を登り、そのまま南峰から戻るか、南峰直下を北峰間のコルへとトラバースするらしいのですが。ちなみに、南峰への登山道はありません。そのため南峰は立入が禁止され、積雪期にのみ尾根沿いに登ることがルートとしては可能です。コルと南峰間は危険な岩場です。
トレースに従いコルへ直登する場合、ほとんど斜面をトラバースしなくてはならず、足下が崩れたりバランスを崩せば一気に滑落です。
先行する人達はそのトラバース面で苦戦しているようでした。
わたしも短距離となるコルへの直登を選択。しかし先行者のトレースより左のできるだけ崩壊地から離れたコースを行くことにしました。
これで先行者が苦戦しているトラバース面を避けて行けます。
左から伸びる短い支尾根に乗越し、今度はクラスト気味の斜面をゆるやかにトラバース。
その斜面を上から眺めると

休憩できる地点は支尾根に乗越した部分のみ。あとは立ち止まれるくらいで、安全のためには登り続けるしかありません。
2度ほどピッケルを支点に立ち止まっただけで、ほとんど休みなくコルへ到着しました。
コルでは無風だった斜面と違い、飛騨側から冷たい強風が吹きつけていました。
北峰下の岩場を慎重にトラバース。中尾からの登山道の合流点は、北アルプスの大展望が楽しめました。

穂高連峰から槍ケ岳、西釜尾根も見えていました。

西穂高と槍ケ岳をアップで。

眼下には開山間も無い上高地。

南峰と乗鞍岳。霞沢岳も間近に見え、独立峰ならではの大展望でした。
北峰は噴煙たなびき、強い硫黄臭が立ちこめています。

雪が消えて登山道が現われるまで、今回のトラバースが続くルートは気をつける必要があります。南峰へ向かう尾根を行くのが安全面ではやはりいいと感じました。その場合コルへのトラバースは遠慮します・・・。
いずれにしてもアイゼンとピッケルは必要です。
下山にかかった時間が思いの外少なく、所要時間は約5時間でした。休憩が短かったので、参考にはなりませんが。
*********************************************
〜高山グリーンツアーのご案内〜
初夏を迎える西穂高丸山へ
<入山日:6月28日(月)>
お問い合わせ、お申し込みはtel.0577(33)5500(代)までどうぞ
北アルプスにもたくさんの人が入山していますが、奥穂高岳が現在は非常に危険な状態です。
穂高岳山荘から奥穂高への登山路が凍っており、アイスクライミングの技術が必要だとのことです。温かくなり雪崩れも起きやすくなっていますのでご注意ください。
そんななか、事情により日帰り登山しかできないわたしも、焼岳へ春山日帰り登山に出かけてきました。
◎焼岳<標高2393m(北峰)> 2010年5月1日(土)快晴
中の湯新登山口<10:30発>〜旧登山道分岐<12:00>〜焼岳コル<13:23>〜下山<13:40>〜分岐<14:20>〜登山口<15:25>
安房峠は平湯側がまだゲート閉鎖されており、中の湯登山口へは安房トンネルを抜けて信州側から向かいました。

登山口には主に県外からの車が数台駐車しており(飛騨ナンバー1台、長野・松本は0台でした)、時間から言ってわたしが最後の入山者。
登山口が標高約1500mなので、焼岳までは標高差約900mを登ります。
残雪が多く、登山道で地面の出ている箇所はわずかでした。
まずは樹林帯を登りますが、この日はまだ雪面が硬く、途中でアイゼンを装着。
下りてきた人に上部の状況を聞くと、焼岳の斜面の雪はゆるいとの返事。
気を引き締める。
1時間半で樹林帯を抜け、ブナの疎林に囲まれた広場に到着しました。

無雪期は背の高い笹藪に囲まれていますが、雪におおわれて素晴らしい展望台となっていました。
焼岳を見上げ、大正池を作った崩壊地と無雪期の登山道がある斜面、そして焼岳南峰に向かう尾根を展望します。トレースは崩壊地に沿った斜面をコルに向かって直登していました。
厳冬期から残雪期は雪崩れの心配があるので南峰へ向かう尾根を登り、そのまま南峰から戻るか、南峰直下を北峰間のコルへとトラバースするらしいのですが。ちなみに、南峰への登山道はありません。そのため南峰は立入が禁止され、積雪期にのみ尾根沿いに登ることがルートとしては可能です。コルと南峰間は危険な岩場です。
トレースに従いコルへ直登する場合、ほとんど斜面をトラバースしなくてはならず、足下が崩れたりバランスを崩せば一気に滑落です。
先行する人達はそのトラバース面で苦戦しているようでした。
わたしも短距離となるコルへの直登を選択。しかし先行者のトレースより左のできるだけ崩壊地から離れたコースを行くことにしました。
これで先行者が苦戦しているトラバース面を避けて行けます。
左から伸びる短い支尾根に乗越し、今度はクラスト気味の斜面をゆるやかにトラバース。
その斜面を上から眺めると

休憩できる地点は支尾根に乗越した部分のみ。あとは立ち止まれるくらいで、安全のためには登り続けるしかありません。
2度ほどピッケルを支点に立ち止まっただけで、ほとんど休みなくコルへ到着しました。
コルでは無風だった斜面と違い、飛騨側から冷たい強風が吹きつけていました。
北峰下の岩場を慎重にトラバース。中尾からの登山道の合流点は、北アルプスの大展望が楽しめました。

穂高連峰から槍ケ岳、西釜尾根も見えていました。

西穂高と槍ケ岳をアップで。

眼下には開山間も無い上高地。

南峰と乗鞍岳。霞沢岳も間近に見え、独立峰ならではの大展望でした。
北峰は噴煙たなびき、強い硫黄臭が立ちこめています。

雪が消えて登山道が現われるまで、今回のトラバースが続くルートは気をつける必要があります。南峰へ向かう尾根を行くのが安全面ではやはりいいと感じました。その場合コルへのトラバースは遠慮します・・・。
いずれにしてもアイゼンとピッケルは必要です。
下山にかかった時間が思いの外少なく、所要時間は約5時間でした。休憩が短かったので、参考にはなりませんが。
*********************************************
〜高山グリーンツアーのご案内〜
初夏を迎える西穂高丸山へ
<入山日:6月28日(月)>
お問い合わせ、お申し込みはtel.0577(33)5500(代)までどうぞ
2010年04月19日
林道歩いて春の川上岳
春の高山祭が行われた先週は、日本に寒波がやってきて雪まで降らせました。
4月17日(土)は、その最後の寒い日。高山周辺の山には朝まで降った雪が積もっていました。
昨年は単独や、高山グリーンツアーやグループで何度も登った川上岳(かおれだけ)。
実は昨年の11月からツメタ谷側の登山道整備が行われ、大変登りやすくなりました。
その工事現場に遭遇したことからどう整備されたのか気になっていたので、まだ冬季閉鎖中の林道に徒歩で入りこの目で確認してきました。
一之宮町から県道453号線(宮清見線)に入り、宮川沿いに車を走らせていると冬季閉鎖のゲートに突き当たります。

このゲートの先は落石が多く、雪は完全に消えていますが道路に落ちた岩が残されたままです。ここから車を降りてツメタ谷ゲートまで歩きます。
20分ほどで赤いスノーシェッドを通過。

さらに20分でツメタ林道入口に到着しました。

冬季閉鎖が解除されれば車でここまで入ることができます。
駐車スペースはゲートの前に3〜4台分あります。
ここからツメタ林道を進み、今回は宮の大イチイを経由して位山から続く稜線に乗越しました。

大イチイの標識前の崖が少し崩れていました。
標識に従い河原に下りて橋を渡ります。

すると立派な橋に掛け替えられていました。橋の先には木道もあります。
今回は宮の大イチイはパスして、まっすぐ登山道へと進みます。左に短い木道が設けられていますが、何のためのものか不明でした。(もしかして水場?)
雨は降っていませんでしたが、枝に積もった雪が解けて降り注いできました。防水のジャケットと帽子で無事でしたが、用意していなかったら大変なことになっていました。

朝方まで降った雪が登山道に積もっていましたが、それがなければ雪は完全に消えていたようです。
林を出ると笹の斜面。新雪を踏みしめて登りますが、ここの道は整備されず以前のままでした。
上に行くに従い、積雪量が増えてきました。
景色はすっかり冬のようです。

雪に潰された笹で分りにくくなっている登山道を何とか判別し、ジグザグに登って行きます。
やがて平坦な場所に出ると、位山とつながる稜線に乗越しました。

ツメタ谷分岐の標識まで進み、右へ折れます。
川上岳まであと約30分。登山道に残った雪は進むにつれて増えてきました。
樹林帯を抜けると稜線は残雪におおわれ、雪で折れた幹や潰れた枝で正規のルートを外しつつ頂上へ。

歩き始めてほぼ3時間でした。
15分ほど休憩。遮るものがないので、風が吹いてくると汗で濡れた背中が寒い。
吸湿速乾性のあるTシャツでも、そんなにすぐには乾かないものです。
展望はいまひとつでした。
上部がほとんど雲で見えない白山。

目前に見えるはずの御嶽は記憶を頼りに想像するだけ。
川上岳自体の景色は、もう少し残雪の多い時期の方が美しいかもしれません。
下山はツメタ林道登山口へ。
下り始めてすぐ、山之口からの登山者が登ってみえました。
分岐から下り道は滑りやすいので気をつけます。

残雪が少ないので、ショートカットはやめて登山道を忠実にトレース。
樹林帯に入る直前から、ちょっとまだらに黒っぽい川上岳を振り返りました。

最初の急な下りは滑りやすい場所でしたが、昨年の整備によりストッパーやロープが付けられていました。
その後も急な箇所には同様の整備がされて、以前よりも歩きやすくなっています。
特に大幅な整備がされたのは登山口の登り口。

削られた痩せ尾根の直登コースだったのが、尾根の裏に回り込む木道が設置されていました。
以前、奥多摩の同様な場所で下山してきた女性がバランスを崩して林道に転落、死亡した事故がありました。安全に配慮した整備は大変ありがたいことです。
連休には川上岳をはじめ飛騨中部の山は、残雪もほとんど消えることでしょう。
花の季節はもう少し先です。
県道の冬季閉鎖が解かれるころには、登山道沿いに花が咲き始めるのではと思います。
*********************************************
〜高山グリーンツアーのご案内〜
初夏を迎える西穂高丸山へ
<入山日:6月28日(月)>
お問い合わせ、お申し込みはtel.0577(33)5500(代)までどうぞ
4月17日(土)は、その最後の寒い日。高山周辺の山には朝まで降った雪が積もっていました。
昨年は単独や、高山グリーンツアーやグループで何度も登った川上岳(かおれだけ)。
実は昨年の11月からツメタ谷側の登山道整備が行われ、大変登りやすくなりました。
その工事現場に遭遇したことからどう整備されたのか気になっていたので、まだ冬季閉鎖中の林道に徒歩で入りこの目で確認してきました。
一之宮町から県道453号線(宮清見線)に入り、宮川沿いに車を走らせていると冬季閉鎖のゲートに突き当たります。

このゲートの先は落石が多く、雪は完全に消えていますが道路に落ちた岩が残されたままです。ここから車を降りてツメタ谷ゲートまで歩きます。
20分ほどで赤いスノーシェッドを通過。

さらに20分でツメタ林道入口に到着しました。

冬季閉鎖が解除されれば車でここまで入ることができます。
駐車スペースはゲートの前に3〜4台分あります。
ここからツメタ林道を進み、今回は宮の大イチイを経由して位山から続く稜線に乗越しました。

大イチイの標識前の崖が少し崩れていました。
標識に従い河原に下りて橋を渡ります。

すると立派な橋に掛け替えられていました。橋の先には木道もあります。
今回は宮の大イチイはパスして、まっすぐ登山道へと進みます。左に短い木道が設けられていますが、何のためのものか不明でした。(もしかして水場?)
雨は降っていませんでしたが、枝に積もった雪が解けて降り注いできました。防水のジャケットと帽子で無事でしたが、用意していなかったら大変なことになっていました。

朝方まで降った雪が登山道に積もっていましたが、それがなければ雪は完全に消えていたようです。
林を出ると笹の斜面。新雪を踏みしめて登りますが、ここの道は整備されず以前のままでした。
上に行くに従い、積雪量が増えてきました。
景色はすっかり冬のようです。

雪に潰された笹で分りにくくなっている登山道を何とか判別し、ジグザグに登って行きます。
やがて平坦な場所に出ると、位山とつながる稜線に乗越しました。

ツメタ谷分岐の標識まで進み、右へ折れます。
川上岳まであと約30分。登山道に残った雪は進むにつれて増えてきました。
樹林帯を抜けると稜線は残雪におおわれ、雪で折れた幹や潰れた枝で正規のルートを外しつつ頂上へ。

歩き始めてほぼ3時間でした。
15分ほど休憩。遮るものがないので、風が吹いてくると汗で濡れた背中が寒い。
吸湿速乾性のあるTシャツでも、そんなにすぐには乾かないものです。
展望はいまひとつでした。
上部がほとんど雲で見えない白山。

目前に見えるはずの御嶽は記憶を頼りに想像するだけ。
川上岳自体の景色は、もう少し残雪の多い時期の方が美しいかもしれません。
下山はツメタ林道登山口へ。
下り始めてすぐ、山之口からの登山者が登ってみえました。
分岐から下り道は滑りやすいので気をつけます。

残雪が少ないので、ショートカットはやめて登山道を忠実にトレース。
樹林帯に入る直前から、ちょっとまだらに黒っぽい川上岳を振り返りました。

最初の急な下りは滑りやすい場所でしたが、昨年の整備によりストッパーやロープが付けられていました。
その後も急な箇所には同様の整備がされて、以前よりも歩きやすくなっています。
特に大幅な整備がされたのは登山口の登り口。

削られた痩せ尾根の直登コースだったのが、尾根の裏に回り込む木道が設置されていました。
以前、奥多摩の同様な場所で下山してきた女性がバランスを崩して林道に転落、死亡した事故がありました。安全に配慮した整備は大変ありがたいことです。
連休には川上岳をはじめ飛騨中部の山は、残雪もほとんど消えることでしょう。
花の季節はもう少し先です。
県道の冬季閉鎖が解かれるころには、登山道沿いに花が咲き始めるのではと思います。
*********************************************
〜高山グリーンツアーのご案内〜
初夏を迎える西穂高丸山へ
<入山日:6月28日(月)>
お問い合わせ、お申し込みはtel.0577(33)5500(代)までどうぞ
2010年04月11日
低山バンザイ!〜残雪の猪臥山
昨日は全国的に晴れとなり、春の山を登る人も多かったようです。
低山でも飛騨北中部にある山は、1500m付近にまだ雪が残り、しばらくは春山が楽しめます。
今回登ったのは「猪臥山(いぶしやま・いのぶせやま他いろいろ)」。高山市清見町と飛騨市古川町の境界線上にある山です。
古川側からは林道が頂上直下まであり、春スキーに訪れる人が多いコース。
いっぽう、清見町側は彦谷の大規模林道「卯の花街道」に登山口があり、長い尾根歩きを経て頂上へ。下山はU字の稜線続きの道を下る歩きがいのあるコースです。
彦谷一帯は人工林と自然林が混在する美しい森。「源流の森づくり」という活動を早くから実践してきました。そのため彦谷からの猪臥山登山は、森の風景が先へ進むにつれ変化し飽きることがありません。
花の季節はまだ先ですが、天候の良い日に登れば今だ多くの雪をたたえた山々の展望が登山者を迎えてくれます。
登山口は猪臥山トンネルの手前の空き地にあります。
すでに3台の車が停っていました。
念のため軽アイゼンとピッケルを用意しましたが、スノーシューは持ちませんでした。(結局アイゼンは不使用。頂上付近の不安定な稜線でピッケル使用)
10時20分入山。当初の予定より50分ほど遅れてしまいました。
残雪期は全行程6時間ほどが個人的には丁度良いペースだと思いますが、無雪期には休憩込みで5時間を目安にしています。しかし今回は入山が遅れたので、5分休憩2回、昼食20分とし、約5時間で残雪期の全行程を終えました。
入山してしばらくは雪の消えた広葉樹林帯を進みます。
斜面をジグザグに上がり尾根の末端にたどりつけば、後はずっと尾根を歩き続けます。

小さなピークのアップダウンを繰り返し、右手に目指す猪臥山が見えてくると急登の続くカラマツの尾根歩きになります。
左手の樹林の間に白山が見えてくるあたりから尾根に残雪が現れました。

雪の厚みはさほどなく硬く締まっていましたが、今後は雪解けが進み歩きにくくなるかもしれません。
長く感じる尾根登り。猪臥山から続く稜線に乗越すまで続きます。
前方に見覚えのある岩が見えたところで、稜線に乗越すまであとわずかです。

ここからはカラマツの広い稜線歩き。もちろん雪で登山道は見えません。
ポイントは稜線を外れないことです。前方には裸木の間に猪臥山に続く山が見えています。

広い尾根が細くなり、隣のピークとの鞍部に下り登り返すとコース唯一の杉林となります。

林を抜けるとさらに登りが続きますが、今度は笹の斜面となります。これまでとは違い、木々の密度が下がり展望がよくなります。右手には猪臥山の鉄塔と御嶽が見えていました。
雪に隠れた笹の斜面は時折り踏み抜いてしまいます。夏道は右寄りにあるはずなので、なるべく右側を歩くようにしました。時々雪のない夏道が現れるので確認できます。
登り着いたところが、猪臥山の主稜線。

マムシ注意の標識がなつかしい。
稜線にはたっぷりと雪が残っていました。細い稜線の上に残雪が乗っかっていました。びびるほど危険ではありませんが、雪が崩れて落ちないように気をつけます。
ここからは気持ちの良い展望を楽しみながら歩いていきます。

目指す猪臥山のピーク。その下の笹の斜面の向こうに穂高連峰が現れました。
12時37分、猪臥山頂上到着。

白山は雲に隠れていましたが、とにかく360度の大展望。

穂高連峰から続く飛騨山脈。

猪臥山の祠の向こうに見えるのは乗鞍連峰。
飛騨の東西の県境の山々がすべて見えました。
13時、下山開始。
猪臥山トンネルの上をまたぐ稜線はアップダウンがきつく、特に下りは要注意。
頂上直下の駐車場のさらに下から林道がこの急斜面下の鞍部まで延びているので、もし不安ならこちらを歩くこともできます。
鞍部から今度は急斜面の登り。振り返れば猪臥山頂上が。

U字のコースの下山路は登りとは逆方向に歩いていきます。
しばらくカラマツ林の尾根をアップダウンを繰り返し、巨大鉄塔の立つ広場に到着。

雪に埋もれた林道を10分ほど下ると、背の高いガードレールのつなぎ目が彦谷へ下る登山路への入口になっています。林道をそのまま下ると、まったく別の場所へ行ってしまいます。

ガードレールを抜けるといったん小ピークを一つ越えて、その後は下るだけです。
私の前に入山した人が間違えて右手のピークに向かったために、そちらに踏み跡が付いてしまったので釣られて行かないようにご注意。谷の左側に下る登山道があります。
途中でカモシカの新しい足跡が下山路に沿って付いていました。

この山域はカモシカに遭遇したという話をよく聞く場所です。
原生林の雰囲気を楽しみながら尾根を下っていき、やがて展望がなくなり細尾根で写真のような幹が現われたら登山路は左に下って終了です。

尾根から下りたところは廃道の終点。

逆回りの登山路の入山口です。
あとは廃道を10分弱歩いて林道分岐、ゲート脇を抜ければ大規模林道「卯の花街道」。
トンネルの方へ数分歩いて、15時20分に入山口に着きました。
ほぼ5時間で一回りした山歩きでした。
余裕のある山行なら、やはり6時間はかけて歩きたいところです。
****************************************
締切り間近!福地山トレッキングツアー<4月21日(水)入山>の参加者を募集しています。
高山グリーンツアー「残雪の福地山トレッキング」のお申し込みは
◎ネット予約
◎電話:0577-33-5000(代)
低山でも飛騨北中部にある山は、1500m付近にまだ雪が残り、しばらくは春山が楽しめます。
今回登ったのは「猪臥山(いぶしやま・いのぶせやま他いろいろ)」。高山市清見町と飛騨市古川町の境界線上にある山です。
古川側からは林道が頂上直下まであり、春スキーに訪れる人が多いコース。
いっぽう、清見町側は彦谷の大規模林道「卯の花街道」に登山口があり、長い尾根歩きを経て頂上へ。下山はU字の稜線続きの道を下る歩きがいのあるコースです。
彦谷一帯は人工林と自然林が混在する美しい森。「源流の森づくり」という活動を早くから実践してきました。そのため彦谷からの猪臥山登山は、森の風景が先へ進むにつれ変化し飽きることがありません。
花の季節はまだ先ですが、天候の良い日に登れば今だ多くの雪をたたえた山々の展望が登山者を迎えてくれます。
登山口は猪臥山トンネルの手前の空き地にあります。
すでに3台の車が停っていました。
念のため軽アイゼンとピッケルを用意しましたが、スノーシューは持ちませんでした。(結局アイゼンは不使用。頂上付近の不安定な稜線でピッケル使用)
10時20分入山。当初の予定より50分ほど遅れてしまいました。
残雪期は全行程6時間ほどが個人的には丁度良いペースだと思いますが、無雪期には休憩込みで5時間を目安にしています。しかし今回は入山が遅れたので、5分休憩2回、昼食20分とし、約5時間で残雪期の全行程を終えました。
入山してしばらくは雪の消えた広葉樹林帯を進みます。
斜面をジグザグに上がり尾根の末端にたどりつけば、後はずっと尾根を歩き続けます。

小さなピークのアップダウンを繰り返し、右手に目指す猪臥山が見えてくると急登の続くカラマツの尾根歩きになります。
左手の樹林の間に白山が見えてくるあたりから尾根に残雪が現れました。

雪の厚みはさほどなく硬く締まっていましたが、今後は雪解けが進み歩きにくくなるかもしれません。
長く感じる尾根登り。猪臥山から続く稜線に乗越すまで続きます。
前方に見覚えのある岩が見えたところで、稜線に乗越すまであとわずかです。

ここからはカラマツの広い稜線歩き。もちろん雪で登山道は見えません。
ポイントは稜線を外れないことです。前方には裸木の間に猪臥山に続く山が見えています。

広い尾根が細くなり、隣のピークとの鞍部に下り登り返すとコース唯一の杉林となります。

林を抜けるとさらに登りが続きますが、今度は笹の斜面となります。これまでとは違い、木々の密度が下がり展望がよくなります。右手には猪臥山の鉄塔と御嶽が見えていました。
雪に隠れた笹の斜面は時折り踏み抜いてしまいます。夏道は右寄りにあるはずなので、なるべく右側を歩くようにしました。時々雪のない夏道が現れるので確認できます。
登り着いたところが、猪臥山の主稜線。

マムシ注意の標識がなつかしい。
稜線にはたっぷりと雪が残っていました。細い稜線の上に残雪が乗っかっていました。びびるほど危険ではありませんが、雪が崩れて落ちないように気をつけます。
ここからは気持ちの良い展望を楽しみながら歩いていきます。

目指す猪臥山のピーク。その下の笹の斜面の向こうに穂高連峰が現れました。
12時37分、猪臥山頂上到着。

白山は雲に隠れていましたが、とにかく360度の大展望。

穂高連峰から続く飛騨山脈。

猪臥山の祠の向こうに見えるのは乗鞍連峰。
飛騨の東西の県境の山々がすべて見えました。
13時、下山開始。
猪臥山トンネルの上をまたぐ稜線はアップダウンがきつく、特に下りは要注意。
頂上直下の駐車場のさらに下から林道がこの急斜面下の鞍部まで延びているので、もし不安ならこちらを歩くこともできます。
鞍部から今度は急斜面の登り。振り返れば猪臥山頂上が。

U字のコースの下山路は登りとは逆方向に歩いていきます。
しばらくカラマツ林の尾根をアップダウンを繰り返し、巨大鉄塔の立つ広場に到着。

雪に埋もれた林道を10分ほど下ると、背の高いガードレールのつなぎ目が彦谷へ下る登山路への入口になっています。林道をそのまま下ると、まったく別の場所へ行ってしまいます。

ガードレールを抜けるといったん小ピークを一つ越えて、その後は下るだけです。
私の前に入山した人が間違えて右手のピークに向かったために、そちらに踏み跡が付いてしまったので釣られて行かないようにご注意。谷の左側に下る登山道があります。
途中でカモシカの新しい足跡が下山路に沿って付いていました。

この山域はカモシカに遭遇したという話をよく聞く場所です。
原生林の雰囲気を楽しみながら尾根を下っていき、やがて展望がなくなり細尾根で写真のような幹が現われたら登山路は左に下って終了です。

尾根から下りたところは廃道の終点。

逆回りの登山路の入山口です。
あとは廃道を10分弱歩いて林道分岐、ゲート脇を抜ければ大規模林道「卯の花街道」。
トンネルの方へ数分歩いて、15時20分に入山口に着きました。
ほぼ5時間で一回りした山歩きでした。
余裕のある山行なら、やはり6時間はかけて歩きたいところです。
****************************************
締切り間近!福地山トレッキングツアー<4月21日(水)入山>の参加者を募集しています。
高山グリーンツアー「残雪の福地山トレッキング」のお申し込みは
◎ネット予約
◎電話:0577-33-5000(代)
2010年04月08日
原山歩きのすすめ

原山の遊歩道沿いにある貯水池から旧ゲレンデに出る時に見えるのは、黒部五郎岳。
飛騨高山にも春が来ました。今日は格別温かな一日でした。
久しぶりに原山に登り、展望を楽しむには最適な天候です。
2時間もあればゲレンデと頂上をゆっくり往復。
今日はいつもの遊歩道ではなく、ゲレンデから林道に入り頂上に尾根を直登しました。

ここがゲレンデの最上部。
林道を左に入り、しばらく歩くと右にある尾根に入山口が見えてきます。
その先には切り開かれた広場があり、吹き流しが左右に立っています。

吹き流しはパラグライダーの飛行の際に、風を見るためのもの。
休日にはパラが空を飛んでいる様子を目撃できるでしょう。
山の保全作業道入口。

入山の際の注意書きが書かれています。
頂上までは尾根をほぼ直登。短いですが気持ちの良い登山道です。

45度はありそうな急登ののち岩場を回り込めば林を抜けます。
笹の中を頂上へまっすぐの登り。

振り返れば展望が広がっています。
トイレ(まだ冬季閉鎖中)が設置された頂上からは、高山市街と飛騨山脈の大展望。

ここは乗鞍岳と御嶽は見えませんが、左手には白山が見えています。
古い町並だけが飛騨高山ではありません。ぜひ観光旅行の荷物にトレッキングシューズと小さなザックを加えて、原山や松倉城趾へ登ってみてはいかがでしょう。
登りの際に出会った男性は、松倉観音から登ってきたとおっしゃっていました。
これだとプラス2時間弱。でも松倉城趾からなら、乗鞍も御嶽も見ることができます。
****************************************
さて、福地山トレッキングツアー<4月21日(水)入山>の参加者を募集しています。
高山グリーンツアー「残雪の福地山トレッキング」のお申し込みは
◎ネット予約
◎電話:0577-33-5000(代)
2010年04月04日
低山バンザイ!〜下呂白草山
春が来た飛騨地方。祭屋台も飾り付けが始りました。
高山周辺の山は、まだ標高1500mあたりに雪が残る時期ですが、桜が満開の南飛騨では無雪期登山が楽しめます。
今回は下呂市にある白草山。
3月には早々と多くの登山者が訪れ、登山道もしっかりと管理されています。
高山方面から行く場合は、国道41号線で下呂に向い、岐阜との分岐を中津川方面(国道257号線)へ進みます。山間を抜けてすぐの信号を乗政キャンプ場方面(県道440号線)へ左折します。キャンプ場を抜けて突き当たりを左折。1〜2分で登山口ゲートに到着。
寺田小屋山登山口に下る途中に駐車スペースがあります。

真っ赤にペイントされた派手なゲート。ずいぶん長いこと道路工事が続いており、登山者の路上駐車が工事車両の邪魔になるためこんなに派手になったのでは(笑)。
ゲート脇にはルートの案内板があります。

ゲートからの登り参考タイム1時間50分と記載されています。
実際、往復で約3時間半の比較的手軽な山歩きが楽しめます(休憩別)。
登山口までは約30分の林道歩き。途中で溶岩が冷えてできた岩壁の下を通過します。
この岩はもろく、この冬に崩れた落石が道にころがっていました。

中には大きく崩れている箇所もありました。
登山口の手前では、つららが下がる岩壁がすごい迫力。

林道を作る際に人の手で削った岩壁です。良く見ると岩にへばりついた枯れ木が落ちないようにくくられています。
この林道は頭上注意です。
林道の終点が沢の流れ込みとの合流地点。木橋を渡り入山します。

登山道にほとんど残雪はなく、あっても歩行に支障はありませんでした。
しばらくは雑木林のなかをジグザクに登って行きます。
10分ほど登ってきたら、斜面の木々が枝打ちされ間引かれていました。

それもかなり大胆に思えるほどです。
以前はちょっと暗かった登山道が、やけに明るいのです。しかしクラシックな登山道の趣は無くなっていました。
とはいえ枝に隠れていた近隣の山が以前よりよく見えるようになりました。

この山は多分、高森山。眺めていると登ってみたくなります。
もう少し高度を上げると箱岩山も見えてきます。

こちらは箱岩山の斜面に突き出た岩壁。
こうした岩が斜面に点在し、これが例の溶岩でできた柱状節理の岩石で四角いところから、箱岩山と呼ばれたのでは、と想像します。
かつては林の中から笹原の尾根に出た印象がありましたが、今回はなんとなく尾根に出てしまいました。

ここからは小さなピークを越えていく尾根歩きです。

右手には白草山も見えてきます。粉雪も舞ってきました。
後方に歩いてきた尾根を従えながら、前方に三ツ岩が見えてくると、白草山も全体が見えてきます。

三ツ岩の手前から薮が刈られ、三ツ岩の上に出ることができます。
登山道から見上げると人のような岩の後頭部。

見てはいけないものを見てしまったような・・・。
そのまま岩群を乗り越えて登山道に合流。ここから御嶽を拝むまで、あとわずかです。

林を抜けると箱岩山との分岐があり、目の前に御嶽が現れます。
この日は雲が上部にかかり、全体を見ることはできませんでした。
右手に緩やかな曲線を描き、美しい笹原の斜面が白草山に続いています。

雪はもうほとんど残っていません。
途中で男性の4人グループとすれ違い、頂上は独り占めに。

広くて丸い頂上は隠れるところがないので、風をできるだけ除けて30分ほど休憩しました。
御嶽にかかる雲が切れることはなく、時間も限りがあるので下山することに。
帰りに眺めた白草山への尾根です。

拡大してご覧ください。
高山から車で入山口まで往復3時間ほどかかりますが、個人的事情でアプローチ込み7時間制限の登山を強いられている私には、登山時間が短くて済むのがありがたい山の一つです。
御嶽から南西に延びる国境尾根の南端にあるのが(地形図から勝手に判断すると)白草山。その東南には鞍掛峠を経て三国山から小秀山へ尾根が県境に延び、奥山界岳まで山並みは続いています。鞍掛峠から白草山への登山道も一度は登ってみたいと思うのですが、いつになることやら。
****************************************
さて、福地山トレッキングツアー<4月21日(水)入山>の参加者を募集しています。
高山グリーンツアー「残雪の福地山トレッキング」のお申し込みは
◎ネット予約
◎電話:0577-33-5000(代)
高山周辺の山は、まだ標高1500mあたりに雪が残る時期ですが、桜が満開の南飛騨では無雪期登山が楽しめます。
今回は下呂市にある白草山。
3月には早々と多くの登山者が訪れ、登山道もしっかりと管理されています。
高山方面から行く場合は、国道41号線で下呂に向い、岐阜との分岐を中津川方面(国道257号線)へ進みます。山間を抜けてすぐの信号を乗政キャンプ場方面(県道440号線)へ左折します。キャンプ場を抜けて突き当たりを左折。1〜2分で登山口ゲートに到着。
寺田小屋山登山口に下る途中に駐車スペースがあります。

真っ赤にペイントされた派手なゲート。ずいぶん長いこと道路工事が続いており、登山者の路上駐車が工事車両の邪魔になるためこんなに派手になったのでは(笑)。
ゲート脇にはルートの案内板があります。

ゲートからの登り参考タイム1時間50分と記載されています。
実際、往復で約3時間半の比較的手軽な山歩きが楽しめます(休憩別)。
登山口までは約30分の林道歩き。途中で溶岩が冷えてできた岩壁の下を通過します。
この岩はもろく、この冬に崩れた落石が道にころがっていました。

中には大きく崩れている箇所もありました。
登山口の手前では、つららが下がる岩壁がすごい迫力。

林道を作る際に人の手で削った岩壁です。良く見ると岩にへばりついた枯れ木が落ちないようにくくられています。
この林道は頭上注意です。
林道の終点が沢の流れ込みとの合流地点。木橋を渡り入山します。

登山道にほとんど残雪はなく、あっても歩行に支障はありませんでした。
しばらくは雑木林のなかをジグザクに登って行きます。
10分ほど登ってきたら、斜面の木々が枝打ちされ間引かれていました。

それもかなり大胆に思えるほどです。
以前はちょっと暗かった登山道が、やけに明るいのです。しかしクラシックな登山道の趣は無くなっていました。
とはいえ枝に隠れていた近隣の山が以前よりよく見えるようになりました。

この山は多分、高森山。眺めていると登ってみたくなります。
もう少し高度を上げると箱岩山も見えてきます。

こちらは箱岩山の斜面に突き出た岩壁。
こうした岩が斜面に点在し、これが例の溶岩でできた柱状節理の岩石で四角いところから、箱岩山と呼ばれたのでは、と想像します。
かつては林の中から笹原の尾根に出た印象がありましたが、今回はなんとなく尾根に出てしまいました。

ここからは小さなピークを越えていく尾根歩きです。

右手には白草山も見えてきます。粉雪も舞ってきました。
後方に歩いてきた尾根を従えながら、前方に三ツ岩が見えてくると、白草山も全体が見えてきます。

三ツ岩の手前から薮が刈られ、三ツ岩の上に出ることができます。
登山道から見上げると人のような岩の後頭部。

見てはいけないものを見てしまったような・・・。
そのまま岩群を乗り越えて登山道に合流。ここから御嶽を拝むまで、あとわずかです。

林を抜けると箱岩山との分岐があり、目の前に御嶽が現れます。
この日は雲が上部にかかり、全体を見ることはできませんでした。
右手に緩やかな曲線を描き、美しい笹原の斜面が白草山に続いています。

雪はもうほとんど残っていません。
途中で男性の4人グループとすれ違い、頂上は独り占めに。

広くて丸い頂上は隠れるところがないので、風をできるだけ除けて30分ほど休憩しました。
御嶽にかかる雲が切れることはなく、時間も限りがあるので下山することに。
帰りに眺めた白草山への尾根です。

拡大してご覧ください。
高山から車で入山口まで往復3時間ほどかかりますが、個人的事情でアプローチ込み7時間制限の登山を強いられている私には、登山時間が短くて済むのがありがたい山の一つです。
御嶽から南西に延びる国境尾根の南端にあるのが(地形図から勝手に判断すると)白草山。その東南には鞍掛峠を経て三国山から小秀山へ尾根が県境に延び、奥山界岳まで山並みは続いています。鞍掛峠から白草山への登山道も一度は登ってみたいと思うのですが、いつになることやら。
****************************************
さて、福地山トレッキングツアー<4月21日(水)入山>の参加者を募集しています。
高山グリーンツアー「残雪の福地山トレッキング」のお申し込みは
◎ネット予約
◎電話:0577-33-5000(代)
2010年02月23日
低山バンザイ!〜冬の十二ヶ岳
本日の陽気はまるで4月になったかのよう。風もなく、ポカポカの陽射しに春を身近に感じる一日でした。
先週の土曜日に、短時間で登れる山を登ってきました。
◎十二ヶ岳<標高1326.6m>
入山日:2月20日(土)
天候:曇時々晴れ(霧で展望は不良)
11:00入山〜12:50山頂・13:20下山〜14:12入山口(支尾根を下ったので往復した場合の正確な時間は不明)
飛騨の「十二ヶ岳」は、無雪期には手軽に丹生川町の瓜田地区に延びた農道や林道を利用して、山頂直下まで車で行くことができます(もはや登山と言えるかどうか)。
他にはふもとの折敷地から登るもっとも登山道らしい道。そして大萱地区と折敷地地区の境界線にある大規模林道から登る登山道があります。積雪期はこのどちらかを利用するとよいでしょう。

大規模林道の登山口は、駐車スペースが除雪した雪で埋まり利用できません。
距離も標高差もあるのが折敷地からの登山道。少々危険個所もありますので注意が必要です。
今回利用した大規模林道からの登山道は林業のための作業道です。
歩く分にはまったく危険はありません。
しばらくすると水場があり、そこをを過ぎるとすぐに見晴らしが良くなり、畑と農機具小屋が現れます。

ここからは高山市街や位山が展望できます。
作業道歩きは地味です。途中右下方に大規模林道が見えるので、自分がどのあたりにいるのかだいたい見当がつきます。とにかく地道に歩きました。

途中で折敷地からの道と合流します。
この日は折敷地から歩いてきた踏み跡がありました(向かって右が折敷地方面から、左が大規模林道から)。

ここで作業道を外れ、目の前の尾根を直登(ショートカットになります)。ふたたび作業道と合流し、わずかに登ると十二ヶ岳山頂の展望台が見えてきます。
途中で作業道から尾根へ入り、そのまま尾根に沿って登って行きます。
やがて前方に鳥居が見えてきます。

この神社(山域)のゆかりについては「飛騨美濃山語り」の解説が大変分りやすいので紹介しておきます。・・・他の山のことも大変参考になりますよ。
鳥居を抜けると突然目の前に急登が現れます。

無雪期には神社へ登る階段があるのですが、今の時期はただの急な登りです。雪が緩む時期には滑らないように気をつけましょう。
このコース唯一の難所を登りきれば展望台と神社が見えてきます。
無雪期には大きな同定板のある広場の横から上がり、神社(東屋)へ。
先着の方4名が宴会を終えるところでした。
祠の祀られた南西角を除き、外からの風が筒抜け。長時間過ごすにはテントがいると苦笑されていました。中に置いてあった板で囲っての宴会だったようです。

霧により好展望は叶いませんでした。
ちなみに十二ヶ岳とは12の山(域)が見えるということでは無いそうです。
日本各地に同名の山があり、好展望の山を差してそう呼んだとも言われているそう。
登ってきた十二ヶ岳の尾根が眼下に見えています。

入山した日はまだ気温が低く、雪は硬く締まっていました。
今日のような暖かい日は、少し歩きにくくなっているかもしれません。
また寒さがぶり返せば、いったん解けた雪が凍ることも考えられます。
比較的短時間で登れる山ですが、意外と苦労させられることも・・・。踏み跡がない時は道迷いも起こしかねないのでご注意を(基本的には尾根の先に頂上があります)。
********************************************
乗鞍高原スノートレッキングツアー
3月21日(日)入山
ただ今ご予約受付中です!
先週の土曜日に、短時間で登れる山を登ってきました。
◎十二ヶ岳<標高1326.6m>
入山日:2月20日(土)
天候:曇時々晴れ(霧で展望は不良)
11:00入山〜12:50山頂・13:20下山〜14:12入山口(支尾根を下ったので往復した場合の正確な時間は不明)
飛騨の「十二ヶ岳」は、無雪期には手軽に丹生川町の瓜田地区に延びた農道や林道を利用して、山頂直下まで車で行くことができます(もはや登山と言えるかどうか)。
他にはふもとの折敷地から登るもっとも登山道らしい道。そして大萱地区と折敷地地区の境界線にある大規模林道から登る登山道があります。積雪期はこのどちらかを利用するとよいでしょう。

大規模林道の登山口は、駐車スペースが除雪した雪で埋まり利用できません。
距離も標高差もあるのが折敷地からの登山道。少々危険個所もありますので注意が必要です。
今回利用した大規模林道からの登山道は林業のための作業道です。
歩く分にはまったく危険はありません。
しばらくすると水場があり、そこをを過ぎるとすぐに見晴らしが良くなり、畑と農機具小屋が現れます。

ここからは高山市街や位山が展望できます。
作業道歩きは地味です。途中右下方に大規模林道が見えるので、自分がどのあたりにいるのかだいたい見当がつきます。とにかく地道に歩きました。

途中で折敷地からの道と合流します。
この日は折敷地から歩いてきた踏み跡がありました(向かって右が折敷地方面から、左が大規模林道から)。

ここで作業道を外れ、目の前の尾根を直登(ショートカットになります)。ふたたび作業道と合流し、わずかに登ると十二ヶ岳山頂の展望台が見えてきます。
途中で作業道から尾根へ入り、そのまま尾根に沿って登って行きます。
やがて前方に鳥居が見えてきます。

この神社(山域)のゆかりについては「飛騨美濃山語り」の解説が大変分りやすいので紹介しておきます。・・・他の山のことも大変参考になりますよ。
鳥居を抜けると突然目の前に急登が現れます。

無雪期には神社へ登る階段があるのですが、今の時期はただの急な登りです。雪が緩む時期には滑らないように気をつけましょう。
このコース唯一の難所を登りきれば展望台と神社が見えてきます。
無雪期には大きな同定板のある広場の横から上がり、神社(東屋)へ。
先着の方4名が宴会を終えるところでした。
祠の祀られた南西角を除き、外からの風が筒抜け。長時間過ごすにはテントがいると苦笑されていました。中に置いてあった板で囲っての宴会だったようです。

霧により好展望は叶いませんでした。
ちなみに十二ヶ岳とは12の山(域)が見えるということでは無いそうです。
日本各地に同名の山があり、好展望の山を差してそう呼んだとも言われているそう。
登ってきた十二ヶ岳の尾根が眼下に見えています。

入山した日はまだ気温が低く、雪は硬く締まっていました。
今日のような暖かい日は、少し歩きにくくなっているかもしれません。
また寒さがぶり返せば、いったん解けた雪が凍ることも考えられます。
比較的短時間で登れる山ですが、意外と苦労させられることも・・・。踏み跡がない時は道迷いも起こしかねないのでご注意を(基本的には尾根の先に頂上があります)。
********************************************
乗鞍高原スノートレッキングツアー
3月21日(日)入山
ただ今ご予約受付中です!